

近年、メンタル不調を訴える従業員の増加や長時間労働に対する対応として、産業医面談の重要性が高まっています。
しかし、事前準備や周知を行わずに対象となる従業員に面談の通知をしても、面談を断られたり、面談を実施できても効果が上がらず休職してしまったりする可能性があります。
本記事では、産業医面談が必要となる基準や話す内容などについて解説します。
目次
 産業医面談は、従業員の心身の健康管理を目的に行われる
産業医面談は、従業員の心身の健康管理を目的に行われる産業医とは、従業員が健康的に仕事をできるように指導や助言をするために企業が選任した医師です。労働衛生に関する専門的な知識を持ち、従業員との各種面談や職場巡視、衛生委員会への出席などを行います。
産業医面談では、産業医が従業員の健康状態や仕事における悩みなどをヒアリングし、適切な助言や指導をします。
従業員の中には、仕事や健康問題などの悩みを抱えていても「相談したことで職場での自分の立場が不利になるのではないか」と心配し、上司や同僚に相談できない人もいるでしょう。
しかし、産業医には、面談で知り得た従業員の情報を他人に漏らしてはならない守秘義務が課されています。
そのため、「相談したことで職場での自分の立場が不利になるのではないか」と心配している従業員でも、一人で抱え込まずに相談することが期待できます。
また、産業医は医学の専門家として、企業と従業員に対し中立的な立場から意見や助言を述べます。公平な立場にいる第三者に対してなら、率直な意見を打ち明けやすいと感じる従業員もいるでしょう。
【関連記事】【総まとめ】産業医とは?医師との違い・企業での役割・業務内容を解説
 産業医面談の実施は、法律で義務付けられていません。従業員本人の申し出があった場合に実施するため、本人が希望していないのに無理やり面談を受けさせることはできません。
産業医面談の実施は、法律で義務付けられていません。従業員本人の申し出があった場合に実施するため、本人が希望していないのに無理やり面談を受けさせることはできません。
一方で、従業員が心身の健康を損ない労災が起きてしまった場合、業務と労災の因果関係が強く問われます。
企業には、従業員の健康を守るための安全配慮義務があるため、労災が起こる前に面談などを含めて適切に予防策を講じていない場合は、安全配慮義務違反になる可能性があります。
そのため、産業医面談の目的や有用性を従業員に周知し、産業医面談を受けることの重要性を理解してもらうことが大切です。
なお、一定の要件を満たす長時間労働者に対しては、本人の申し出の有無にかかわらず、産業医面談を実施することが義務付けられています。
【参考】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
 産業医面談では、従業員の仕事の状況などの他、仕事以外のことも含めたストレスの要因についての相談が行われます。
産業医面談では、従業員の仕事の状況などの他、仕事以外のことも含めたストレスの要因についての相談が行われます。
睡眠や食事・運動などの生活習慣に関わることや、治療中の病気についての相談(診察ではなく「病院に行ったほうがよいか?」という質問への対応や、健康診断の数値についてなど)を受け、必要に応じて受診勧奨を含めたアドバイスを行います。
その他、職場の愚痴や現状への不満について聞き取りを行うこともあります。
 産業医面談は対面だけでなく、オンラインでも実施可能です。ただし、オンラインでの面談実施の際には以下に留意すべきとされています。
産業医面談は対面だけでなく、オンラインでも実施可能です。ただし、オンラインでの面談実施の際には以下に留意すべきとされています。
【参考】厚生労働省「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年11月19日付け基発1119第2号)」
【関連記事】産業保健活動、オンライン対応がOK、NGなものは?―今さら聞けない産業保健vol.4
 産業医面談が必要となるのは、以下のようなケースです。
産業医面談が必要となるのは、以下のようなケースです。
産業医面談が必要となる基準や面談で話す内容について解説します。
産業医は健康診断結果を確認し、問題のある従業員と面談を行います。事業者は、健康診断等の結果、異常の所見があると診断された労働者について、就業上の措置について、3ヶ月以内に医師の意見を聴かなければなりません。
産業医の役割は、健康診断で異常があった従業員に対して、就業状況や食生活、運動習慣などについて聞き取りをして、改善に向けたアドバイスをすることです。産業医は、疾患の治療はできないため、治療が必要な場合は医療機関の受診を勧めます。
また、産業医は面談内容をもとに、以下の区分で企業に提言します。
| 通常勤務をさせて問題ない場合 | 従業員に改善に向けたアドバイスをして、これまでと同じように勤務させる |
| 就業制限が必要な場合 | 就業内容や就業時間に制限を設けて負担を軽減させる |
| 休職が必要な場合 | 一定期間、療養させる |
企業側は、医師の提言を参考にして、状況を改善するための措置をとらなくてはなりません。
【参考】厚生労働省「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」
【関連記事】【産業医監修】健康診断後、産業医に求められる対応とは?
ストレスチェックで高ストレスと判定された従業員のうち、希望者に対して産業医面談をします。
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡単な検査です。労働安全衛生法により、従業員が50人以上いる事業所では、年1回すべての従業員に対してストレスチェックを実施しなければなりません。
高ストレス者に対する産業医面談では、現在の就労状況、身体面・精神面における健康状態を聴取し、アドバイスや指導をします。高ストレス状態は、うつ病などの疾患につながることもあるため、メンタルヘルス不調の評価をすることも大切です。
面談の結果、早急に対処しなくてはならないと産業医が判断した場合は、従業員の許可を得た上で企業に情報を提供し、職場環境の改善についてアドバイスすることもあります。
【参考】厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
【関連記事】ストレスチェックの高ストレス者への対応は?産業医面談の流れを解説
メンタルヘルス不調の相談があった場合にも、産業医面談をすることがあります。メンタルヘルスの不調の原因には、以下のようなものがあります。
メンタルヘルス不調者に対する産業医面談の目的は、メンタルヘルス不調者が抱えている悩みを聞いて、適切にアドバイスするためです。
不眠症状が続いている場合や希死念慮の症状がある場合などは、早めに医療機関を受診するように指導することもあります。
体調不良が続き、それを理由に遅刻や欠勤といった影響が出ている場合にも、産業医面談が実施されることがあります。
原因不明の体調不良や、ストレスが原因の体調の悪化は、なかなか周囲の理解を得難いこともあります。しかし、産業保健や労働衛生に精通している産業医であれば、従業員の労働環境を理解した上でのアドバイスや指導が期待できるでしょう。産業医との面談の結果、現状の環境で働き続けることが難しいと判断された場合には、時短勤務や休職などの就業制限が必要とする意見書が企業側に提出されることもあります。
一定時間以上の長時間労働を行った場合も、産業医面談の対象となります。面接指導の対象となる条件は、以下のとおりです。
・労働者:時間外・休日労働時間が1カ月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者
・研究開発業務従事者:上記に加えて月100時間超の時間外・休日労働を行った者
・高度プロフェッショナル制度適用者:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者
長時間労働は睡眠・ 休養時間、家庭生活・余暇時間の不足を引き起こし、疲労を蓄積させます。そして、脳や心臓疾患の発症、精神障害、自殺の危険性を高めることも明らかになっているのです。
そのほか、事故や怪我、胃十二指腸潰瘍、過敏性大腸炎、腰痛、月経障害など、さまざまな健康問題を引き起こすリスクも指摘されています。
長時間労働者に対する産業医面談では、現在の就業状況や疲労の蓄積具合を聴取し、健康状態やメンタルヘルス面のチェックを行います。
【参考】厚生労働省「長時間労働者への医師による面接指導制度について」
【関連記事】
長時間労働の原因は?引き起こす問題や防ぐための対策を解説
過重労働とは?健康被害を防ぐために企業が取り組むべき対策を解説
休職希望者に対する産業医面談では、従業員の健康状態や休職の原因をヒアリングするとともに、主治医の診断書を確認します。
復職希望者に対する産業医面談では、休職中の過ごし方や治療の経過などを確認し、職場でやらなければならない業務をこなせるまで心身が回復しているかどうかを判断します。
日常生活が問題なく送れており、主治医から復職可能と言われている場合でも、仕事が元通りにできるまで回復していない可能性もあるため注意が必要です。不安や焦りによって十分に回復できていないにもかかわらず、復職を希望しているケースもあります。
無理に復職すると休職者本人や周囲の従業員に負担がかかり、再度休職してしまう可能性があるため、慎重に心身の状態を確認し復職の可否を判断しなければなりません。

産業医面談を実施する主なメリットには、以下などが挙げられます。
それぞれのメリットについて解説します。
産業医面談の実施は、休職者・離職者の減少につながります。休職や離職にいたる前に、従業員のケアができるためです。
産業医面談では、当該従業員に保健指導をしたり、医療機関の早期受診を促したりします。本人の健康状態を把握して適切な対処をすることで、健康を損ない就業困難になることを防げます。
また、面談内容をもとに従業員のストレス要因を特定し職場環境の改善を行えば、従業員の定着率向上が期待できます。
長時間労働者やストレスチェックで高ストレス判定であった従業員に、適切な就業措置を講じられる点も産業医面談を実施するメリットです。
産業医面談で従業員から聴取した内容を踏まえ、産業医は事業者に当該従業員の休職の必要性の有無や、労働時間・勤務日数などの見直しに関して意見を述べます。
事業者は、医学の専門知識を有する産業医からの意見を踏まえて、従業員の健康状態に応じた適切な就業措置をとれます。
産業医面談を通じて、従業員の健康意識の向上が期待できます。面談を受けることで、従業員が自身の健康状態を正しく把握できるためです。
産業医面談では、健康診断やストレスチェックの結果を踏まえ、従業員に生活習慣の改善策を提案したり、ストレスケアの重要性を説明したりします。
医学の専門家である産業医からのアドバイスを受けることで、健康に関する正しい知識が身につけられるため、健康意識が高まるでしょう。
産業医面談は、健康経営の推進につながります。健康経営とは、従業員の健康保持・増進の取り組みを経営的な視点で考え、戦略的に行う経営手法です。
産業医面談での保健指導により、従業員の健康意識が向上し従業員が自ら心身の健康に気を使うようになることが期待できます。そのため、健康経営を推進するうえで、産業医面談は重要な施策の一つといえます。
【関連記事】
健康経営とは?推進されている背景やメリット、取り組み事例を紹介
健康経営の始め方は?成功につなげるための具体策も解説
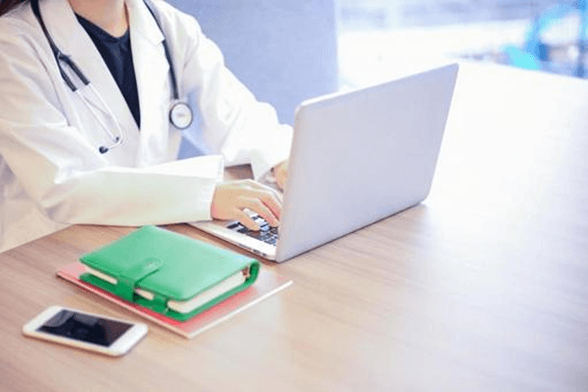 産業医には「守秘義務」と「報告義務」が課されています。
産業医には「守秘義務」と「報告義務」が課されています。
「守秘義務」とは、「業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」という義務です。
産業医に対しては、「労働者の同意がない限り、労働者の健康管理情報を上司および企業側に伝えてはならない」と労働安全衛生法第105条によって規定されています。これらは非常に重い義務であり、刑法には罰則規定もあります。
産業医に課される「報告義務」とは、「労働者の健康上の問題を知ったとき、事業者にその旨を報告する義務」です。従業員が安全・健康に働けるよう労働環境を整備する「安全配慮義務」を果たすためのものです。
これらの2つ相反する義務が課されている産業医ですが、基本的には守秘義務の方が優先となります。そのため、従業員が産業医に話した内容は、基本的には企業側に伝えられることはありません。
【参考】e-GOV法令検索「労働安全衛生法」
【関連記事】産業医面談が休職時に必要な理由とは?タイミングと復帰支援の方法を解説
 産業医面談を実施する際は、事前準備から面談後の対処までいくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、産業医面談における一般的なフローを説明します。
産業医面談を実施する際は、事前準備から面談後の対処までいくつかの手順を踏む必要があります。ここでは、産業医面談における一般的なフローを説明します。
産業医面談の実施が必要となる面談者を選定します。対象者は、前述した産業医面談の実施ケースに当てはまる従業員です。
面談者を選定したら、産業医へ面談者の情報を共有します。選定した理由や面談者の業務内容、解決すべき問題などを共有するとよいでしょう。
産業医面談の日程を組み、面談場所を確保します。面談者の負担にならないよう、人目につかないための配慮が必要です。
場合によってはオンラインで面談を実施するとよいでしょう。面談の日時は、面談者の業務スケジュールも加味して決めましょう。
産業医面談の日程や場所を面談者へ通知します。従業員が面談を受けたくないと感じないよう、面談の目的や必要性・メリットなどを事前に説明しておきましょう。産業医面談は従業員の義務ではないため、強制しないように注意が必要です。
産業医と従業員にて面談を行います。本人が落ち着いて面談を受けられるよう、個室(会議室)を手配するといった配慮をしましょう。
面談記録(産業医面接指導結果報告書)は労働安全衛生規則第52条の6により、5年間の保管義務があります。適切に保管を行いましょう。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生規則第52条の6」
面談の結果をもとに、今後の対処を決定します。産業医面談は問題を未然に防ぎ、解決するための手段です。
面談を行って終了ではなく、産業医の指導・助言により必要に応じて専門医の受診を勧めたり、職場環境の改善に努めたりするなどの対応が求められます。
 従業員が安心して産業医面談を受けられるようにするために、人事労務担当者は以下の配慮が必要です。
従業員が安心して産業医面談を受けられるようにするために、人事労務担当者は以下の配慮が必要です。
それぞれの内容について解説します。
産業医面談の導入についての周知は、社内の掲示板やポスター、メール、社内システムなど、全従業員が分かる方法で行う必要があります。
また、面談は企業のためではなく、従業員の健康のために行うものであることもしっかりと伝えましょう。
産業医面談の対象となった従業員への連絡は、メールやチャット、封書などを利用し、他者に分からないように行いましょう。面談の対象となったことを、他の人に知られたくないと感じる従業員が多いためです。
従業員が面談にいたるハードルを下げるためには、社外に相談窓口を置くのも有効です。心身の不調を社内の人間に知られたくないと思う従業員もいます。不安を抱える従業員にとって、社外の相談窓口や匿名で相談ができるホットラインは、安心できる相談先になるでしょう。
なお、2020年6月の改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の施行に伴い、ハラスメント防止対策も強化されています。ハラスメント相談窓口の設置は義務化されていることを覚えておきましょう。
【参考】
厚生労働省「パワーハラスメント対策が事業主の義務となりました! ~セクシュアルハラスメント等の防止対策も強化されました~」
厚生労働省「2020年(令和2年)6月1日より、職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
【関連記事】
産業医はハラスメント防止にも対応できる?相談窓口における役割や注意点
EAPとは?必要とされる理由や導入メリットをわかりやすく解説
説
産業医面談を実施するだけでなく、職場環境の見直しも大切です。産業医からのアドバイスに従って職場環境の改善、および業務量・業務内容を調整し、従業員が心身ともに健康に働ける環境を整えます。
ある従業員が産業医面談を受けたことをきっかけにより働きやすい環境が整う事例ができれば、他の従業員も前向きに産業医面談を受けられるでしょう。
定期的にストレスチェックや職場環境の調査を実施して、健康状態に不安がある従業員の早期発見に努めましょう。
産業医と連携して、継続的に職場環境の改善に取り組むことも大切です。職場環境の改善は、従業員の健康維持だけでなく、モチベーションアップや業務効率の改善にもつながります。
人事や上司などが同席していると、従業員は本音を言いづらくなってしまうため、基本的に産業医面談は対象となる従業員と産業医だけで実施します。
ただし、復職に向けた面談など、会社側の対応も検討する必要がある場合は、従業員に同意を得た上で人事や上司が同席することもあります。
 産業医面談を受けてくれない従業員がいる場合、原則として強制をしてはなりません。
産業医面談を受けてくれない従業員がいる場合、原則として強制をしてはなりません。
本人の意思のもと受けてもらうために、産業医面談とは何か、面談の必要性やメリットは何かを理解してもらうことが大切です。従業員が産業医面談を拒否する原因として、以下のようなパターンが考えられます。
不利益を被ると考えている従業員に対しては、産業医には守秘義務があることや、公平な立場で相談を受けられる旨を説明しましょう。
産業医面談を受けても問題が解決しないと考えている従業員には、面談後に産業医が意見書を通して企業や本人に対し指導・助言を行ってくれることを説明するとよいでしょう。
また、時間の余裕がないとして産業医面談を拒否する場合は、関連部署とコミュニケーションをとり、業務量・スケジュールを調整するなどの対応が必要です。
【関連記事】「産業医面談は意味ない」と従業員が拒否したら?人事のための対処法を紹介
 自社に産業医がいない場合は、地域の医師会や定期健診を依頼している医療機関などに相談してみるとよいでしょう。産業医を紹介してもらえる可能性があります。
自社に産業医がいない場合は、地域の医師会や定期健診を依頼している医療機関などに相談してみるとよいでしょう。産業医を紹介してもらえる可能性があります。
産業医の選任は、常時雇用する従業員が50人以上いる場合に発生します。近い将来、従業員が50人以上になる見込みがある場合は、早めに産業医を探し産業医面談を実施できる体制を整えておくことが大切です。
従業員が50人未満の場合、産業医の選任は努力義務です。しかし、産業医の選任義務がない小規模事業場であっても事業者には安全配慮義務があり、従業員の健康管理に配慮する必要があります。
産業医の探し方は、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
【関連記事】〈2024年版〉産業医を探す主な5つの方法まとめ
【参考】厚生労働省「産業医について」
 産業医面談に関するよくある質問に回答します。
産業医面談に関するよくある質問に回答します。
従業員が産業医面談を受けてくれない場合、企業側のリスクとしては安全配慮義務違反に見なされてしまう可能性があります。安全配慮義務とは、企業が従業員の生命や安全を守り、労働環境を整える義務です。
従業員には産業医面談を受ける義務はないため、本人が面談を拒否したら強制的に面談を行うことはできません。
しかし、面談を拒否されたからとそのまま放置してしまうのはよくありません。従業員の不調によって労災が発生した場合、産業医面談を行っていないことで安全配慮義務に違反したと見なされてしまう可能性があります。
企業としてのリスクを回避するためにも従業員が産業医面談を受けやすい環境を作り、面談を拒否された場合の対策もしておくとよいでしょう。
具体的には、面談実施にはいたらなかったものの面談を勧奨した履歴や、拒否に対する代替手段を行った記録を残すなどの対策が有用です。
【参考】e-GOV法令検索「労働契約法 第5条(労働者の安全への配慮)」
産業医面談中に従業員の感情が高ぶり、泣いてしまうことは珍しいことではありません。大切なのは、泣いてしまう従業員がいることを事前に想定して産業医面談の環境を整えることです。
たとえば面談場所を普段の作業場所から離れた場所にする、会議室を手配する、防音の効いた場所にするのがよいでしょう。
そういった場所を準備するのが難しい場合、できる限り人のいないタイミングを狙って産業医面談の日程を組むのも有効です。
その他の細かな配慮として、手の届く位置にティッシュを設置しておくのも、泣いてしまった従業員の心を落ち着かせるための対策となります。
産業医面談をスムーズに行い問題を早期解決するために、従業員が話をしやすい環境を作りましょう。
産業医を探す方法には、主に以下の4つがあります。
自社のニーズや予算などを考慮して、自社に合った産業医を選任しましょう。
【関連記事】〈2024年版〉産業医を探す主な5つの方法まとめ
従業員数が50人未満の小規模な事業場で産業医を選任していない場合は、地域産業保健センターを利用して産業医面談を実施するとよいでしょう。
地域産業保健センターとは、従業員数が50人未満の小規模事業者やそこで勤務する従業員の健康管理を支援する機関です。独立行政法人労働者健康安全機構が運営しています。
サービスの利用を希望する場合は、事業場を管轄している地域の窓口に問い合わせましょう。
【関連記事】地域産業保健センター(地さんぽ)とは?役割や利用時の注意点を解説
産業医面談は、自社の会議室など個室で実施しましょう。従業員のプライバシーが守られる環境を用意することが重要です。適しているのは、周囲に声が聞こえない、面談をしている姿が見られない場所です。ただし、業務に支障が出ないよう、職場からあまりにも離れた場所は避けましょう。
万が一面談の内容が他の従業員に漏れてしまうと、面談を受けた本人の心理的安全が確保できず、状況が悪化してしまう恐れがあります。
産業医面談で従業員に対して退職勧奨してもらうことはできません。
退職勧奨とは、会社側が従業員に退職を勧めることで、あくまでも会社と従業員の間で行わなくてはなりません。産業医は、従業員の安全と健康を守る立場であり、退職勧奨はふさわしくない行為に当たります。
ただし、産業医と相談しながら職場環境の改善に努めることで退職勧奨の必要がなくなるケースや、産業医と面談するうちに従業員がみずから退職を決断するケースはあります。
【関連記事】産業医面談で休職者を退職勧奨できる?そのリスクとは
事業者であっても、従業員が産業医に話したすべての内容を把握することはできません。
産業医には守秘義務が課せられており、面談で知り得た情報を漏らしてはいけないため、事業者には共有されません。
どうしても面談の内容を把握したい場合は、当該従業員の許可を得る必要があります。
 産業医面談は、従業員本人の健康を守るために非常に有効な手段です。従業員に健康で長く働き続けてもらうためにも、企業は必要に応じて産業医面談の場を従業員に提供することが重要です。
産業医面談は、従業員本人の健康を守るために非常に有効な手段です。従業員に健康で長く働き続けてもらうためにも、企業は必要に応じて産業医面談の場を従業員に提供することが重要です。
また企業には、面談の結果を踏まえて職場環境の改善を行ったり、配置換えや業務内容の変更をしたりするなど、適切な措置をとることも求められます。
産業医面談を「ただ実施して終わり」とするのではなく、そこで得られた結果をしっかりと活かしていきましょう。
医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。
等、お悩みに合わせてご相談承ります。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
産業医面談の受診勧奨を促すWord形式の参考例文フォーマットです。 参考例文をコピー&ペーストしてそのままメール文として送れるものになっています。産業医面談が義務である従業員用、努力義務である従業員用の2種類をご用意していますので、用途に応じて使い分け可能です。 本フォーマットを活用いただくことにより、速やかに産業医面談の受診勧奨をすることができます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け