
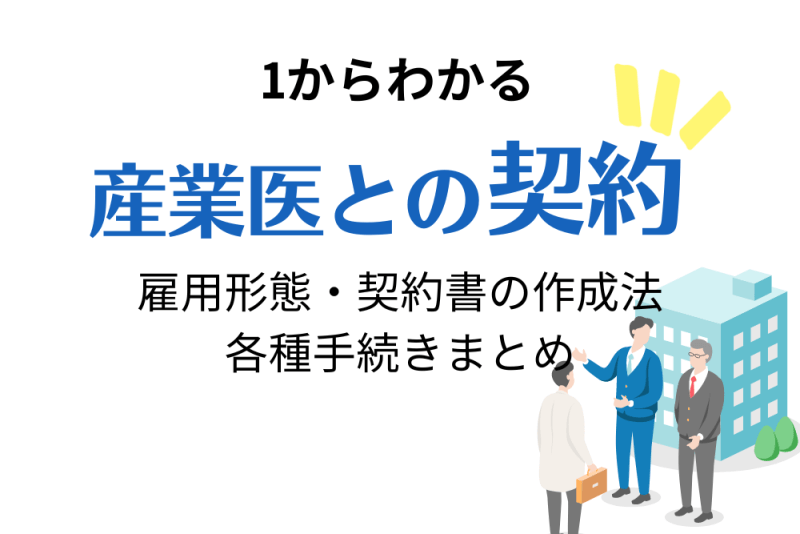
従業員の健康を守るために欠かせないのが産業医の選任です。
産業医の選任時には、「顧問料」「訪問日」「活動内容」等といった契約を結ぶ必要があります。
本記事では「そもそも産業医との契約ってどんなものなの?」
「契約手続きの流れや準備するものがよくわからない」という企業担当者の方に向けて、産業医の役割や契約形態、契約書の作成方法やひな形、そして契約時の注意点など、産業医との契約にまつわる疑問点をわかりやすく解説します。

産業医と契約・選任を行い、適切に稼働させることは企業(事業主)にとって法律で定められた義務です。
これは、労働安全衛生法(第13条)、労働安全衛生法施行令(第5条)で定められており、従業員50名以上の事業場で産業医を選任していない場合は罰則が科されます。
契約を結んだ産業医がいないことは、従業員の健康リスクや労基署からの指導のおそれがあるなど、社会的信頼の低下にもつながる恐れがあるので注意しましょう。
その産業医ですが、主な役割は労働者の健康管理と事業所の環境管理について、医学の専門家という立場から指導・助言する医師のことです。
また、産業医と契約する際は、その医師が専門資格を有していることが前提となります。
医師国家試験の合格者であることが大前提ですが、医師免許のほかに厚生労働大臣が定めた産業医研修の修了者、労働衛生コンサルタント試験の合格者、労働衛生の教授や助教授、厚生労働大臣が指定した医学部で産業医の養成課程と実習を履修した者で産業医の認定を持っている医師に限られます。
企業における産業医の具体的な業務内容については、関連記事をご確認ください。
【関連記事】産業医とは?企業での役割、病院の医師との違いを解説
【関連記事】従業員50人以上の事業場に求められる労働法令上の義務とは?
産業医には大きく分けて「嘱託産業医」と「専属産業医」の2種類があります。
従業員数が50名~999名の職場であれば嘱託産業医との契約で問題ありませんが、1,000名を超える職場(有害業務等を行う事業場では500名以上)では専属産業医と契約を結ぶ必要があります。
なお、従業員数が3,000名を超えるほど大きな事業場では、専属産業医を2名以上選任する必要がありますので、契約時に注意しましょう。
嘱託産業医と専属産業医の違いは契約方法や報酬に関連しており、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
嘱託産業医とは?専属産業医との違いや報酬相場、選び方のポイント
常勤の専属産業医とは? その定義や選任基準などを解説

産業医と企業が契約を結ぶ場合、主に以下4つのケースであることが多いです。
一つずつ紹介していきます。
雇用契約は、専属産業医の場合に多い契約方法です。
この場合、産業医は労働者として企業の労働に従事し、使用者(企業)が労働に対して報酬を支払います。
産業医の雇用契約は、通常のスタッフを雇用するときと同じ方法で企業が契約します。雇用契約を交わす際の名目は、契約社員や嘱託社員などが一般的です。
オフィス業務ではまだまだ兼業を認める企業は多くありませんが、医師の世界では、病院に勤務しながら別の医療機関でアルバイトする、施設をかけ持ちして兼業するといった働き方が一般的です。
雇用契約をする際は、こうした医師の文化への理解が必要です。
嘱託(非常勤)産業医の場合は、業務委託契約(顧問契約と呼ぶ場合もあります)を結ぶケースが多いでしょう。
業務委託契約とは、企業が産業医に特定の業務を依頼し、その対価を支払う契約です。このため産業医は契約内容を遵守しなければならない一方で、契約内容にない業務を拒否することも可能です。
トラブル防止のためには、業務の範囲や報酬など、諸条件を事前にしっかり取り決め、業務委託契約書に明記しておくことが大切です。業務委託契約には専門的な知識も必要なため、産業医の業務委託契約を初めて担当する人事担当者は、産業医紹介サービスの利用を検討するのも選択肢の一つになるでしょう。
企業が近隣の医療機関や健康診断を依頼している医療機関と業務委託契約を結ぶこともあります。
この場合、医療機関は自院で産業医資格を有する医師に依頼して、企業と結んだ業務内容を遂行してもらうことになります。
これまで説明してきた3つの契約のほか、1案件ごとに報酬を支払うスポット(単発)契約もあります。このスポット契約は、産業医紹介会社がサービス提供を行っているケースが多いです。
例えば、契約している産業医だけでは手が回らず突発的な面談依頼をする、従業員50人未満の事業場で産業医に専門的な業務を依頼しなければならない場合などに利用されます。
必要なタイミングで必要な依頼をできること、雇用契約や業務委託契約のように契約期間を設定する必要がないことが特徴です。
【関連記事】産業医との業務委託とは?契約形態の種類と特徴を詳しく解説!
【関連サービス】スポット産業医サービス「産業医エクスプレス」

産業医との契約は、一般的に以下のようなステップで進めます。
次に、契約書作成にあたり注意したいポイントについて解説していきます。
まずは産業医契約書のひな形を入手することから始めましょう
日本医師会や独立法人労働者健康安全機構などが産業医との契約書のひな形を公開しています。産業医との契約書作成をする際は、自社に合う産業医契約書のひな形を活用することで書類作成の工数削減にもなります。
・日本医師会「日本医師会認定産業医制度産業医契約書」
・独立行政法人労働者健康安全機構「中小企業のために産業医ができること」
産業医との契約書作成にあたって、以下の基本的な項目は必ず明記しましょう。
業務内容については、各種面談、職場巡視、衛生委員会での意見を述べるなど、産業医に求める具体的な業務内容や責務について記載します。
報酬、経費といったお金関係のことは後々トラブルになりやすいので細かく取り決めておきましょう。
事業場への訪問回数、月額あるいは1時間あたりの報酬額、報酬の支払日、移動にかかる交通費といった諸経費について、できる限り具体的に明記しましょう。また、場合によっては事業場への訪問時間が延長になることも考えられるので、契約時間を超過したときの対応についてもあらかじめ決めておくと安心です。
特に注意が必要なのは、個人情報の取り扱いです。個人情報については、本人の同意なく第三者へ提供することが禁じられています。具体的な個人情報としては、各種面談の内容、健康診断やストレスチェックの結果などが含まれます。医師が学会などで研究発表を行う際、他意なく従業員のデータを使用してしまう可能性もあります。個人情報保護法に則って、取扱いを明記しておきましょう。
産業医との契約期間もしっかり明記しましょう。一般的に、産業医は1年契約で自動更新になります。なかには契約社員あるいは嘱託社員として、1~5年の有期雇用にする企業もあります。顧問契約を結ぶケースもあるため、事前に契約期間を定めておきましょう。
出典:日本医師会「産業医契約書の手引き」
【関連記事】産業医の報酬相場と報酬以外にかかる費用 会計処理の注意点などを徹底解説
無事に産業医と契約が締結できたら、所轄の労働基準監督署に書類を提出します。提出書類は以下の通りです。
・産業医選任報告書
・医師免許のコピー
・産業医であることの証明またはコピー
産業医の選任報告書は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。産業医である証明とは、厚生労働大臣が定めた産業医研修の修了者、労働衛生コンサルタント試験の合格者、労働衛生の教授や助教授、厚生労働大臣が指定した医学部で産業医の養成課程と実習を履修した者の証明です。選任報告の手続きについては、以下の記事をご参考ください。
【関連記事】産業医選任報告(選任届)の書き方と記入例

企業が産業医と契約する際には、「医師の働き方」、「産業医の選任義務が発生してから選任するまでの期間」を意識することが大切です。次に、詳しく解説していきます。
産業医と契約する際に留意したいのは、医師の世界と一般企業の常識にはギャップがあることです。
前述した通り、医師は正規の勤務先以外でのアルバイトや兼業が当たり前に行われています。診療科にもよりますが、フレキシブルな勤務時間をとるなど、ホワイトカラーとは異なる働き方も珍しくありません。患者さんの命や健康を守る専門職としてのプライドを持っている方も多いので、契約の際には、医師が希望する働き方や業務内容なども事前に確認したうえで選任するのが望ましいでしょう。
産業医を変更する場合は、事前に後任の産業医を探しておきましょう。産業医の選任義務が発生してから14日以内に選任しなければならないためです。時間がないからと前任の産業医と同様の条件で契約すれば、後々トラブルに発展する可能性もあります。契約条件や契約書の作成など、なるべく余裕をもって準備を進めることをおすすめします。
産業医と契約を交わしたものの、産業医が契約内容の職務を遂行しないことも稀にあります。このような、いわゆる「名義貸し産業医」と称される状態は労働安全衛生法違反にあたり、企業に罰則が科される場合があります。
人事労務担当者は、産業医が契約書に記載した業務内容を行っているか、職務を果たしているかをしっかり確認しましょう。
また、当ブログを運営している会社(エムスリーキャリア)では、しっかり法令対応をクリアする産業医の紹介・選任サービスをご提供しています。
はじめての産業医選任でも、産業医の交代でも対応可能で、料金も業界の最安値水準です。
以下の「見積もりフォーム」に事業場の所在地を入力することでかんたんにお調べすることが可能ですので、価格調査や相見積もりの取得にぜひお試しください。
\ 所要時間1分 /見積もりを出してみる
【関連記事】産業医の「名義貸し」が企業にもたらす3つのリスクとは?
産業医との契約は、ホワイトカラーの社員の雇用と異なる点が少なくありません。一般企業の人事担当者にとっては、「よくわからない」と感じる点もあるのではないでしょうか。スムーズな契約締結のために、地域の医師会、産業医紹介会社に相談するのも選択肢の一つです。
従業員の健康を守り、生産性の高い職場をつくるためには、より自社に合った産業医を確保することが大切です。もしも産業医との契約に際して不安なことや疑問点があれば、ぜひエムスリーキャリアまでお気軽にお問い合わせください。
医師会員数No.1!全国の医師の約9割が登録する豊富な医師会員基盤から、貴社に最適な医師をご紹介いたします。
等、お悩みに合わせてご相談承ります。
これから産業医を選任しようとお考えの企業担当者様向けに、「そもそもいつから選任しなければいけないのか」「選任後には何が必要なのか」「産業医を選ぶ時のポイント」「FAQ」などを丁寧に解説! エムスリーキャリアの産業医顧問サービスについても併せて紹介しておりますので、ぜひご活用ください!
主な産業医紹介会社のサービス内容、料金等を比較表にまとめました。相見積もりや稟議にお使いいただけます。 主な比較項目 登録医師/産業医の人数 料金 主な対応エリア オンライン対応の有無 紹介会社選びのご相談はこちら 費用等について無料相談も受け付けております。カレンダーから日程をご予約ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け