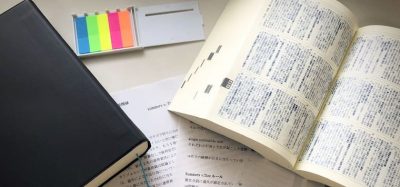
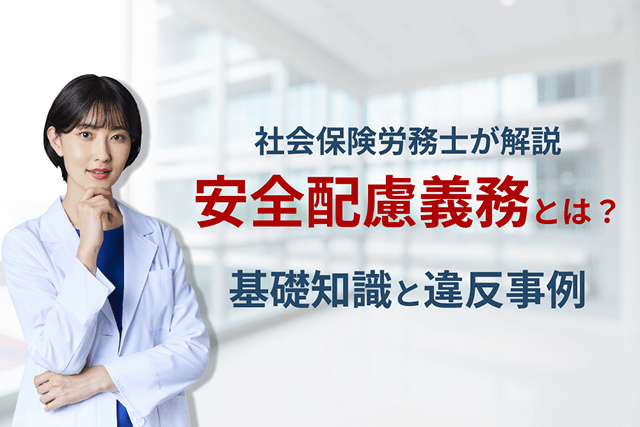
安全配慮義務とは、従業員が身体的・精神的に健康かつ安全に働くために企業が配慮すべき義務です。違反すると民法・労働安全衛生法によって罰則を科せられるケースもあります。
しかし、「従業員への安全衛生のために、具体的に何をしたらいいのか分からない」などの疑問をもつ人事労務担当者の方もいるでしょう。
本記事では、安全配慮義務違反に該当する基準や、違反しないために講じるべき対策について社会保険労務士が解説します。働きやすい環境を作る取り組みを考える上での参考にしてください。
目次
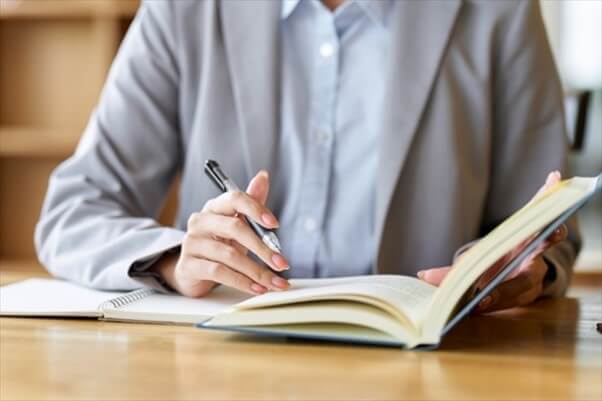 安全配慮義務とは、従業員の身体・精神両面において健康かつ安全に働くために企業が心がけるべき義務のことです。
安全配慮義務とは、従業員の身体・精神両面において健康かつ安全に働くために企業が心がけるべき義務のことです。
安全配慮義務は民法における「権利の行使および義務の履行」から発展し、労働契約法・労働安全衛生法に明記されています。企業はこれらの法律を遵守し、次のような措置を取らなくてはなりません。
【参考】
e-Gov法令検索「民法」
e-Gov法令検索「労働契約法」
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
 安全衛生義務の対象者は、主に以下4つのとおりです。
安全衛生義務の対象者は、主に以下4つのとおりです。
自社の従業員だけでなく、会社のために働いてもらっている下請け業の労働者や派遣社員などの安全も配慮しなければなりません。
会社とは直接の労働契約はありませんが、会社の指揮命令や管理監督のもとで働いているので、安全配慮義務を負うべきと考えられています。
 安全配慮義務違反に該当するかどうかの判断基準は、次の3つです。
安全配慮義務違反に該当するかどうかの判断基準は、次の3つです。
それぞれ解説していきますので、安全配慮義務が守られているかチェックする際の参考にしてください。
法律に明記されている、企業が果たすべき義務を果たしていない場合には、違反と見なされる可能性が高いでしょう。
安全配慮義務は、具体的には「健康配慮義務」と「職場環境配慮義務」に取り組む必要があります。
| 義務の種類 | 明記されている法律 | 義務の内容 |
| 健康配慮義務 | 労働契約法第5条 | 従業員の健康を守るために健康診断や労働時間管理を実施する義務 |
| 職場環境配慮義務 | 労働安全衛生法第3条 | いじめ・ハラスメント対策を実施して働きやすい職場を整備する義務 |
上記の措置を怠ったために従業員の健康や安全が脅かされた場合、安全配慮義務違反とみなされます。人事・労務担当者は安全配慮義務について正しく理解し、適切な対策を講じましょう。
【参考】
e-Gov法令検索「労働契約法」
e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
企業の安全配慮義務違反の内容と、従業員のケガや病気に因果関係があるかどうかも判断基準の一つです。
因果関係が認められるのは次のようなケースです。
安全配慮義務違反は身体的なケガだけでなく、従業員が精神的な病気になった場合も該当します。
安全配慮義務違反を訴えられた際には、企業側の措置を怠ったことが原因なのか、従業員に過失はないかを確認しましょう。
従業員が心身の健康を害したり、安全が脅かされたりすることを企業側が予測できていたかも判断基準の一つに挙げられます。
予見可能性があったと認められるのは、たとえば次のようなケースです。
予見可能性がありながらも対策を実施していなかった・不十分だった場合、安全配慮義務違反とみなされる可能性が高いでしょう。
 具体的な事例をもとに、安全配慮義務違反に該当する判断基準について確認しましょう。
具体的な事例をもとに、安全配慮義務違反に該当する判断基準について確認しましょう。
1991年5月、慢性的な長時間労働に従事していた新入社員がうつ病に罹患し、その後自殺した事例です。
従業員は上司に対しても「自信がない、眠れない」と訴えており、異常行動も見られていました。
判決においては、以下の点において企業側の安全配慮義務違反(とくに健康配慮義務違反)とみなされました。
・ 企業は長時間労働があったにもかかわらず、業務負担を軽減させようとしなかった
・ 長時間労働とうつ病罹患、その後の自殺には関連性がある
・ 上司は従業員の長時間労働・健康状態の悪化に気づいており、予見可能性があった
なお二審では、従業員の性格(真面目、完璧主義、責任感の強さ)がうつ病と親和性が強いとされ、賠償額が減額されています。
しかし三審で、過労自殺の事案一般に、本人の性格は一定範囲を外れない限り過失にすべきではないとされ減額は破棄されました。
最終的には、企業側が約1億6,800万円を支払い和解が成立しています。
この事例では、従業員の過労自殺と業務の間の因果関係が民事訴訟ではじめて認められました。従業員を監督する立場にある人は、長時間労働や過重な負担により従業員が健康を損なっていないかを、常に気にかける必要があります。
今回の事例のように、優秀で完璧主義、責任感の強い従業員ほど自分で抱え込んでしまう可能性が高いため注意が必要です。
【参考】厚生労働省「うつ病による過労自殺について使用者の安全配慮義務違反を認めるリーディングケースとなった裁判事例(電通事件)」
職場でのいじめが原因で職員が自殺し、安全配慮義務違反が問われた事例です。
川崎市水道局に勤務する男性職員は、同課の課長や係長などから執拗な嫌がらせを受けており、精神的に追い詰められて自殺にいたりました。
男性職員が配属する課の責任者は、いじめを把握していたにもかかわらず、必要な措置を講じていなかったとのことです。
裁判では、上司の安全配慮義務違反が認定され、遺族の損害賠償請求が認められました。
この事件は、職場におけるいじめ防止と安全配慮義務の重要性を社会に強く訴えた事例の一つです。
【参考】厚生労働省「上司がいじめを認識しつつ対応を取らなかったため自殺したとして、損害賠償請求が認められた事案」 ―川崎市水道局事件」
 安全配慮義務に違反した場合、民法と労働安全衛生法にもとづいて罰則が科される可能性があります。
安全配慮義務に違反した場合、民法と労働安全衛生法にもとづいて罰則が科される可能性があります。
民法においては、次の3項目にもとづいて損害賠償請求が発生する可能性があります。
(参考:e-Gov法令検索「民法」)
労働安全衛生法においても、該当する規定に違反すると50万円~300万円の罰金が生じる可能性があります。
損害賠償が訴訟に発展すればニュースに取り上げられ、企業イメージを大幅に損ねる結果になりかねません。法律にもとづいて適切に労働環境を整え、従業員の健康を守るよう配慮しましょう。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
 ここでは、企業が安全配慮義務を果たすために取り組むべきことを解説します。
ここでは、企業が安全配慮義務を果たすために取り組むべきことを解説します。
企業には労災(労働災害)を防止するための責任が課せられており、事業場の規模や業種に応じて安全管理者や衛生管理者などの選任が義務付けられています。
管理者を中心に以下のような対策を実施し、安全を確保できるように配慮する必要があります。
・機械に巻き込まれるのを防ぐために柵を設置
・滑りやすい場所に滑り止め効果の高い床材を設置
・作業場所や業務工程に潜む危険因子の洗い出し、対策
・機械設備や作業環境の定期的な点検、整備
・ヘルメットや安全靴など、保護具の着用の徹底
事故の原因となる要素を排除するよう努めましょう。
従業員の心身の健康に配慮するためには、産業医を選任し健康相談を実施することも重要です。
産業医とは、従業員が健康に働けるような職場を実現するための、専門的な知識を備えた医師です。常時50人以上の従業員を使用する事業場では、産業医を選任する義務が発生します。
産業医による健康相談は、以下のような場合に実施します。
健康相談は従業員の健康を守り、高いパフォーマンスで働いてもらうために有効な手段です。産業医への相談のメリットも含めて社内に周知し、利用を呼びかけましょう。
【参考】厚生労働省「中小企業事業者の為に産業医ができること」
従業員に安全や健康に関する知識をもってもらい、労災を防止するためにも企業は安全衛生教育を実施する必要があります。
企業が実施を義務付けられている安全衛生教育は、次の3つです。
上記の他にも、安全衛生管理者などの能力向上教育、従業員の健康意識を向上させるための教育も努力義務としています。
また、近年は労災による死傷者数は増加傾向にあり、2023年における休業4日以上の死傷者数は約36,000人です。前年から2.3%(約3,000人)増加しており、依然として労災は深刻な課題です。
労災の原因は、転倒や墜落・転落などが多い傾向にあります。このような状況を踏まえ、リスクを具体的に理解させる教育や実務に即した訓練などを行い、従業員の安全意識を向上させることが大切です。
【参考】
厚生労働省「職場のあんぜんサイト:安全衛生教育」
厚生労働省「令和5年労働災害発生状況」
労働安全衛生法により、事業者は従業員に対し健康診断を実施しなければなりません。
定期健康診断は、年に1回の実施が義務付けられています。また、以下も実施しなければなりません。
・雇い入れ時の健康診断
・特定業務従事者の健康診断
特定業務従事者の健康診断とは、深夜業や有害物質を取り扱う業務など、労働安全規則に定められている特定の業務に従事する従業員に対して実施する健康診断です。
特定業務従事者には、配置換え時や6ヶ月ごとに健康診断を行わなければなりません。
健康診断の結果、従業員に異常の所見があれば産業医の意見も参考に、就業場所の変更や作業負荷の軽減、作業環境の見直しなどの措置が必要です。
健康診断の種類や有所見者への対応などについては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
【関連記事】
「健康診断は企業の義務! 会社で実施される健康診断の種類、対象者などを解説」
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう」
ストレスチェックは、50人以上の従業員を使用する事業場で義務となっており、年に1回実施しなくてはなりません。ストレスチェックでは、質問票を用いて次の3項目をチェックします。
従業員は自分でも気づかないうちにストレスを溜め込んでいることもあります。従業員がストレスを自覚したり、企業がうつ病などに発展する前に対策を取ったりするために、ストレスチェックは有効な手段です。
【関連記事】
ストレスチェックで高ストレス者を選定する際の方法や注意点
従業員の健康を守るために事業者は、従業員の勤務時間を正確に記録し、過剰な時間外労働を抑制しなければなりません。勤怠管理システムなどを使用し、従業員の月の時間外労働時間・総労働時間を把握する必要があります。
業務の効率化が図れているか、計画性のない時間外労働が発生していないかなどを確認し労働時間を管理しましょう。
なお、時間外・休日労働が月80時間を超えている従業員には、当該従業員から面接の申し出があった場合、産業医による面接指導を行わなければなりません。
面接指導後、事業者は産業医から意見を聴取し、当該従業員の就業場所や業務内容の変更などの就業措置を講じる必要があります。
【関連記事】長時間労働者への産業医面談が必要になる基準とは?面談を実施する流れも解説
ハラスメント対策は、働きやすい良好な職場環境を維持する「職場環境配慮義務」に該当します。2022年4月からはパワーハラスメント防止措置が中小企業を含めた全企業の義務となり、いっそうの取り組みが必要です。
職場でのハラスメントを防止するために企業が取り組むべき具体的な措置は、以下のとおりです。
以上のような義務を十分に果たさなければ、安全配慮義務が厳しく問われることになります。企業としてハラスメントに対応するためのルールを明確にし、それに沿った対応を心がけましょう。
【参考】厚生労働省「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」
【関連記事】
パワハラ防止法は中小企業も対象!罰則や取り組むべき対策を解説
職場におけるハラスメントとは?種類や発生する原因、対策を解説
 安全配慮義務は、海外勤務にあたる従業員も対象になります。国内で働く従業員とは労働環境が大きく違うため、特別な対応が必要です。
安全配慮義務は、海外勤務にあたる従業員も対象になります。国内で働く従業員とは労働環境が大きく違うため、特別な対応が必要です。
たとえば、治安が悪く情勢が不安定な地域に赴任する場合、犯罪やテロなどが発生することが予見できます。現地で安全に移動するための車やボディーガードの手配が必要になるでしょう。
熱帯地域に向かう場合には現地の感染症にかかるおそれもあるため、予防接種や現地の医療サポートが必要です。また、慣れない地での業務になるため、勤務期間を心身ともに健康に過ごすための研修・メンタルサポートも欠かせません。
 自然災害においても、企業は従業員への安全配慮義務を持っています。
自然災害においても、企業は従業員への安全配慮義務を持っています。
裁判例などでは従業員の生命・身体を守るため次のような義務があるとされています(以下は一例です)。「想定外」という言い訳は許されないと考えておきましょう。
| 1.行動指針の策定
自然災害時に労働者の生命身体を守るための行動指針を策定しておかなければならない。 2.防災マニュアル等の策定周知・避難訓練などの実施 3.現場責任者が被災した場合の対応を行動計画で明確にしておく。 4.停電や通信途絶などを想定した代替策、予備対策等の策定・準備 5.職員の安否確認の方法の明確化と徹底 6.過去の被災事例などを元にした検討の徹底 学校に求められる安全配慮義務
学校に求められる安全配慮義務とは、生徒が学校内外の教育活動において安全に過ごせる環境を整備するための責任を指します。 たとえば、校舎や遊具の老朽化による事故を防ぐための点検や修繕、災害時に備えた避難訓練の実施などです。 また、遠足や修学旅行などの校外活動においては、事前のリスク評価や引率教職員による適切な危機管理体制の整備などが欠かせません。 安全配慮義務を怠ると学校側が法的責任を問われる場合があり、安全管理を徹底する必要があります。 www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/fs/8/5/1/7/0/6/3/_/2-1%20事故防止のた...
|
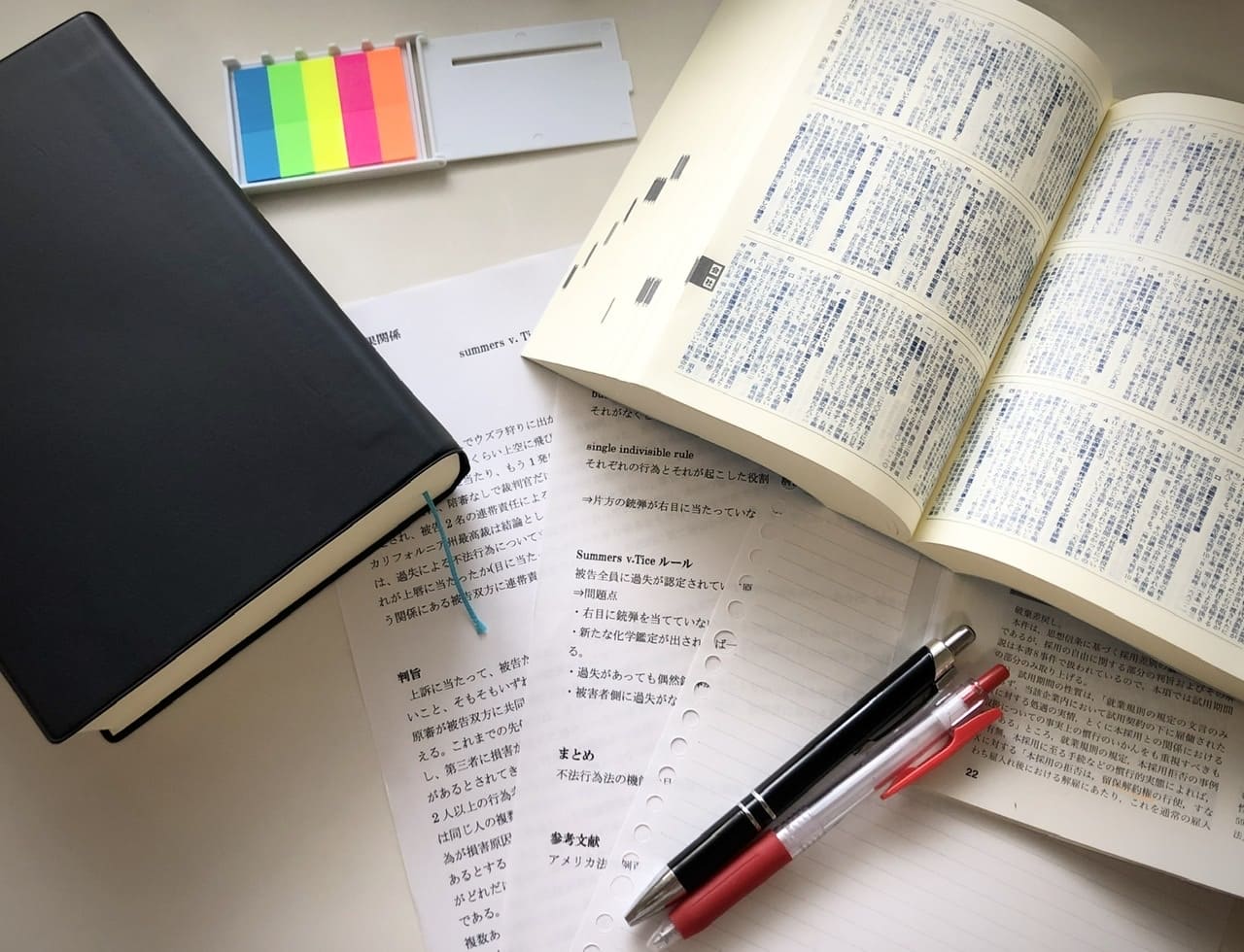 従業員や下請労働者、派遣労働者など関係のある人から安全配慮義務違反を訴えられた場合、次のような手順で対応することになります。
従業員や下請労働者、派遣労働者など関係のある人から安全配慮義務違反を訴えられた場合、次のような手順で対応することになります。
ただし、訴訟に発展すると時間的にも金銭的にも大きなコストがかかります。従業員とコミュニケーションをとり、訴訟に発展させずに問題解決を図るのが望ましいでしょう。
まずは従業員が訴える安全配慮義務違反の事実について十分な事実確認を行います。
長時間労働に対する訴えの場合、勤務実績などをチェックするだけでなく、従業員の同僚などに聞き込みを行うことも有効です。
また、ハラスメントが行われていた際には、行為者である従業員への聞き込みは慎重に行いましょう。
労災保険に対応する場合、事業者は従業員が認定請求をするために協力をしなくてはなりません。実際には従業員に代わって労災認定のための手続きを行うことになります。
労災保険の給付の認定を得られれば、その限りで会社は責任を免れます。
ただし、労災保険に認定された場合でも、休業1~3日目の休業補償分は給付されず、企業側が支払う必要があるので注意しましょう。
【関連記事】
【社労士監修】労災とは?人事労務担当者が知っておくべき基礎知識と対応方法
労災認定基準をケース別に解説!直近の改正や認定されない例も紹介
賠償請求額の合意が得られない、安全配慮義務違反の見解が一致しなかった場合には、従業員側から訴訟が提起されることもあります。
法廷では会社側の主張を通し、適正な賠償額で解決することが重要です。訴訟に発展する可能性があったら、早めに労働争議に詳しい弁護士に相談しましょう。
 安全配慮義務違反を判断するポイントは「果たすべき義務を果たしているか」「ケガや病気に因果関係があるか」「予見可能性があるか」の3つです。
安全配慮義務違反を判断するポイントは「果たすべき義務を果たしているか」「ケガや病気に因果関係があるか」「予見可能性があるか」の3つです。
安全配慮義務を果たすには、「健康配慮義務」と「職場環境配慮義務」の2つに取り組む必要があります。違反すると罰則が科される可能性があるので、正しく理解して対策を実施しましょう。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け