

職場における代表的なハラスメントとして、セクハラ、マタハラ、パワハラが挙げられますが、この他にもさまざまなハラスメントが存在します。
ハラスメントが発生している労働環境下では、従業員のメンタルヘルス不調や生産性低下が懸念されるだけでなく、休職や退職をまねきかねません。
本記事では、職場におけるハラスメント、その対策として企業に求められる義務などについて解説します。
目次
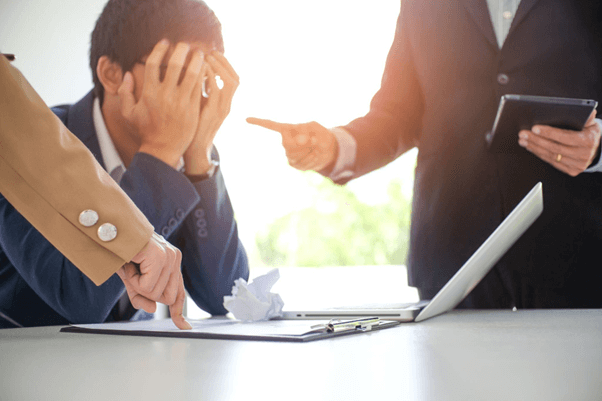 ハラスメントとは、相手の意に反する行為によって相手を不快な気分にさせたり、人間としての尊厳を著しく傷つけたりすることです。いじめ、嫌がらせと同等の行為に値します。
ハラスメントとは、相手の意に反する行為によって相手を不快な気分にさせたり、人間としての尊厳を著しく傷つけたりすることです。いじめ、嫌がらせと同等の行為に値します。
たとえ相手を傷つける意図がなかったとしても、相手が不快な思いをした時点でハラスメントは成立します。
【参考】厚生労働省「NOハラスメント あかるい職場応援団」
【関連記事】
職場におけるパワハラの定義とは?企業が知っておくべきポイント
アンガーマネジメントとは?職場に取り入れるメリットを解説
 ハラスメントを防止するには、どのような種類のハラスメントがあるのか知っておくことが大切です。
ハラスメントを防止するには、どのような種類のハラスメントがあるのか知っておくことが大切です。
セクシャルハラスメントとは、他者を不快にさせる性的言動全般のことです。職場にて労働者の意に反する性的な言動によって職場環境を著しく害する、労働条件について不利益を被る行為全般と定義されています。
具体的には、異性の身体に意味もなく触る、新婚の部下に対してしつこく家庭内の性生活について尋ねるなどの行動が該当します。
マタニティハラスメントとは、女性従業員が妊娠、出産したことで同僚や上司から仕事を奪われるなどの嫌がらせを受け、就業環境を害される行為を指します。
また、育児休業を申請した男性従業員に対するパタニティハラスメントも存在します。
【関連記事】マタハラとは?企業が取るべき対策を具体的事例・発言をもとに解説
パワーハラスメントとは、上司と部下のような地位による優位性を利用して、職場で相手に精神的・身体的苦痛を与える行為です。
パワハラを細分化すると、暴力によって相手を傷つける身体的攻撃型や、言葉の暴力による精神的攻撃型などの種類が存在します。
具体的には、他の従業員の前で執拗に怒られる、ある特定の従業員だけミーティングに呼ばないなどの行動がパワハラに該当します。
【関連記事】職場におけるパワハラの定義とは?企業が知っておくべきポイント
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先から受ける嫌がらせ行為を指します。
具体的には、些細なミスで何度も謝罪を要求する、土下座や解雇を要求する、大声で怒鳴ったり罵声を浴びせたりするなどの行為のことです。
セクハラ、マタハラ、パワハラなどが自社の職場内で発生しやすいハラスメントであるのに対し、カスハラは社外から自社従業員に対し行われます。
【関連記事】カスハラが労災認定基準に追加!事例や企業が取り組むべき対応を解説
アルコールハラスメントとは、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害のことです。
具体的には、飲酒の強要やお酒に酔った状態での迷惑行為を指します。
【関連記事】これってアルハラ?職場の飲み会で注意すべきこと
モラルハラスメントとは、倫理・道徳に反した嫌がらせのことです。パワハラとは異なり職務上の地位は関係なく、同僚間や先輩・後輩間、部下から上司に対する精神的な嫌がらせやいじめなども該当します。
このため、パワハラ以上に被害者が発生しやすいと考えられます。
【関連記事】職場のモラハラきちんと対応できてますか?人事担当者が知っておくべきポイント
SOGIとはSexual Orientation and Gender Identityの略で、日本語に訳すと「性的指向および、性自認」です。SOGI(ソジ)ハラスメントとは、性的指向・性自認に関する言動・行動で人を傷つける行為を指します。
具体的には、SOGIを理由とした不当な異動や解雇、差別的な言動や嘲笑、呼称などが当てはまります。
【関連記事】SOGIハラスメントとは?職場で求められる対応、取り組み事例について解説
リモートハラスメントとは、リモートワークで起こるハラスメントです。主に以下のような行為がリモハラに該当します。
「テレワークハラスメント(テレハラ)」や「オンラインセクハラ・パワハラ」などと呼ばれることもあります。
【関連記事】リモハラ(リモートハラスメント)とは?企業が知っておくべき対処法や具体例
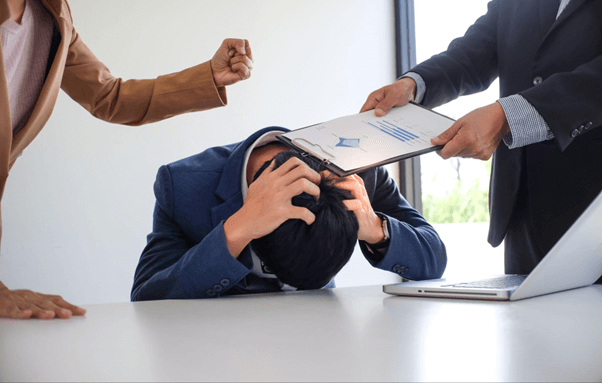 厚生労働省が公表している2023年の調査資料によると、過去3年間に相談のあったハラスメントの割合は以下のとおりです。
厚生労働省が公表している2023年の調査資料によると、過去3年間に相談のあったハラスメントの割合は以下のとおりです。
| 顧客からの迷惑行為(カスハラ) | 86.8% |
| セクハラ | 80.9% |
| パワハラ | 73.0% |
| 介護休業等ハラスメント | 55.5% |
| 妊娠・出産・育児休業等ハラスメント | 50.1% |
セクハラ・パワハラ・マタハラは職場の三大ハラスメントとも呼ばれますが、上記の調査結果から社外からのハラスメント(カスハラ)が非常に多いことが分かりました。
【参考】厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査」
 ハラスメントはさまざまな要因により発生しますが、以下のようなことがハラスメントの原因となり得ます。
ハラスメントはさまざまな要因により発生しますが、以下のようなことがハラスメントの原因となり得ます。
それぞれの内容について解説します。
パワハラは、従業員同士のコミュニケーションが希薄化していることが原因の一つと考えられています。
コミュニケーションが不足すると従業員が自分の意見を発信しづらくなったり、相手を褒めて認めあったりができなくなるためです。
パワハラを防ぐには、日頃からコミュニケーションを取り、職位に関係なく同じ職場で働く仲間だという意識をもつことが大切です。
【参考】厚生労働省「職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!」
性別による役割分担の意識は、セクシャルハラスメントの発生原因につながりやすいと考えられています。
性別による役割分担の意識とは、たとえば「男なら◯◯すべき」「女のくせに」などのように、個人的な性別の価値観を他者に押しつける考えです。
他にも「料理上手だね。いい奥さんになるよ」「早く結婚したほうがいい」なども当てはまります。本人が褒めているつもりや応援しているつもりでも、セクハラに該当するため注意が必要です。
ハラスメントに関する知識が不足していると、ハラスメントが発生する原因となり得ます。知識不足がハラスメントを招く原因として、以下のような状況が挙げられます。
ハラスメントを防止するには、役職や仕事上の立場を問わず、すべての従業員がハラスメントに関する知識を身につけることが大切です。
上司や管理者などのマネジメント能力が不足していることで、ハラスメントにつながる可能性があります。たとえば以下のような場合です。
上司や管理者の采配力や教育力が不足していると、従業員が委縮したり不要な負担を感じたりしてしまうため、ハラスメントの発生が懸念されます。
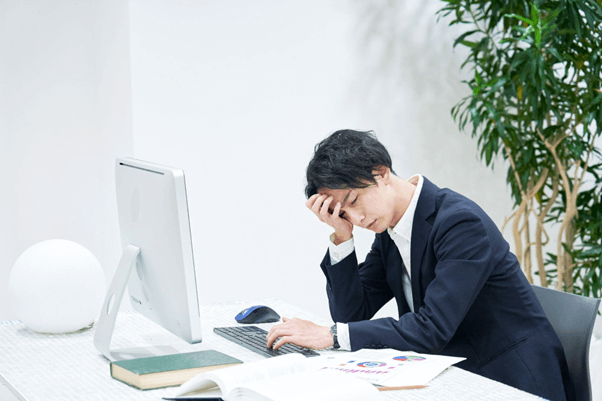 ハラスメント対策を怠るリスクとして、以下が挙げられます。
ハラスメント対策を怠るリスクとして、以下が挙げられます。
それぞれの内容について解説します。
ハラスメントに対し適切な防止措置や対処をせず放置した場合、法的責任を問われる可能性があります。労働契約法にもとづき、事業者には従業員が働きやすいよう安全な職場環境を整える安全配慮義務があるからです。
そのため、ハラスメントを確認したら早急な対応が必要です。
【参考】e-GOV法令検索「労働契約法第5条」
ハラスメントが発生し適切な対処をしないと、メンタルヘルスの不調に陥り当該従業員が離職する可能性があります。
また、適切な措置を講じない企業に対し、強い不信感を抱き他の従業員も辞めてしまうことも考えられるでしょう。
さらに、企業の口コミサイトやSNS上で評価を下げる恐れがあり、求職者を遠ざけてしまうことも懸念されます。
職場にハラスメントが横行すると職場環境が悪化し、生産性が低下する可能性があります。ハラスメントにより上司に不信感が募り、従業員の意欲が低下する恐れがあるためです。
また、職場内の雰囲気が悪化してコミュニケーションが取りづらくなると、連携不足によるミスが多発しやすくなります。
 パワハラを防止対策していなかったり、パワハラを放置し適切に対処しなかったりした場合は、裁判に発展し損害賠償責任を問われる恐れがあります。
パワハラを防止対策していなかったり、パワハラを放置し適切に対処しなかったりした場合は、裁判に発展し損害賠償責任を問われる恐れがあります。
ここでは、職場でハラスメントが発生し裁判に発展した事例を紹介します。
本事例は、従業員が身体的・精神的なハラスメントを加えたことにより、企業が法的責任を問われた事例です。被害者である従業員3名が、上司にパワハラを受けたとして損害賠償を求めました。
行われたハラスメントは以下のとおりです。
上記のハラスメントによって被害者のうち一人は抑うつ状態に陥り、治療費および休業損害を請求しています。上司の行為は違法行為と認められました。
また企業に対しても、被害者からの相談に対し真摯に取り合わなかったとして慰謝料の支払いが命じられました。
【参考】厚生労働省「日本ファンド(パワハラ)事件」
本事例は、忘年会で上司がセクハラ行為をした事例です。被害者7名が治療費、営業成績低下に伴う逸失利益、精神的苦痛に対する慰謝料を加害者および企業へ求めました。
本事例で違法と認められた点は以下のとおりです。
本事例からは、宴会のような無礼講の席であったとしても、度を超えた行為はセクハラに該当することが分かります。
セクハラを防ぐには、場を盛り上げるための悪ふざけと思わず、自分の行為がハラスメントに当てはまらないか意識して行動することが大切です。
【参考】厚生労働省「広島セクハラ(生命保険会社)事件」
 ハラスメントを深く理解するためには、ハラスメントとの関連がある以下の法律もあわせて知っておくとよいでしょう。
ハラスメントを深く理解するためには、ハラスメントとの関連がある以下の法律もあわせて知っておくとよいでしょう。
法律で禁止されているハラスメントに該当する行為や、義務化されているハラスメント対策の内容を理解し、ハラスメントを発生させないようにしましょう。
男女雇用機会均等法は、採用や昇進、配置などを、性別を理由に差別することを禁止する法律です。具体的には、以下のような行為を禁止しています。
ただし、現状の男女間に発生している格差を是正するために、女性を優遇することは特例として認められています。
【参考】厚生労働省「男女雇用機会均等法の概要」
育児・介護休業法は、従業員が就労と子育て・介護を両立できるよう支援する法律です。男女で条件が異なるものの、女性だけでなく男性にかかわる育児休業の定義も示されています。
育児・介護休業法では、育児や介護のための休業申し出・取得を理由として、企業が当該従業員に対し不利益な扱いをすることを禁止しています。
事業者は当該従業員の就業環境が害されることがないよう、措置を講じなければなりません。
【参考】厚生労働省「育児・介護休業法の概要」
労働施策総合推進法とは、労働者の雇用の安定や、やりがいをもって働ける社会をつくることを目的とした法律です。同法には、企業に対するパワハラ対策の義務規定が設けられています。
従来はパワハラに適用できる法律がありませんでした。そのため、ハラスメントのない社会の実現に向けて、労働施策総合推進法の一部が改正され、企業にパワハラ対策が義務付けられました。
【参考】厚生労働省「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について」
【関連記事】パワハラ防止法は中小企業も対象!罰則や取り組むべき対策を解説
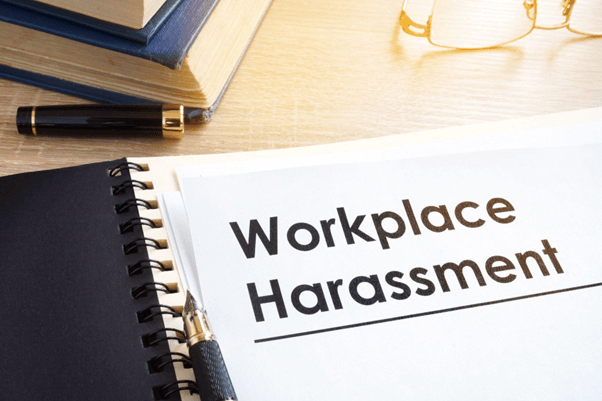 労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正により、以下のパワハラ対策が義務化されました。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)の改正により、以下のパワハラ対策が義務化されました。
(出典:厚生労働省「労働施策総合推進法の改正(パワハラ防止対策義務化)について」)
なお、労働施策総合推進法には、セクハラ対策に関する規定もあります。現行のセクハラ対策の内容とあわせて、上記の義務化された内容について解説します。
労働施策総合推進法にもとづき、パワハラ対策における企業の方針を明確化し、社内に周知・啓発をしなくてはなりません。具体的には、パワハラはあってはならないことであると明言するよう義務付けられています。
また、就業規則などに明文化し、パワハラをした者に対する処分を定めて周知しなくてはなりません。社内全体にパワハラに対する企業の方針を広めることで、パワハラを未然に防ぐことにつながります。
企業には、相談窓口を設置し従業員からパワハラに関する相談を受けられるようにする体制の整備が求められます。
社内で起きるパワハラに関して、社内窓口では相談しづらい従業員もいると考えられるため、社外の相談窓口も活用できるようにするのも有効です。
また、ハラスメント 相談専門の部署を設置したり、相談に関する対応方法をマニュアル化したりしておくと迅速に適切な対応ができます。
【関連記事】産業医はハラスメント防止にも対応できる?相談窓口における役割や注意点
パワハラの事実確認後、被害者および行為者への対応を速やかに行う必要があります。その際、被害者への配慮が大切です。
たとえば、事実確認時に行為者と被害者を同席させると被害者が委縮してしまう可能性があるため、別々に行うようにするなどを検討しましょう。
また、パワハラは該当事例を解決させて終わりではなく、再発防止策を講じることも重要です。
先述の1から3までを行ったうえで、必要な措置があれば対応しましょう。たとえば以下のような措置が挙げられます。
上記を事前に周知しておけば、パワハラを受けた被害者が相談しやすくなります。また、事実確認時にパワハラを目撃した従業員が協力者として名乗り出やすくなるでしょう。
 ハラスメントをなくすために、企業には以下のような防止策の実施が求められます。
ハラスメントをなくすために、企業には以下のような防止策の実施が求められます。
防止策を実施し、従業員が安心して働ける職場づくりに努めましょう。
ハラスメントをなくすには、上下関係を気にせず意見を言い合える、コミュニケーションが活発な職場をつくることが大切です。なぜなら、ハラスメントは立場が上の者が加害者となることが多いためです。
コミュニケーションが不足している職場環境だと意見が言えないだけでなく、ハラスメントの相談もしにくくなります。従業員一人ひとりが日頃からコミュニケーションをとり、気軽に相談できるようにしておきましょう。
また、閉鎖的なハラスメントを防ぐためにも、同じ事務所や部署内だけでなく自社全体でコミュニケーションをとれるようにするとよいでしょう。
ハラスメントを防ぐためには、管理者向けのマネジメント研修の実施が欠かせません。マネジメント能力不足により、部下に不要なプレッシャーを与えてしまっている場合もあるからです。
マネジメント研修では、よい職場づくりを実現するためのコミュニケーション能力や采配力を高められます。
部下との距離感や接し方、部下の適性に合わせた仕事の振り方などを学び、部下が上司に萎縮せず個人の能力を発揮できるよう努めることが大切です。
ハラスメントを発生させないようにするためには、全従業員に対して研修を実施し、企業全体でハラスメントに関する正しい知識をもつことが重要です。
たとえば、ハラスメントを行う人の中には「相手のために言っていただけ」など自身の行いがハラスメントに該当すると自覚がない場合もあります。
そのため、どのような行為がハラスメントに該当するかをハラスメント研修で示すことが大切です。
産休・育休など制度について社内報知を徹底することは、ハラスメント防止につながります。従業員一人ひとりが制度について理解を深めることで、以下のような思考に陥ってしまうリスクが低減するからです。
ハラスメントを防ぐために、産休・育休などの制度は誰もが取得してよいものであると認識させ、制度を利用しやすい社内風土をつくりましょう。
 ハラスメントは従業員の健康を損なうだけでなく、離職率増加や生産性低下などのリスクを生じさせます。
ハラスメントは従業員の健康を損なうだけでなく、離職率増加や生産性低下などのリスクを生じさせます。
ハラスメントを防止するためには、ハラスメント研修を実施したりコミュニケーションが活発な職場環境を整備したりするなどの対策が欠かせません。
企業には従業員が安全に業務にあたれるよう、職場環境を整える義務があります。ハラスメントを発生させないために、適切な対策を講じましょう。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け