

パソコンやスマートフォンなどを用いた「VDT作業」は、眼精疲労や腰痛など心身にさまざまな影響をおよぼすといわれています。
そのため、従業員が長時間VDT作業に携わる職場では、健康障害を防ぐための対策に悩んでいる人事労務担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、VDT作業が身体におよぼす影響や健康障害を防ぐための対策を詳しく解説します。
 VDT作業とは「visual display terminals」の略で、液晶ディスプレイなどの出力装置と、キーボードやマウスなどの入力装置で構成される機器を使用して作業をすることをさします。
VDT作業とは「visual display terminals」の略で、液晶ディスプレイなどの出力装置と、キーボードやマウスなどの入力装置で構成される機器を使用して作業をすることをさします。
パソコンやタブレット、スマートフォンなどを用いた以下のような作業が、VDT作業に該当します。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:VDT作業」
 厚生労働省は、2002年に「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました。ガイドラインを策定した目的は、VDT作業をする人の心身の負担を軽減するためです。
厚生労働省は、2002年に「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」を策定しました。ガイドラインを策定した目的は、VDT作業をする人の心身の負担を軽減するためです。
そして2019年、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」として17年ぶりにガイドラインがリニューアルされました。リニューアルの背景には、以下の理由が挙げられます。
このような背景を踏まえ、従来のガイドラインのベースは維持しつつ、健康管理を行う作業区分が見直されました。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
 長時間にわたるVDT作業は、従業員の健康にどのような影響を与えるのか理解しておきましょう。
長時間にわたるVDT作業は、従業員の健康にどのような影響を与えるのか理解しておきましょう。
長時間にわたりVDT作業を続けていると、身体に以下のような影響をおよぼす恐れがあると懸念されています。
| 懸念されている身体への影響 | 具体的な症状 |
| 視覚機能への負担 | ・眼疲労(眼が重い、眼がかすむなど)
・ドライアイ ・眼の充血 ・視力低下 ・眼の疲れに伴う頭痛 |
| 筋骨格への負担 | ・首や肩のこり
・腱鞘炎 ・背中の痛み ・腰痛 |
(参考:独立行政法人労働者健康安全機構「VDT作業とその対策」)
視覚機能の症状は、VDT作業による目の使いすぎや、まばたきの回数減少が原因で起こります。
筋骨格への負担による症状は、同じ姿勢で長時間作業を続けることで起こる可能性があります。
VDT作業による影響で、以下のような精神・心理的な症状を引き起こすことがあります。
従業員を精神・心理的な症状を引き起こしている状態で働かせ続けると、精神疾患に陥り休職や退職につながる恐れがあります。
そのような事態を防ぐために、事業者には適切な作業管理や従業員の健康管理が求められます。
【参考】独立行政法人労働者健康安全機構「VDT作業とその対策」
 新VDTガイドラインでは、正社員やパートタイマー、派遣労働者などの雇用形態を問わず、1日のVDT作業時間が4時間以上の従業員を対象としています。
新VDTガイドラインでは、正社員やパートタイマー、派遣労働者などの雇用形態を問わず、1日のVDT作業時間が4時間以上の従業員を対象としています。
過去の調査結果から1日のVDT作業時間が4時間以上の場合は疲労が蓄積されやすいことが示されています。
事業者は、該当する従業員に対して作業時間や健康管理への配慮が必要です。
また、最近ではテレワークの普及により、自宅で情報機器を使用して仕事をする割合が増加してきています。
在宅ワークの場合も、ガイドラインに準じた労働衛生管理が必要とされています。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
 VDT作業による身体的・精神的影響を最小限に抑えるためには、適切な作業環境に整えることが大切です。ここでは、VDT作業に適した環境の整え方を解説します。
VDT作業による身体的・精神的影響を最小限に抑えるためには、適切な作業環境に整えることが大切です。ここでは、VDT作業に適した環境の整え方を解説します。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
事務所衛生基準規則および労働安全衛生規則にもとづく労働衛生基準では、作業場における照度を以下の状態に保つよう規定しています。
| 作業内容 | 推奨されている照度(ルクス) |
| パソコンなどを用いた一般的な事務作業 | 300ルクス以上 |
| 細かな文字の読み込みなどが不要な付随的な事務作業 | 150ルクス以上 |
(参考:厚生労働省「職場における労働衛生基準が変わりました」)
適切な照度が保たれているかは、照度計を用いることで確認できます。
【関連記事】事務所則の改正に伴う対応とは?事業者が取り組むべき項目を解説
目の保護のためには、グレアを減らすことが重要です。グレアとは、太陽光や照明などにより、物の見えづらさや不快感を生じさせるようなまぶしさのことです。
グレアを防ぐための対策には、以下などが挙げられます。
情報機器を使用した作業は多岐にわたるため、それぞれの作業内容に適したデバイスや設備を選択することが重要です。
たとえば、データの集計作業とディスプレイを用いた監視業務では、必要な画面のサイズが異なります。
また、文章のみの作業と画像や映像を使った作業では、求めるスペックが異なるでしょう。
パソコンはノート型・デスクトップ型のどちらがいいのか、ソフトウェアは作業者の能力にあっているかなど、作業者の意見も取り入れながら、情報機器を選ぶことが大切です。
また、作業する人や作業時の環境によって、周辺との明暗差や負担にならない体勢などが異なります。
そのため、ディスプレイ画面の輝度やコントラスト、ディスプレイの位置やキーボードの位置などが作業者によって容易に変更できるものがよいでしょう。
デスクや椅子も同様、作業者自身が使いやすいように高さや背もたれを調整しやすいものが推奨されています。
 仕事に没頭していると、長時間にわたりディスプレイ画面を見続けながら作業してしまいがちです。
仕事に没頭していると、長時間にわたりディスプレイ画面を見続けながら作業してしまいがちです。
このような状況を避けるために事業者は、従業員の作業状況を把握し適切な時間・業務量かを管理・指導する必要があります。ガイドラインでは作業管理について、以下の通り定められています。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
ガイドラインでは、1回の連続作業時間は1時間以内にするようにと定めています。1時間を超える場合は、次の連続作業に取り掛かる前に10~15分程度の休息時間を設けなければなりません。
また、連続作業中も1~2回は小休憩を取らせる必要があります。
ガイドラインには、ディスプレイ画面との視距離はおおむね40㎝以上が望ましいと明記されています。この距離で見えやすくなるようメガネなどで矯正することをおすすめします。
ディスプレイの高さは、ディスプレイの上端が目と同じ高さか、やや下になるようにし、キーボードを自然に手が届く位置に配置しましょう。
 ガイドラインでは、VDT作業による従業員の健康障害を防ぐために、企業は以下の措置をとるよう推奨しています。
ガイドラインでは、VDT作業による従業員の健康障害を防ぐために、企業は以下の措置をとるよう推奨しています。
それぞれの措置について解説します。
VDT作業に従事する従業員に対し、配置前健康診断と定期健康診断を行いましょう。
配置前健康診断とは、新たに情報機器を使用した作業にあたる従業員の配置前に実施する検査を指します。配置前の従業員の健康状態を把握するために必要です。
定期健康診断は、VDT作業にあたる従業員の健康管理を適切に進めるために1年以内ごとに1回、定期的に実施します。VDT健診の検査項目は以下のとおりです。
健診結果をもとに、VDT作業による健康障害を防ぐための作業方法・作業環境の改善など、適切な対策を講じましょう。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」
作業者が自身の健康について気軽に相談し、適切なアドバイスを受けられるような健康相談の機会を設けましょう。
その際、プライバシー保護の十分な配慮や、パートタイマーなど正社員以外の従業員も相談できる環境を整えることが重要です。
VDT作業による健康障害を予防するために、VDT作業中の休憩時間や作業後に体操などをして身体をほぐすよう従業員に促しましょう。
短時間で実施可能な体操やストレッチ、軽い運動などは肩の疲れを防ぐのに効果的です。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
VDT作業にあたる従業員はもちろん、管理者に対しても労働衛生教育を実施することが大切です。研修など機会を設け、以下のことを指導しましょう。
情報機器を用いた作業がもたらす健康リスクや、その効果的な防止方法については、VDT作業者への周知徹底はもちろん、管理者が適切に指導・マネジメントできるような教育が必要です。
作業内容に対して発生している課題の把握や、環境の整備が必要そうな部署に対する指導などを、管理者が適切に対応できるようにしておきましょう。
【参考】厚生労働省「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」
 情報機器の利用環境については、継続的に点検し必要に応じて改善する必要があります。
情報機器の利用環境については、継続的に点検し必要に応じて改善する必要があります。
しかし、情報機器の利用環境には個人差が大きいため、管理者だけで課題を把握・改善していくことが難しい場合もあるでしょう。そのような場合に最も有効なのが、産業医の活用です。
産業医による職場巡視で、客観的かつ専門的な立場から、たとえばディスプレイの照度やオフィスの照明、一連続作業時間が適切に保たれているかなど、チェック・指導してもらえます。
ガイドラインでも、健康診断後に適切な措置を講じることや、健康への影響が懸念される従業員に対して、専門家の指導を仰ぐよう推奨されています。
医療の専門家のサポートを受けながら、安全かつ生産性の高い職場環境へと改善を図りましょう。
【関連記事】 産業医とは? 企業での役割、仕事内容、病院の医師との違いを解説
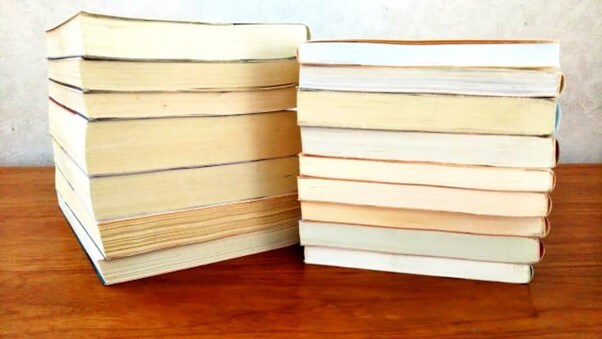 急速なIT化に伴い、さまざまな情報機器が生み出され、働き方や生活スタイルも多様化が進んでいます。
急速なIT化に伴い、さまざまな情報機器が生み出され、働き方や生活スタイルも多様化が進んでいます。
もはや、パソコンやスマホ、タブレットなどのデバイスなくして私たちの仕事・生活は成り立ちません。
だからこそ、情報機器がもたらす健康リスクを正しく理解し、適切な予防・対策をとることが、今後ますます重要になっていくでしょう。
従業員一人ひとりの健康を守り、生産性の高い企業活動を行うためには、新ガイドラインに沿って着実に職場環境を改善していくことが大切です。
本記事でご紹介した内容を参考に、自社に合った環境づくりに取り組みましょう。
エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け