

衛生管理者は、従業員数が一定以上の事業場に配置が定められています。働き方改革やテレワークの拡大、労働者のメンタルヘルス問題などの労働環境の多様化にともない、衛生管理者の役割は重要視されています。
この記事では、衛生管理者の仕事内容や選任義務、配置するメリットを解説します。
 衛生管理者とは、労働安全衛生法にもとづき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人のことです。
衛生管理者とは、労働安全衛生法にもとづき、労働環境の衛生的改善や疾病の予防処置などをして、職場の衛生全般の管理を行う人のことです。
雇用形態を問わず50名以上の従業員が所属している事業場には、職種に関わらず選任義務があります。また、従業員のほとんどが社外に派遣されており、事業場に常時数名しかいない状態でも、所属の従業員が50名以上であれば、衛生管理者の選任が必要です。
さらに、衛生管理者の選任基準である50名以上の従業員が所属している職場には、衛生委員会(安全衛生委員会)の設置義務もあり、衛生管理者が構成員としての役割もはたさなければなりません。
衛生管理者は企業の労務管理の要ともいえる、重要な職務を担っているのです。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」
 厚生労働省が示す衛生管理者の職務内容をもとに、衛生管理者の具体的な仕事内容を紹介します。
厚生労働省が示す衛生管理者の職務内容をもとに、衛生管理者の具体的な仕事内容を紹介します。
【参考】厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」
従業員の健康状態に目を配り、心身の健康に問題を抱える従業員を発見した場合に、適切な対応を行うことが衛生管理者の主要な仕事です。
従業員の心身の健康状態を悪化させないよう、産業医などと連携して回復に向けた以下の対処をします。
【関連記事】華麗なる連携プレーで、メンタル不調の兆しをキャッチ!―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.4
従業員の作業環境に健康を害する要因はないか、衛生面の調査を行うことも衛生管理者の仕事です。衛生管理者には週1回以上の定期的な職場巡視が義務付けられており、以下の観点から従業員の衛生と安全を点検・管理します。
近年は産業医の巡視義務軽減との兼ね合いで、衛生管理者の巡視が重要視されるようになっています。
【関連記事】衛生管理者による職場巡視は義務なのか?労働環境改善に役立つポイントを徹底解説
職場施設全体の安全性と衛生を保つことも、衛生管理者の重要な役割です。
衛生管理者の管理対象は、仕事をするスペースだけにとどまりません。休憩場所のような直接業務と関係のないスペースに対しても、定期的な巡視で衛生環境に問題がないか確認を行います。
衛生管理者の主な点検箇所は以下のとおりです。
万が一の急病や事故に備える救急用具や、保護具の管理・点検を行うことも衛生管理者の役割です。
業種に応じて必要な保護具(保護具手袋、保護メガネなど)や器具を考慮し、以下の点検・整備を行います。
従業員に健康保持の重要性を周知したり、健康相談を受けたりすることも衛生管理者の大切な役目です。
衛生管理者が産業医とのパイプ役となり、従業員が医療的見地から必要なアドバイスを得られる場を設定します。
たとえば、従業員が産業医面談を受けられるよう日程を調整し、産業医に必要な報告書を渡すなどのサポートを行うほか、以下の業務に携わります。
【関連記事】
健康診断の再検査、従業員に受けてもらうには?企業がとるべき対応を解説
【人事担当者必見】休職に必要な手続きと対策とは?うつ病時の手当から復職対応まで
労働災害防止や衛生環境整備に活かすために、労働者の負傷や疾病などの記録を統計化することも、衛生管理者の重要な仕事です。
従業員の日頃の健康状態や連携医療機関の管理も含め、主に以下の統計・リスト化を行います。
衛生管理者は、派遣・出向などによる他の事業の労働者と同じ作業に従事する場合に、衛生面で必要な配慮と対応を行います。
衛生管理者は以下の観点から職場の衛生環境をチェックし、問題があれば改善策を立案して対策を講じます。
従業員の健康・安全状態に関わる職場の衛生環境について衛生日誌へ記録しておくことも、衛生管理者の仕事です。
記録を残すことで労働災害を防ぎ、従業員が安全かつ健康的に働けるための職場づくりにつながります。
衛生日誌の記録や保存義務はないものの、労働基準監督署の監督官の臨検で巡視記録を求められるのが一般的です。以下の記録を残せば、臨検時に企業が安全配慮義務を怠っていないことを証明できます。
健康診断の受診状況
【関連記事】労働基準監督署の臨検とは?調査の種類や指摘されやすい項目を解説
有害業務などで生じる危険性や有害性の調査や、調査・リスクアセスメントの結果にもとづいた必要な措置も、衛生管理者の役割です。
労働安全衛生法の改正により、通知の義務対象物質が追加されたことを受け、衛生管理者の対応範囲も拡大しています。
これまで国の規制対象外だった有害な化学物質についても、今後は順次ばく露の上限基準が策定されることになりました。新たに加わった有害物質の危険性・有害性に関する情報伝達方法の整備は、各企業の衛生管理者も担うとされています。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」
安全衛生に関する計画の作成(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Action)も衛生管理者の役割です。
衛生管理者は日頃の衛生管理活動や統計データをもとに課題を発見し、周辺職種と連携して健康推進・労災防止のアイデアを出し合います。
たとえば衛生日誌の内容のうち、衛生委員会で検討が必要と思われる項目があれば報告し、委員会で対策や改善案を策定します。
そして実施した対策を評価したうえでデータとして蓄積し、さらなる改善へと活かすことが、衛生管理者のPDCAサイクルです。
現場からは環境改善を経営側に提言しにくい場合もあるでしょう。しかし、衛生管理者には経営者に問題点を報告する法的義務があり、改善策を遂行する権限を与えられているため、実行力を発揮できます。
 衛生管理者には「選任義務」があり、定められた人数を選任した後は、期限までに所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。ここでは衛生管理者の選任義務について解説します。
衛生管理者には「選任義務」があり、定められた人数を選任した後は、期限までに所轄の労働基準監督署へ届け出なければなりません。ここでは衛生管理者の選任義務について解説します。
従業員が50名以上いる事業場には衛生管理者の選任義務があり、選任しなければならない人数は、従業員数に応じて以下のように決められています。
| 常時使用する事業場の従業員数 | 専任が必要な衛生管理者数 |
| 1~49名 | 衛生管理者の選任義務なし
(安全衛生推進者を専任) |
| 50~200名 | 1名以上 |
| 201~500名 | 2名以上 |
| 501~1,000名 | 3名以上 |
| 1,001名~2,000名 | 4名以上 |
| 2,001名~3,000名 | 5名以上 |
| 3,001名以上 | 6名以上 |
(参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」)
同じ敷地内に事業場が2つあり、どちらも50名以上従業員が所属している場合は、原則として各事業場1名ずつの選任義務が生じます。
ただし、2人以上の衛生管理者を選任する場合で、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントがいる場合には、労働衛生コンサルタントのうち一人は専属でなくても問題ありません。
【参考】厚生労働省「衛生管理者について教えて下さい。」
衛生管理者の選任義務が生じた場合は14日以内に選任し、選任報告書を所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。
選任報告書は、厚生労働省のサイトからダウンロード可能です。必要事項を記入したら、郵送や電子申請で提出します。
前任の衛生管理者の突然の退職や死亡など、やむを得ない事由により14日以内に選任できない場合は、その旨を所轄労働基準監督署に報告すれば、おおむね1年以内まで選任を免除してもらえます。
ただし、特定の者が衛生管理者業務を行うのが条件です。
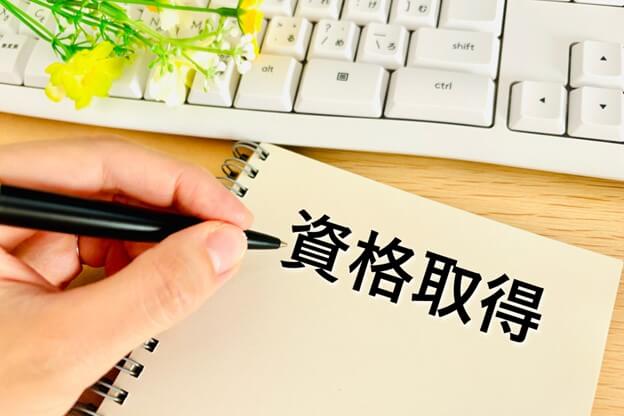 選任が必要な衛生管理者は、事業場の業種により第一種・第二種とで種別が異なります。第一種と第二種それぞれで対応できる業種は以下のとおりです
選任が必要な衛生管理者は、事業場の業種により第一種・第二種とで種別が異なります。第一種と第二種それぞれで対応できる業種は以下のとおりです
| 資格の種類 | 対応できる業種 |
| 第一種衛生管理者 | 農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業 |
| 第二種衛生管理者 | 金融業、保険業、情報通信業、小売業など |
(参考:厚生労働省「職場のあんぜんサイト:衛生管理者」)
第一種免許をもつ衛生管理者は、危険をともなう「有害業務」を含むすべての業種に携われます。
一方第二種免許では、携われる業種が金融・保険業や情報通信業、小売業などに限定されます。
従業員に資格を取得させる際には、自社の業種に合わせて受験させることが重要です。
【関連記事】〈2024年版〉難易度・合格率は?衛生管理者試験の対策と手続き総まとめ
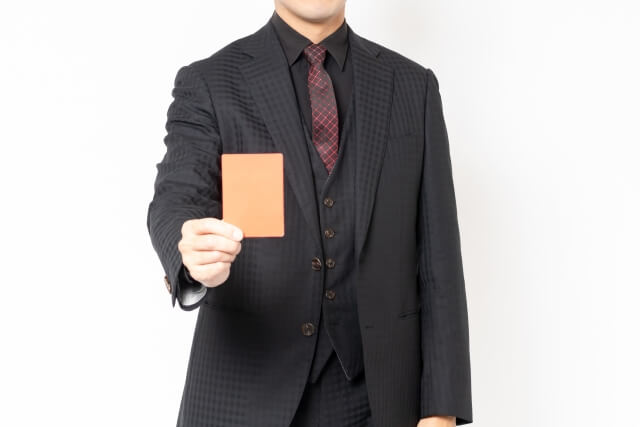 選任義務がありながら衛生管理者を配置しない場合は、労働安全衛生法にもとづき50万円以下の罰金が科されます。
選任義務がありながら衛生管理者を配置しない場合は、労働安全衛生法にもとづき50万円以下の罰金が科されます。
衛生管理者が不在となりそのまま放置した場合、労働基準監督署から是正命令を受け、罰金を科せられるため注意しましょう。
それでも改善されない悪質なケースでは、経営者が逮捕・起訴される場合もあります。
【参考】e-Gov法令検索「労働安全衛生法」
 衛生管理者と混同されやすいのが安全管理者です。衛生管理者について理解するためにも、安全管理者との役割の違いや、選任の方法を覚えておきましょう。
衛生管理者と混同されやすいのが安全管理者です。衛生管理者について理解するためにも、安全管理者との役割の違いや、選任の方法を覚えておきましょう。
文字通り職場の安全に関して管理する役割を担うのが安全管理者です。労働者の命や健康を守る観点は、衛生管理者と変わりません。
衛生管理者は職場の衛生管理や、労働者のメンタルヘルスに関する問題を管理するのが役割で、労働者の健康を守るための存在です。
対して安全管理者は、職場や業務手順に関する危険を管理したり、消防・避難訓練を実施したりして、労働者の安全を守るための役割を担います。
安全管理者は、労働安全衛生法で定められた業種で、常に50人以上の労働者を使用する場合に選任が必要です。
安全管理者になるには、安全管理者選任時研修を修了する必要があります。衛生管理者は国家資格なので、試験の合格が条件となりますが、安全管理者選任時研修は誰でも受講さえすれば選任可能です。
しかし、安全管理者選任時研修には受講資格が設けられており、卒業区分に応じて一定の産業安全実務に従事した経験が求められるため注意しましょう。
また、法律上は安全管理者と衛生管理者の兼務も可能ですが、それぞれが担う業務は異なるため、なるべく兼務を避けるのが無難です。
【参考】
厚生労働省「安全管理者について教えて下さい」
公益社団法人労働管理教育センター「安全管理者選任時研修 受講のご案内」
 衛生管理者以外に、企業によっては統括安全衛生管理者の選任も求められます。統括安全衛生管理者の役割や選任条件を把握しておきましょう。
衛生管理者以外に、企業によっては統括安全衛生管理者の選任も求められます。統括安全衛生管理者の役割や選任条件を把握しておきましょう。
統括安全衛生管理者は、衛生管理者と安全管理者を指揮管理する人です。労働者の健康が維持管理されるための措置に関して、統括管理するのが役目です。
衛生管理者が職場の衛生管理に関する実務を担うのに対し、統括安全管理者は管理する立場で、具体的な措置の決定に責任をもちます。衛生管理者や安全管理者は、課題や懸念を統括安全衛生管理者と共有しながら、職場環境の適正化を目指します。
統括安全衛生管理者は、労働安全衛生法で定める一定の業種ごとに定められた労働者数を超えた場合に、選任が義務づけられています。
たとえば建設業では、常に100人以上の労働者を使用する場合に選任義務があります。選任義務は100人以上からなので、50人以上100人未満の事業場では、統括安全衛生管理者を選任しなくても問題ありません。
また、統括安全衛生管理者には、工場長や所長をはじめとした、実質的に事業場の管理を担っている人が選任されます。統括安全衛生管理者と衛生管理者の兼務は法的に禁止されてはいませんが、担う役割は異なり、適正な衛生管理を考える上では避けるべきです。
【参考】厚生労働省「統括安全衛生管理者について教えて下さい」
衛生管理者は従業員が一定数以上いる事業場では義務となっていますが、それ以外にも配置することによるメリットがあります。その一例を紹介します。
衛生管理者の配置により労働環境が改善すれば、従業員の業務パフォーマンス向上につながります。
衛生管理者が健康診断結果を管理していれば、従業員の健康上の問題を把握できるため、病欠の低減が可能です。欠勤者が少なくなれば、周囲の業務負担増加による士気の低下を抑えられ、生産性を維持できるでしょう。
また、社内に健康相談窓口を設置すれば、心身の病気の防止や早期発見につながります。メンタルの不調も相談できるため、従業員も安心して仕事に臨めるようになり、エンゲージメントと業務パフォーマンスの向上が期待できます。
衛生管理者を配置すれば、職場巡視や衛生教育の徹底により、労働災害を未然に防げます。
衛生管理者は過去のケーススタディやリスクアセスメントの視点から労働災害のリスクを分析できるため、従業員へリスク回避の教育が可能です。
また、衛生委員会の開催により、小さなリスクを早期発見することもできるでしょう。それにより、大きなトラブルに発展することを防ぐことにつながります。
衛生管理者が職場巡視や衛生教育などを定期的に行うことで、従業員の健康に対する意識向上が期待できます。
健康診断を実施しても、従業員が診断結果を理解しきれない場合もあるでしょう。しかし衛生管理者が健康診断結果を管理していれば、データに潜むリスクを指摘でき、従業員自身の健康管理につなげられます。
また、衛生管理者による衛生教育が浸透すれば、社内に健康を重視する文化を醸成できます。長時間労働が常態化している職場でも、専門家の立場で従業員に休息を促せば、現場の意識改革に効果的です。
 衛生管理者の職務は、産業医や安全管理者、統括安全衛生管理者と連携して従業員の健康維持・管理をサポートし、労働災害を未然に防ぐことです。
衛生管理者の職務は、産業医や安全管理者、統括安全衛生管理者と連携して従業員の健康維持・管理をサポートし、労働災害を未然に防ぐことです。
衛生管理者は、従業員数50名以上の事業場に選任が義務付けられています。業種によりもつべき資格が異なるため、担当者は自社の業務に合わせた資格取得が必要です。
衛生管理者による職場の衛生環境改善は、従業員のモチベーションと生産性の向上にも貢献します。衛生管理者を適切に選任し、労働災害のない健康経営につなげましょう。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け