

ストレスチェック後の面談とは、高ストレスと判断された従業員に対して医師が実施する面談です。
高ストレスの従業員が適切に面談を受けられるように、事業者は面談の流れを把握しておく必要があります。
本記事では、ストレスチェック後の面談の対象となる従業員や、面談実施の流れを解説します。
目次
 ストレスチェック制度とは、従業員が普段の業務の中で感じているストレスの大きさを客観的に調査し、必要に応じた措置を行うためのものです。
ストレスチェック制度とは、従業員が普段の業務の中で感じているストレスの大きさを客観的に調査し、必要に応じた措置を行うためのものです。
具体的には、選択式のストレスに関する質問票に従業員に回答してもらい、仕事上のストレスをどの程度感じているのかを分析します。
また、分析によって職場がどの程度ストレスを感じやすい環境なのかを把握することも可能です。
ストレスチェックによって従業員のメンタルヘルスの問題が把握できれば、休職・退職を未然に防止できます。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
 ストレスチェック後の面談とは、ストレスチェックで高ストレスと診断された従業員に実施する面談です。高ストレスと診断された従業員のメンタルヘルス不調を防止することを目的としています。
ストレスチェック後の面談とは、ストレスチェックで高ストレスと診断された従業員に実施する面談です。高ストレスと診断された従業員のメンタルヘルス不調を防止することを目的としています。
面談は医師から高ストレスの従業員に対して、ストレスの原因や職場環境について聞き取り、必要に応じて専門医などを紹介します。
従業員と面談をしたうえで職場環境の改善が必要と判断された場合は、事業者に対して意見を伝えなければなりません。
【参考】厚生労働省「長時間労働者、高ストレス者の面接指導について|こころの耳:働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト」
 ストレスチェック後の面談を実施できる担当者は、労働安全衛生法により医師のみに限られています。ストレスチェック実施者である、精神保健福祉士や保健師は面談できません。
ストレスチェック後の面談を実施できる担当者は、労働安全衛生法により医師のみに限られています。ストレスチェック実施者である、精神保健福祉士や保健師は面談できません。
産業医を選任している場合は、面談実施者として産業医を指名できます。外部に委託する場合も、産業医の資格をもつ医師を選任するのがよいでしょう。
産業医の選任義務がない事業所の場合は、産業保健総合支援センターの利用がおすすめです。
産業保健総合支援センターでは、産業医の選任義務がない小規模事業場に対して、産業保健に関する相談・訪問支援などを無料で行っています。医師によるストレスチェック後の面談も依頼できるので、活用するとよいでしょう。
【参考】e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
【関連記事】産業保健総合支援センター(さんぽセンター)とは? 役割や地さんぽとの違いを解説
 ストレスチェック後の面談の対象者は、高ストレスと診断を受けた従業員のうち、面談を受けたいと申し出た従業員に限られます。従業員自らの申し出がないと、ストレスチェック後の面談を実施できません。
ストレスチェック後の面談の対象者は、高ストレスと診断を受けた従業員のうち、面談を受けたいと申し出た従業員に限られます。従業員自らの申し出がないと、ストレスチェック後の面談を実施できません。
そのため、事業者はストレスチェック後の面談が受けやすい職場環境を整備することが求められます。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
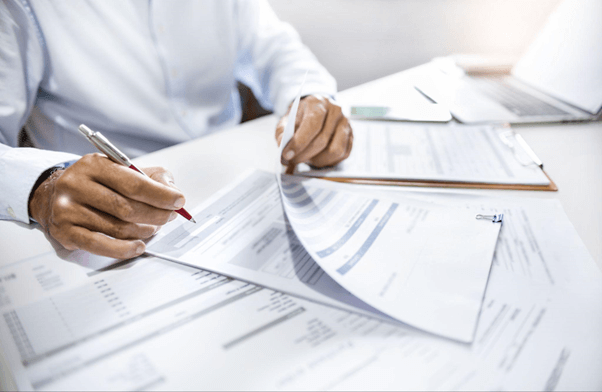 医師が面談をスムーズに行えるように、事業者は以下の情報を事前に準備しましょう。
医師が面談をスムーズに行えるように、事業者は以下の情報を事前に準備しましょう。
上記の情報を医師に提供できると面談前に高ストレス者の情報を整理でき、当該従業員に対し円滑に聞き取り調査を行えます。
【参考】厚生労働省「面接指導の具体的な進め方と留意点」
 高ストレス判定の従業員に対する面談の流れは、以下のとおりです。
高ストレス判定の従業員に対する面談の流れは、以下のとおりです。
それぞれの手順について解説します。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
ストレスチェックの診断結果をもとに、過度にストレスを抱えた従業員を選定します。高ストレス者は以下の判断基準にもとづき、ストレスチェック実施者が選定しなければなりません。
医師との面談が必要と判断された高ストレス者には、面談指導の申し出を勧奨しましょう。
高ストレス判定の従業員から面談の申し出を受けたら、事業者は医師にストレスチェック後の面談を依頼します。面談は従業員による申し出を受けてから1ヶ月以内に実施するのが望ましいです。
面談日時は就業時間内に設定し、従業員が面談を受けやすい環境を整える必要があります。周囲の目が気にならずにリラックスして話せる会議室などがよいでしょう。
医師による面談では、高ストレス者の状況を把握するために以下のようなことを確認します。
| 確認内容 | 具体的な聞き取り事項 |
| 従業員の勤務状況 | ・勤務時間
・業務内容 ・職場環境における心理的負担の原因 ・周囲のサポート状況 |
| 従業員の心理的負担 | ・抑うつの症状
・精神疾患の症状 |
| 従業員の心身の状況 | ・現在の生活状況
・過去に受けた健康診断の結果 |
医師は上記内容を確認後、医学的に判断したうえでストレスの対処方法やセルフケアを伝えます。また、従業員の状況に応じて専門機関への受診を促します。
高ストレス者と面談した医師の意見を踏まえて、事業者は職場環境の改善を行います。従業員の状況に応じて配置転換や就業の制限、休業などを検討しましょう。
従業員の就業条件を変更したり職場環境を改善したりする場合は、医師の判断を仰ぐとよいでしょう。
医師による面談を終えたあとは、ストレスチェック結果や面談指導結果についての報告書を作成し、労働基準監督署へ提出します。また、事業者は報告書を5年間保管しなければなりません。
報告書は、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
【関連記事】ストレスチェックは結果報告書の提出が必須!正しく理解して実施しよう
【関連資料】【産業医監修】産業医面談の受診勧奨 参考例文フォーマット
 高ストレス判定の従業員から面談の申し出がなくても、放置せず医師による面談を受けるように促しましょう。事業者には、従業員が健康かつ安全に働けるようにするための安全配慮義務があるからです。
高ストレス判定の従業員から面談の申し出がなくても、放置せず医師による面談を受けるように促しましょう。事業者には、従業員が健康かつ安全に働けるようにするための安全配慮義務があるからです。
従業員が高ストレス状態であると把握していながら面談を受けるよう勧奨せず、従業員の健康が損なわれた場合、安全配慮義務違反に問われる可能性があります。
そのため高ストレスの従業員に対して、面談を受けることの重要性や不利益な扱いがないことなどを伝えましょう。また、複数回にわたって面談の申し出の勧奨を行うことも大切です。
【参考資料】【産業医監修】産業医面談の受診勧奨 参考例文フォーマット
【関連記事】安全配慮義務違反に該当する基準とは?企業が取り組むべき対策も解説
 ストレスチェック後の面談を実施する際は、以下の点に注意が必要です。
ストレスチェック後の面談を実施する際は、以下の点に注意が必要です。
それぞれの注意点について解説します。
【参考】厚生労働省「労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル」
事業者は、ストレスチェック後の面談をした従業員に対し、以下のような不利益な取り扱いをしてはなりません。
上記のような不当な取り扱いは、労働安全衛生法により禁じられています。面談実施後は医師による意見を踏まえたうえで、従業員に配慮した措置を検討しましょう。
【参考】e-Gov 法令検索「労働安全衛生法」
事業者は、ストレスチェックの結果や面談内容に関する情報を保護しなければなりません。ストレスチェックの結果や面談内容は個人情報であり、従業員の了承を得ずに共有することはできないからです。
面談結果の取り扱い(利用目的や共有する範囲)は、事業所ごとにルールを定めておく必要があります。安全衛生委員会もしくは衛生委員会により、調査審議することが望ましいです。
面談結果を含む健康情報を取り扱うルールを定めた場合は、速やかに従業員へ周知しましょう。
【関連記事】安全衛生委員会と衛生委員会とは? それぞれの役割と開催条件について
 派遣社員は派遣元企業が雇用先なので、高ストレスの判定を受けた派遣社員がいる場合は、派遣元企業にストレスチェック後の面談を実施する義務があります。
派遣社員は派遣元企業が雇用先なので、高ストレスの判定を受けた派遣社員がいる場合は、派遣元企業にストレスチェック後の面談を実施する義務があります。
ただし、ストレスチェック結果の集計・分析は、事業場単位で実施しなければなりません。そのため、派遣社員のストレスチェックは、派遣先企業での実施が望ましいとされています。
派遣社員が高ストレスの判定を受けた場合は、就業契約の変更を検討する必要もあります。
従業員に対して不利益がないように、派遣元・派遣先の企業で連携を図り、職場環境の改善や就業条件の変更を検討しましょう。
【参考】厚生労働省「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度について」
【関連記事】派遣社員は「従業員数」に含める? 従業員数50名以上の企業の義務とは
 高ストレスと判定された従業員に対し医師の面談を実施することで、メンタルヘルスによる不調を未然に防止できます。ただし、ストレスチェック後の面談は、従業員自らが申し出なければ実施できません。
高ストレスと判定された従業員に対し医師の面談を実施することで、メンタルヘルスによる不調を未然に防止できます。ただし、ストレスチェック後の面談は、従業員自らが申し出なければ実施できません。
事業者は当該従業員に対し、医師の面談を受けることの重要性や不利益な取り扱いがない旨を伝えて、ストレスチェック後の面談を促しましょう。
産業医の選任など、産業保健関連の法定義務が一目でわかるチェックシートです。 最近では、労基署から指摘を受けた企業担当者からの相談も少なくありません。働き方改革を推進する観点から、国では今後も法定義務が遵守されているかの確認を強化していくと思われるため、定期的に自社の状況を確認することをお勧めします。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け