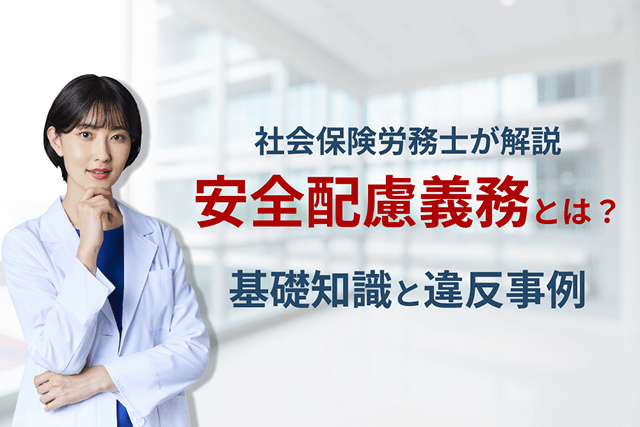

目次
労働安全衛生法に違反した場合、どのような罰則が科されるかご存知でしょうか。人事労務担当者として、自社の安全衛生管理体制が法令を遵守しているか、常に把握しておく必要があります。
この記事では、労働安全衛生法に違反した場合の罰則について罰則一覧や具体的な違反事例、企業と個人の両方に科される「両罰規定」について解説します。
労働安全衛生法に違反した場合、違反内容に応じて主に4つの罰則が科されます。これらの罰則は、違反の重大性や悪質性によって程度が異なります。
労働安全衛生法に違反した場合の具体的な罰則を一覧でまとめました。自社の管理体制がどの規定に抵触する可能性があるか確認するのに役立てていただけます。
労働安全衛生法には「両罰規定」が設けられています。これは、法人(企業)と法人を代表する個人(事業主や役員など)の両方に罰則を科すというものです。
例えば、安全配慮義務を怠った結果、労働者が事故にあった場合、直接の違反者である担当者だけでなく、企業そのものも罰則の対象となります。これにより、企業全体で法令遵守を徹底し、安全衛生管理を推進する責任を負うことになります。
法令違反による罰則を回避するためには、日頃からの予防策が重要です。以下の対策を参考に、社内の安全衛生体制を見直してみてください。
これらの対策を講じることで、法令違反のリスクを低減し、従業員が安心して働ける環境を整備することが可能となります。
労働安全衛生法の違反は、企業に罰則という大きなリスクをもたらします。懲役や罰金といった刑事罰に加え、行政処分や損害賠償のリスクも無視できません。
人事労務担当者として、法令を正しく理解し、自社の安全衛生管理体制が適切に運用されているか定期的に確認することが重要です。この記事で解説した罰則一覧や両罰規定、そして予防策を参考に、法令遵守を徹底していただければ幸いです。
エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。
従業員数が50名を超えた事業場には、労働法令によって4つの義務が課せられています。 「そろそろ従業員が50名を超えそうだけど何から手をつければいいんだろう」「労基署から勧告を受けてしまった」。従業員規模の拡大に伴い、企業の人事労務担当者はそんな悩みを抱えている人も少なくありません。 本資料ではそのようなケースにおいて人事労務担当者が知っておくべき健康労務上の義務と押さえるべきポイントについて詳しく解説していきます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け