
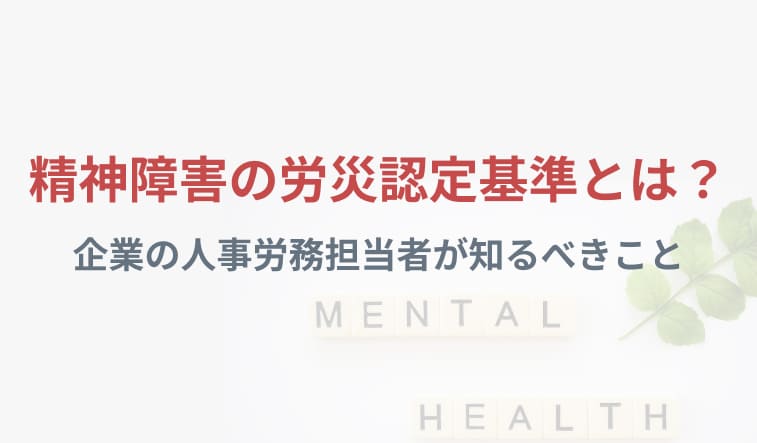
従業員のメンタルヘルス不調が社会的な課題となるなか、精神障害による労災申請は企業にとって重要なテーマとなっています。しかし、「何から手をつけたらいいかわからない」「複雑な手続きや基準が理解できない」と悩んでいる人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。この記事では、心理的負荷による精神障害の労災認定基準について、企業の人事労務担当者が知っておくべき最新の情報をわかりやすく解説します。
目次
精神障害の労災認定は、単なる手続きではありません。従業員の安全配慮義務を果たすためにも、企業が認定基準を正しく理解し、適切な対応をとることが求められます。認定基準を知ることは、労災申請があった際にスムーズな対応を可能にするだけでなく、日頃から従業員のメンタルヘルスをケアする体制を構築するためにも不可欠です。
精神障害の労災認定は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。これらの基準は、2023年9月1日から改定されています。
まずは、発病した精神障害が労災認定の対象となるかどうかが問われます。対象となるのは、国際疾病分類(ICD-10)に記載されている精神障害です。うつ病や適応障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)などが含まれます。ただし、パーソナリティ障害やアルコール依存症などは、通常、労災認定の対象とはなりません。
次に、発病の原因が業務による「強い心理的負荷」であると認められる必要があります。この「心理的負荷」の強度は、客観的な事実に基づいて判断されます。具体的には、精神障害の発病前おおむね6か月の間に、業務に関連して「出来事」があったかどうか、そしてその出来事の「心理的負荷の強度」が「強」と評価されるかがポイントになります。
最後に、業務以外の要因、例えば個人的な出来事や病歴などが精神障害の発病に大きく影響していないことも確認されます。業務上の心理的負荷と発病との間に、明確な因果関係が認められることが重要です。
2023年9月1日から、精神障害の労災認定基準が改定されました。主な変更点は以下の通りです。
心理的負荷の強度は、「強」「中」「弱」の3段階で評価されます。ここでは、改定後の基準も踏まえ、「強」と評価される代表的な出来事をご紹介します。
実際に労災申請が行われた際、どのような流れで手続きが進むのかを把握しておきましょう。
従業員から労災申請の相談があった際、企業の人事労務担当者は以下の点に注意して対応してください。
労災申請は労働者の権利です。会社が不利益を被ることを恐れて、申請を妨害したり、不利益な取り扱いをしたりすることは、法律で禁止されています。もし労災と認められなかったとしても、会社として誠実に対応する姿勢が、従業員との信頼関係を維持するために不可欠です。
精神障害の労災認定は、従業員と企業双方にとって重要な問題です。以下の3つのポイントを参考に、日頃から対策を講じましょう。
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めており、職場におけるメンタルヘルスケアを推進しています。 この指針では、メンタルヘルス対策には4つのケアがあると定義されています。 本資料では、この4つのケアを軸とし、弊社が推奨する取組事項をまとめ、チェックリストにしています。 「セルフケアに関する取り組みが足りていない」「事業場外資源によるケアを行えていない」等、各領域の取り組み状況の確認にご活用ください。
企業の人事・労務担当者が思い悩むことの1つに、従業員のメンタルヘルス対応が挙げられるでしょう。 本資料では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷の産業医兼精神科医の岸本 雄先生に、 産業保健現場で起きていることやその対応について解説いただいた内容をまとめています。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け