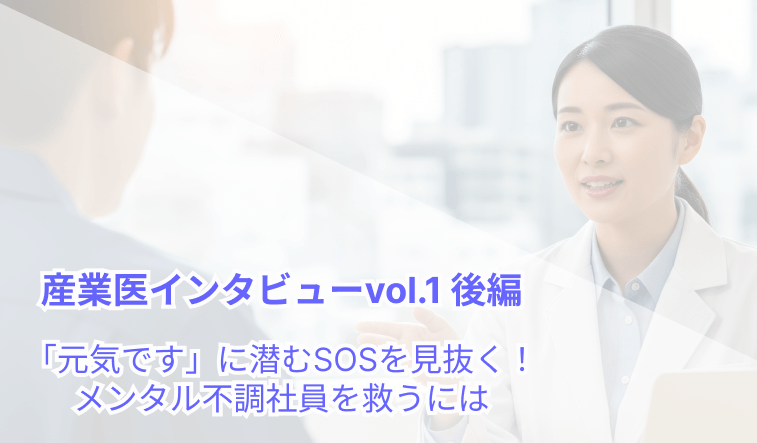
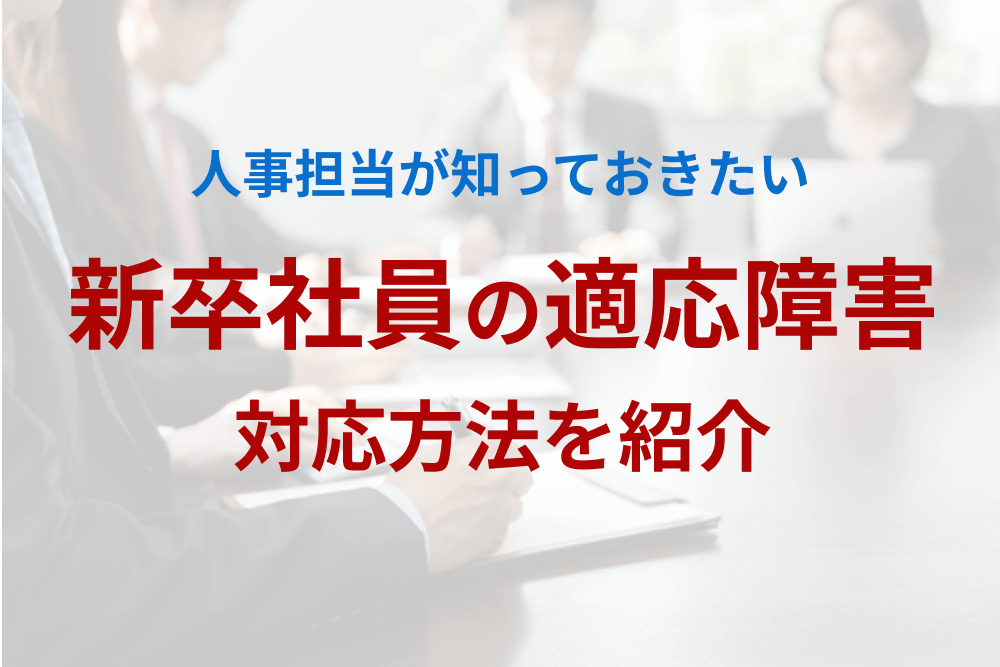
せっかく入社してくれた新卒社員は、今後大切に育成していきたいと考える企業が多いでしょう。そこで、早期離職の防止として職場のサポートが重要な課題かと思いますが、新卒社員は「適応障害」を発症するケースが増加しているともいわれており、適切な対応が求められています(※1)。
本記事では、適応障害について早期発見のサインから具体的な対応フローに焦点を当て、産業医との連携を含めた予防と対応策について紹介します。
目次

適応障害とは、明確なストレス因子(環境変化など)に対する不適応反応として現れる心身の状態を指します。
新卒社員にとっては、学生から社会人への急激な役割転換がこの大きなストレス因子となっていることが考えられます。
また、適応障害のこの病態は、「甘え」や「根性不足」などと誤解されがちですが、医学的には誤った認識といえます。
また、適応障害はストレスの原因がはっきりしており、その原因から離れると比較的速やかに回復するという特徴があり、この点がうつ病との違いといわれています。
適応障害の診断基準では、症状はストレス因子に反応して生じるため、入社後の環境変化という強いストレスに晒される期間、すなわち入社から3ヶ月以内に出現しやすいという実態があります(※2)。
これは臨床現場の知見とも一致しており、企業はこの初期段階でのサインを見逃さないことが大切です。
適応障害の症状は、従業員個人の生活や業務に著しい支障をきたします。適応障害に陥る原因は複合的でありますが、特に新卒社員では次のようなことが考えられます。
厚生労働省の調査「新規学卒者の離職状況(令和3年卒業者」によると、大学卒業者で約3割、高校卒業者で約4割が3年以内に離職しています。
また、1年以内の離職率も、高校卒業者、大学卒業者ともに1割前後と高い水準です。
離職に至る主な要因として、内閣府の調査「平成30年版 子供・若者白書(新入社員の離職理由)」によれば、メンタルヘルスに深く関わる要因が上位を占めています。
具体的には、「仕事が自分に合わなかった」が4割以上、「人間関係」と「ノルマや責任が重すぎた」がそれぞれ約2割となっています。若手従業員(20代)は、他の年代と比べてメンタルヘルス不調の経験率が高い傾向にあり(※3)、この層が環境変化に起因する適応障害の発症リスクが高いことを強く示唆しています。
新入社員のメンタルヘルス不調による離職は企業側の損失にもつながります。
そのため企業では、メンタルヘルス不調を防ぐ「一次予防」から、再発を防ぐ「三次予防」まで、多角的な対応が求められます。この対策の実行において、産業医との連携は欠かせません。
・業務負荷を適切に保つことが大切
業務指示の際は目的、背景、期限を明確に伝え、適切な業務量を設定し、責任が集中しすぎることを防ぎます。また、長時間労働になっている場合も十分な注意が必要です。。
・コミュニケーション、関係性の構築
質問や相談がしやすい雰囲気づくりも大切です。上司や先輩による定期的な1on1ミーティングを行いましょう。なお、1on1では業務の進捗だけでなく、体調や精神状態についても話せる機会としてとらえましょう。
・産業医との連携(研修)
入社時の研修にて、産業医や保健師などの専門家が講師となり、ストレスマネジメント、セルフケア、社内相談窓口の活用方法を周知することで一次予防につなげます。
・不調サインの把握
新卒社員の上司や人事担当者は、特に入社後3ヶ月〜半年頃に現れやすいといわれている次のような行動的症状や精神的・身体的症状に注意を払う必要があります。
行動的症状の例:業務効率の低下、ミスの増加、遅刻・欠勤・早退の増加、口数の減少、服装の乱れ。
精神的・身体的症状の例:抑うつ気分、強い不安・イライラ、睡眠障害、持続的な頭痛や胃腸症状。
・産業医との連携
ストレスチェックで高ストレスと判定された社員や、新卒社員の上長から不調の申告があった社員に対しては、産業医面談をすすめます。
産業医は面談を通じて心身の状態を医学的に評価し、必要に応じて医療機関への受診勧奨を行います。また、業務調整(業務量の軽減、配置の見直しなど)に関する意見書を会社に提出し、人事部門が具体的な対応を取るための判断材料を提供します。
・休職制度と休職中の支援
適応障害の症状が悪化してしまった場合等には休職となることもあるでしょう。
人事としては、新卒社員が休職制度を利用できるよう支援します。また、その際には傷病手当金の制度について情報提供することで、経済的な不安を軽減します。
・産業医との連携(復職支援)
復職時には産業医の役割が特に重要です。
産業医は、休職中の社員の主治医と連携し、回復状況や就業上の配慮事項を確認します。
また、復職に際しては、産業医が復職可否の判断に関わるとともに、短時間勤務や軽減業務から始める「段階的復職」の計画策定に専門家として関与します。
・復職後のフォロー
適応障害で休職していた新卒社員が復職した後も、適切なフォローが重要です。
例えば、残業を控える配慮や、通院しやすい環境整備を行います。
また、生活リズムの確立、ストレス対処法の習得を支援するため、リワーク施設の活用も積極的に推奨します。
新卒社員の適応障害について、発症理由や人事としての対応法を紹介しました。
適応障害は環境の変化を理由に起こることがあり、その背景には個々人の問題というよりも、組織や職場環境から生じている可能性もあるでしょう。
例えば、「他の従業員が見ている中で叱責されている社員はいないか」「怒号が飛ぶような過激な指導が行われていないか」といったことがないか改めて組織全体を見直し、健全な職場環境を再構築する機会として捉えることが、人事や上司の責任です。
そして、産業医の専門性を活用した適切なサポート体制を体制を構築することで、個人の成長と健全な職場環境の実現につながります。適切な知識と対応をもって、若手社員の定着と活躍を支援していきましょう。
【出典元・脚注】
(※1)厚生労働省「過労死等の労災補償状況」
(※2)適応障害の診断における時間的基準(ICD-10など)より
(※3)日本生産性本部「第11回「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査結果」
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めており、職場におけるメンタルヘルスケアを推進しています。 この指針では、メンタルヘルス対策には4つのケアがあると定義されています。 本資料では、この4つのケアを軸とし、弊社が推奨する取組事項をまとめ、チェックリストにしています。 「セルフケアに関する取り組みが足りていない」「事業場外資源によるケアを行えていない」等、各領域の取り組み状況の確認にご活用ください。
企業の人事・労務担当者が思い悩むことの1つに、従業員のメンタルヘルス対応が挙げられるでしょう。 本資料では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷の産業医兼精神科医の岸本 雄先生に、 産業保健現場で起きていることやその対応について解説いただいた内容をまとめています。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け