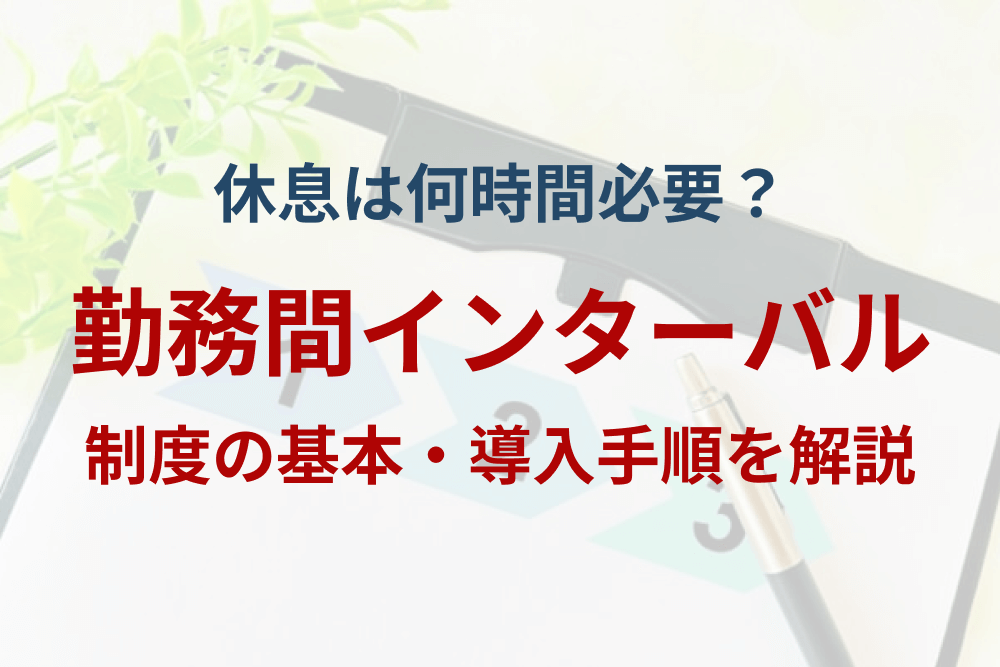
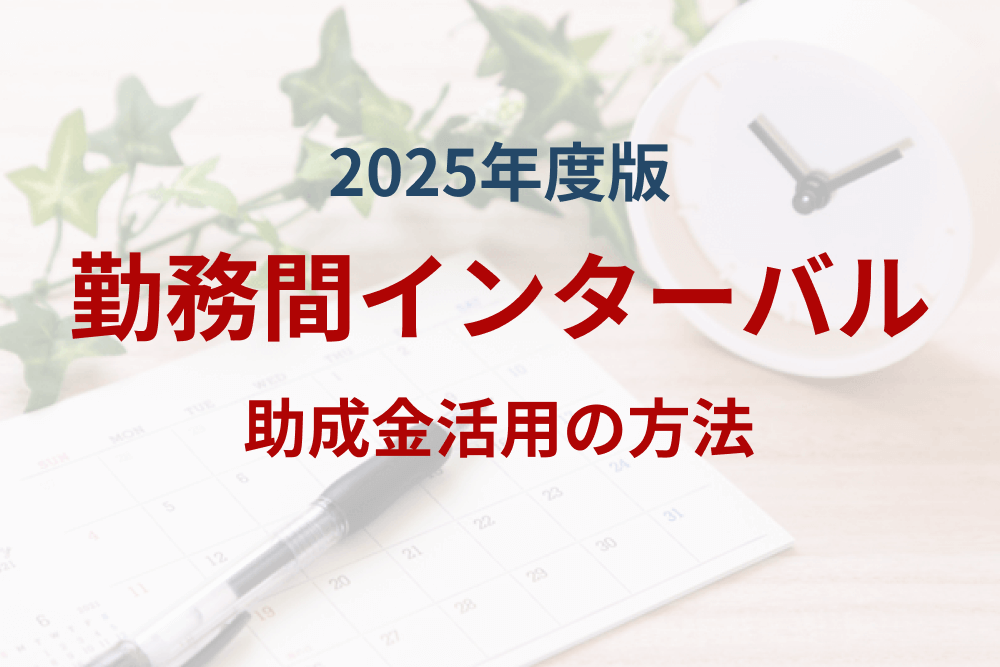
目次

勤務間インターバル制度とは、就業時刻から次に始業する時刻までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を確保する制度です。
勤務間インターバル制度の目的は、従業員の生活リズムを整えたり睡眠時間を確保したりして、健康的に働き続けられるようにするためです。従来は接客業や輸送業など長時間労働が避けられない職場でよく導入されていましたが、近年は職種を問わず導入を検討する企業が増えています。
また、働き方改革の一環として政府も推進しており、勤務間インターバル制度を導入する企業に対して助成金が支払われます。
本記事では、
【参考】厚生労働省「勤務間インターバル制度について」

勤務間インターバルを導入する事業場が活用できる助成金には、「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」があります。申請の手順は以下のとおりです。
なお、「交付申請書」の提出締め切りは11月28日となっています。
支給対象となる事業者の条件・取り組み・支給額について詳しく解説します。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」を受給するためには、以下のいずれか一つ以上の取り組みを実施していなければなりません。
(参考:厚生労働省「令和7年度『働き方改革推進支援助成金』勤務間インターバル導入コースのご案内」)
勤務間インターバル制度をはじめて導入する事業場なら、制度についての社内研修や、就業規則の変更などは比較的取り組みやすいでしょう。事業場の課題に即したものや、無理なく取り組めるものを選んで実施することが大切です。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」の支給対象は、以下の5つすべての条件に当てはまる中小企業の事業主です。
中小企業(事業主)について、業種と出資額・規模の関係は以下の用になっています。この表において、AまたはBの要件を満たす企業が中小企業になります。なお、医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
.png)
【参考】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」
勤務間インターバルに関する助成金が支給されるためには「成果目標」の達成を目指して取組む必要があります。
成果目標は「新規導入」「適用範囲の拡大」「時間延長」があります。前述した4.a~cの助成対象事業者とともに見ていきます。
●勤務間インターバルの新規導入(対象事業主4.aに該当する場合)
所属労働者の半数を超える労働者を対象に、新たに勤務間インターバルを導入すること。
●勤務間インターバル適用範囲の拡大(対象事業主4.bに該当する場合)
勤務間インターバルの対象労働者について範囲を拡大し、所属労働者の半数を超える労働者を対象にすること。
●インターバル時間の延長(対象事業主4.cに該当する場合)
所属労働者の半数を超える労働者を対象として、休息時間数を2時間以上延長して9時間以上とすること。
また、これらの成果目標に加え、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上5%以上または7%以上引き上げることを成果目標に加えることができます。
前述した「助成対象の取組み」とその「成果目標」の達成した状況に応じて、勤務間インターバル導入にかかった経費の一部が助成されます。
また、上限額と助成額は次のようになっています。
・上限額:選択した「成果目標」に設定された助成上限額に、成果目標「賃金の引上げ」の上限額への加算額を合計した金額
・助成額:上限額または対象となる経費の合計額について、補助率3/4(※)を乗じた額のいずれか低い金額が助成されます。
※常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象となる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
▼新規導入に該当するものがある場合
| 休息時間数※1 | 補助率※2 | 1時間あたりの上限額 |
| 9時間以上11時間未満 | 3/4 | 100万円 |
| 11時間以上 | 3/4 | 120万円 |
▼適用範囲の拡大・時間延長のみの場合
| 休息時間数※1 | 補助率※2 | 1時間あたりの上限額 |
| 9時間以上11時間未満 | 3/4 |
50万円 |
| 11時間以上 | 3/4 | 60万円 |
※1: 事業実施計画で指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間数のうち最も短いものを指します。
※2: 常時使用する労働者数が30人以下かつ、「支給対象となる取組」で⑥から⑦を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
▼成果目標が「賃金の引き上げ」の上限額の加算
常時使用する労働者が30人を超える場合、達成した成果目標の助成上限額に対し、以下の上限額が加算されます。
| 引き上げ人数 | 1~3人 | 4~6人 | 7~10人 | 11~30人 |
| 3 %以上引き上げ | 6万円 | 12万円 | 20万円 | 1人あたり2万円
(上限60万円) |
| 5%以上引き上げ | 24万円 | 48万円 | 80万円 | 1人あたり8万円
(上限240万円) |
| 7%以上引き上げ | 36万円 | 72万円 | 120万円 |
1人あたり12万円 (上限360万円)
|
常時使用する労働者数が30人以下の場合は、達成した成果目標の助成上限額に、上記の表の2倍の上限額が加算されます。なお、賃上げ額そのものを助成するものではないため注意しましょう。
【参考】厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」

勤務間インターバル制度を事業場に導入する際に注意すべき点は、以下の3つです。
それぞれの注意点について詳しく解説します。
勤務間インターバル制度のために事業場の労働環境を整える際は、勤怠管理システムの導入などにかかる費用を工面する必要があります。また、新しいシステムの導入後には、メンテナンス費用が継続してかかる場合もあるでしょう。
さらに、制度の導入で従業員一人あたりの労働時間が減ると、増員が必要となりこれまでより人件費がかかることにもなりかねません。制度導入の際には、必要経費を算出して事前に準備しておきましょう。
勤務間インターバル制度を導入したときは、従業員一人あたりの労働時間が減ることも少なくありません。状況によっては業務が時間内に終わらず、自宅に仕事を持ち帰って作業する従業員が出てくる可能性があります。
こうした事態が起こるときは、取り組み内容が事業場の状況に合っていないと考えられます。制度本来の目的を達成するためには、従業員の業務量の見直し・効率化・増員など、自宅でのサービス残業を解消するための工夫が必要です。
勤務間インターバル制度の導入においては、業務の進め方が今までと大幅に変わる可能性があります。従業員にとっては慣れない方法に変更しなければならなくなり、やりにくさを感じる場合もあるでしょう。
事業場全体に制度が定着するには、時間がかかることもあります。しかし、制度導入の目的やメリットを周知徹底し、根気強く従業員の理解を得る努力を続けましょう。

前述した助成金を活用しているかどうかにかかわらず、働き方改革に成功している企業は多く存在します。
勤務間インターバル制度を導入している事業場は複数あり、厚生労働省がその事例集を作成しています。ここではその事例集から3社を取り上げ、具体事例を紹介します。
【参考】厚生労働省「勤務時間インターバル制度導入事例集」
KDDI株式会社では、2015年7月から全社に対して勤務間インターバル制度を導入しています。2015年以前も部分的には同制度を適用していましたが、労働組合から適用範囲拡大の要求があったことで、全社導入に踏み切りました。
導入内容は、管理職以外の社員に対する最低8時間のインターバル確保の義務化です。また、管理職を含む全社員に対しては、健康管理の指標として11時間のインターバル確保を掲げています。
11時間の健康管理指標を掲げたことで、社内でそれまで見えていなかった過重労働が明らかになりました。さらに、インターバルを意識することで健康リスクの回避ができるようになってきたことも、制度導入による効果の一つです。
TBCグループ株式会社では、2017年の1月より勤務間インターバル制度を導入しています。導入の背景には、エステティック業界の労働時間管理について、会社として意識を高めていきたいとの考えがありました。
労務管理が行き届いた働きやすい職場であるとアピールし、今後の人材確保につなげたかったことも、制度を導入した理由の一つです。
導入内容としては、グループ企業を含む全社員に対し、9時間のインターバルを義務化したことが挙げられます。また、健康管理指標として11時間(月11日以上)のインターバルを規定し、時間管理システムの電子化にも取り組みました。
効果として、時間管理の電子化を整えた店舗では、時間外労働の申請が楽になったという声がありました。さらに、スタッフの時間管理意識が高まってきていることもポイントです。
ユニ・チャーム株式会社では、2017年の1月より勤務間インターバル制度を導入しています。
導入理由は、働き方の改革と人事制度の改定を2018年度に実施予定であったことです。また背景には、育児や介護などで制約のある人たちも活躍できる制度を整えたいという考えがありました。
導入内容は、全社員に対し最低8時間以上、努力義務で10時間以上のインターバルの規定です。従業員一人ひとりがいきいきと健康に働ける環境を整え、事業場の生産性を上げることを最終目標としています。

勤務間インターバル制度は、従業員の休息時間を十分に確保するための取り組みです。導入することで、従業員の心身の健康維持や離職率の低下、企業イメージの向上などが期待できます。
制度を適切に運用するためには事業場の現状を正しく理解し、実態に即した取り組み目標の設定が大切です。
事業場を対象とした助成金もうまく活用し、勤務間インターバル制度を導入して業務効率や生産性の向上を目指しましょう。
産業医をはじめて選任する場合、産業医についての知識や担当業務、探し方や選任手続きについて、何をどうすればいいのかわからない担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本資料は保健師監修のもと作成した、産業医をはじめて選任する企業担当者様向けの資料になります。「産業医選任の基本的な知識について確認したい」、「産業医の探し方や選任手続きの流れについて知っておきたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
本資料は、自社の産業保健にかかっているコストを見直せるチェックリストです。 チェック項目が多いほど、産業保健のコストを見直す余地があります。ぜひご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け