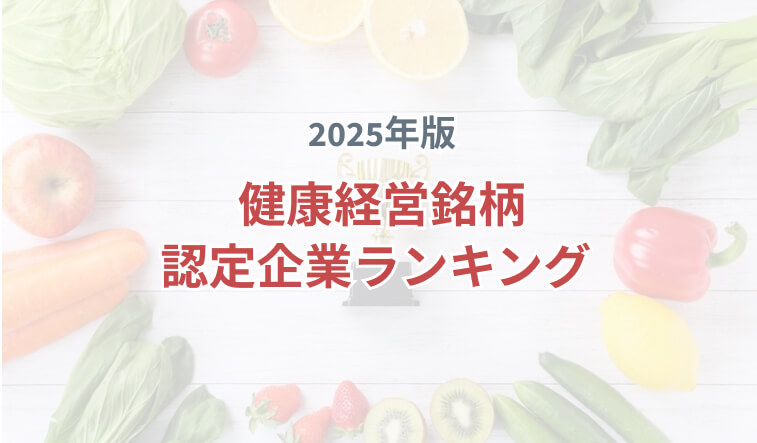「健康経営」という言葉が一般化し、多くの企業で健康経営への関心が高まっています。しかし、「健康経営を推進しても、具体的な成果が見えにくい」「従業員の健康意識がなかなか向上しない」といった悩みを抱える人事労務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。本記事では、経済産業省と東京証券取引所が共同で選定する「健康経営銘柄2025」の企業事例から、企業価値向上に繋がる健康経営の具体的な取り組みとその効果を深掘りします。先進企業の成功事例から、貴社の健康経営をさらに一歩前進させるヒントを見つけましょう。
健康経営銘柄とは?その重要性と選定プロセス
健康経営とは、従業員の健康管理を経営的な視点から捉え、戦略的に実践することです。経済産業省と東京証券取引所は、「国民の健康寿命の延伸」への取り組みの一環として、東京証券取引所に上場している企業の中から特に健康経営に優れた企業を「健康経営銘柄」として選定しています。これは、長期的な企業価値向上を重視する投資家に対し、魅力的な投資対象として紹介することを通じて、企業における健康経営の促進を目指すものです。
「健康経営銘柄2025」の選定プロセスは、以下のステップで行われました:
- 「令和6年度健康経営度調査」に回答した東京証券取引所上場会社を選出
- 回答企業を評価基準に基づいて評価し、健康経営優良法人(大規模法人部門)に申請している法人のうち上位500位以内、かつ選定要件を満たす企業を「健康経営」に優れた企業(選定候補)として選出
- 選定候補企業について、ROE(自己資本利益率)に基づくスクリーニングや加点を行い、前年度の調査への回答有無、社外への情報開示、投資家との対話状況等も評価し、業種内で最高順位の企業、および全産業最高順位企業の平均より優れている企業を「健康経営銘柄2025」として選定
この取り組みは、従業員の活力や生産性の向上といった組織の活性化をもたらし、結果的に業績や企業価値の向上、さらには株価向上にも繋がると期待されています。
認定回数別に見る、健康経営を継続する企業と成果
「健康経営銘柄2025」には、複数回にわたり認定されている企業が多数存在します。これは、単発の取り組みに終わらず、継続的に健康経営を推進し、その効果を測定・改善していることの証と言えるでしょう。特に認定回数の多い企業からは、長期的な視点での健康経営の秘訣が見えてきます。
11回認定企業
- SCSK株式会社(情報・通信業): 2012年の取り組み開始以来、残業時間は大幅に低減し、年次有給休暇の100%取得も当然のこととなっています。社員満足度は取り組み前に比べ80%から89%に向上しており、この間、会社の業績は増収増益を継続しています。健康経営を通じて「全社員で組織的に取り組む」という組織風土も培われ、健康と仕事のパフォーマンスとの関係性についてポジティブに実感できる社員が73%から91%へと向上しています。
10回認定企業
- 花王株式会社(化学): 年間を通じて様々な健康支援を行い、心身のケアに取り組むことで、活き活きと働く社員は78.8%に達しています。健康イベントを拡大し、多くの社員や家族に参加を促すことで、健康づくりに自発的に取り組む風土がより醸成されており、健康づくりがワークエンゲイジメントや生産性の向上に繋がるという社内調査結果も出ています。
- TOTO株式会社(ガラス・土石製品): 毎年、健診結果傾向をふまえた健康増進活動を推進し、フィジカル・メンタルでの休業者数は年々減少、有所見率も低水準を維持しています。健康増進イベントへの参加者増加やPHRサービスの登録者増加など、社員一人ひとりが健康に向き合う風土が拡がったと感じられています。長時間労働は減少、有給休暇の取得率もアップしており、社員一人ひとりが健康でイキイキと働くことが、生産性や業績の向上に寄与すると考えられています。
- 株式会社大和証券グループ本社(証券、商品先物取引業): 健康上の理由による個人の生産性低下を示すプレゼンティーイズム損失割合は、2018年度の19.7%から2023年度には13.9%と、過去5年間で5.8ポイント縮小しています。アプリを活用した健康増進イベントには多くの社員が参加しており、「みんなで超えよう!障害物競走」のようなチーム戦イベントは、全国の事業所でコミュニケーション活性化と連帯感強化に繋がっています。
8回認定企業
- 株式会社丸井グループ(小売業): 専属産業医が取締役となり、健康の視点を経営に活用しています。10年以上にわたる「手挙げの文化」に基づく取り組みにより、人の意思を尊重する風土が浸透し、「職場で尊重されている」人の割合は2012年の28%から2024年には69%へ(41ポイント向上)、「強みを活かして挑戦できている」人の割合は2012年の38%から2024年には58%へ(20ポイント向上)と、社員の意識が大きく変化しています。
7回認定企業
- 株式会社KSK(情報・通信業): エンゲイジメントサーベイは過去10年間で12.3%改善、社員のヘルスリテラシーは3.65(2021年)から3.77(2024年)に向上し、生産性向上、組織活性化に繋がっています。採用活動においても「喫煙者ゼロ」等の「健康経営」は強い訴求力を持ち、新卒採用目標達成100%の原動力となっています。「わくわく健康プラン」には65%の社員が参加し、社員発案のスポーツサークルも生まれるなど、コミュニケーションが活性化されています。
2025年選定企業に見る、健康経営の多様なアプローチと成果
従業員の健康意識向上と行動変容
- 石油資源開発株式会社(鉱業)では、社内でのラジオ体操の毎日実施や2017年から始まった「ダイエットキャンペーン」を通じて、年々参加者が増え、健康意識が高まっていることを実感しています。
- 株式会社ヤクルト本社(食料品)では、身近な健康増進として「階段の使用」「血圧計の利用」や、社員食堂でヘルシーメニューを選択する従業員の増加など「健康」に関する行動変容が見られています。男性育児休業取得の促進にも継続して注力し、取得率95%(平均取得日数:28日)を達成しています。
- アース製薬株式会社(化学)は、喫煙率が取り組み初年度の2018年27.9%から2024年には18.8%に減少しています。全社員の健診結果の確認や敷地内禁煙の導入により、会社の本気度が伝わり、健康セミナーへの積極的な参加や健康相談窓口の活用が増加し、セルフケア行動の実践に繋がっています。
- TOYO TIRE株式会社(ゴム製品)は、2024年に全社禁煙を達成しました。段階的に進めたことで禁煙文化が定着し、猛暑時の通勤時負担軽減・熱中症防止のため100%在宅勤務を推奨し、その後、恒常的な制度として採用されています。
- 大阪ガス株式会社(電気・ガス業)は、体重・食事・運動・飲酒・禁煙・睡眠・ストレスの7項目について、「Daigasグループ行動指針“ヘルシー7”」に基づいた健康推進活動を展開し、健診で医療が必要と判定される従業員の割合が減少しています。年2回開催のウォーキングイベント参加者は年々増加し、今では5,500名を超え、個々のモチベーション向上や職場のコミュニケーション活性化に繋がっています。
職場の活性化とエンゲージメント向上
- 日本国土開発株式会社(建設業)では、従業員一人ひとりが健康を意識し、自ら改善に取り組む文化が根付いており、今年は従業員主体型の活動もスタートし、ストレスチェックや健康に関する研修も高い受検率・受講率を誇っています。
- 株式会社ニチレイ(食料品)は、従業員の特性や業務上のニーズに応じた社内セミナー「ニチレイ健康塾」を展開し、健康への関心が高まるにつれ、社内の雰囲気も明るくなり、業務効率化や生産性向上に良い影響が出ています。
- コクヨ株式会社(その他製品)は、リモートワークと出社の選択制導入、部門を超えた人間関係づくりイベント開催、1on1の型や仕組みの整備などにより、3年間でエンゲージメントスコアが4ポイント上昇し、業務負荷やストレス反応の項目も7ポイント改善されました。
- KDDI株式会社(情報・通信業)は、社内カウンセラーによる年2回の全社員面談を実施し、社員個々の心身の健康支援に加え、職場の人間関係改善にも繋がっています。毎年秋に実施するスポーツフェスティバル(運動会)も役員をはじめ社員やご家族まで多くが参加し、コミュニケーション活性化に貢献しています。
- ANAホールディングス株式会社(空運業)では、各部署のウェルネスリーダーや健康推進担当者の募集が進み、社員から睡眠・運動不足・食事に関する質問が増加。会社が発信する情報やイベントが社員同士の活発なコミュニケーションに繋がり、パフォーマンス向上にも貢献しています。
特定課題へのアプローチ
- ニッポン高度紙工業株式会社(パルプ・紙)では、各種活動がストレスチェックの高ストレス者率の改善(2021年度14.8%→2024年度9.7%)につながり、男性育児休業取得率は2023年度以降100%を継続しています。
- カシオ計算機株式会社(電気機器)は、2024年に「女性の健康施策」を重点テーマとして女性特有の健康課題を学ぶセミナーを開催。男性の育児休業取得も推奨し、2030年までに取得率100%を目指しています(最近のデータでは63%で、取得者の70%が1ヶ月以上連続で取得、平均39日)。
- 株式会社群馬銀行(銀行業)は、女性の健康課題の理解促進やプレコンセプションケア、不妊治療への支援がエンゲージメント向上と女性管理職比率向上に寄与。男性育休の長期化や家事育児参加が進み、ワークライフバランスの向上と女性の活躍に繋がっています。
健康経営と企業価値向上の相関性
多くの選定企業が、健康経営の推進が労働生産性の向上、企業ブランド価値の向上、採用活動における訴求力の強化、そして最終的な企業価値の向上に繋がると実感しています。例えば、伊藤忠商事株式会社は、独自の取り組みにより、労働生産性が2023年度には2010年度比で「5.2倍」に向上したと報告しています。また、株式会社三機サービスは、健康経営への取り組みが社員満足度・定着率・採用力の向上に繋がり、新卒採用数が約3倍に増加し、2024年本決算では過去最高の売上高を記録しました。
経営層のコミットメントの重要性
健康経営の推進において、経営層のコミットメントは極めて重要です。健康経営銘柄に選定された企業では、約8割が取締役会で健康経営の取り組み効果や経営上の課題に対する効果を議題として議論しており、これは銘柄選定外の企業と比較して高い比率を示しています。経営トップ自らが健康経営に取り組む姿勢を示すことで、従業員の健康意識が高まり、組織全体の活性化に繋がることが示されています。
まとめ
健康経営は、単なる福利厚生の拡充に留まらず、企業の持続的な成長と競争力強化に不可欠な経営戦略として位置づけられています。今回ご紹介した健康経営銘柄2025選定企業の事例は、従業員の心身の健康が企業全体のパフォーマンス向上に直結することを明確に示しています。特に複数回認定を受けている企業の継続的な取り組みは、その効果と重要性を強く裏付けています。貴社でも、これらの事例を参考に、従業員の健康を経営の基盤と捉え、戦略的な健康経営を推進してみてはいかがでしょうか。