

会社としてうつ病の従業員をサポートしたいけれど、困難に感じている職場もあるかと思います。
うつ病は、真面目で責任感が強い人ほどなりやすいともいわれています。しかし、うつ病を抱える従業員のケアをしながら業務を行っている場合では、職場の人間関係や同僚の不調に心を痛め、周囲の人物も疲弊してしまうことがあります。
本記事では、従業員のうつ病発生と同僚のケアなどについて具体的な方法について解説します。
目次
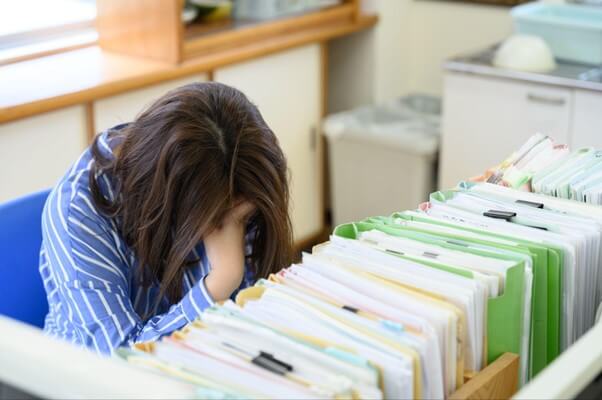
うつ病の従業員は、心配や励ましを素直に受け取ることが難しい状態にあります。
そのため、周囲の同僚が「力になりたい」と思ってかけた言葉や協力・行動は、本人には響かないばかりか、かえって負担になってしまうことさえあるのです。
この、「良かれと思ってしたことが、全く役に立たない」という周囲の経験が、無力感や喪失感につながってしまう可能性があります。
一生懸命に支えようと努力しているのに、その努力が報われないと感じることが、同僚が消耗感を感じる原因になります。
うつ病の従業員が業務を十分にこなせない場合、そのしわ寄せは同僚等に回ってくることが考えられます。
周囲の人間としては、本来の自分の業務に加えて、うつ病の従業員の業務を請け負うことになり、場合によっては残業が増えるような場合もあるでしょう。
こうした時に不公平感が募り、不満や疲労へと変わっていきます。同僚に対する冷たい感情ではありません。誰もが感じ得る自然な感情です。
つまり、気を遣うことや業務量の増加が、周囲の同僚が疲労感を感じる要因になっているといえます。

うつ病の従業員に対しては、まずプライバシーを最大限に尊重した上で、以下の対応を検討しましょう。
遅刻や早退、欠勤といった勤怠の乱れ、業務におけるミスの増加、表情の変化など、日頃から不調のサインを察知できるよう努めましょう。
不調や異変に気づいたら、相談の対応や産業医など専門スタッフへの橋渡しを行います。
診断書が提出されたら、速やかに休職制度の内容(期間、給与、復職の流れなど)を説明します。
従業員が手続きで不安を感じないよう、人事担当者が寄り添う姿勢を見せることが大切です。
本人の同意なく、病状や休職の理由を他の従業員に伝えることは絶対に避けなければなりません。
また、うつ病の要因についてなど、知っていたとしても口外しないことです。
周囲には「〇〇さんはしばらくお休みをいただきます」など、事実のみを伝えるに留め、憶測や噂が広まらないよう配慮しましょう。
うつ病の従業員の周囲で働く人々の疲弊にも、人事として配慮が必要です。
休職中の従業員の業務を割り振る際も注意が必要です。業務が特定の従業員のみに集中することは、不公平感や疲労が生じるおそれがあるからです。
よって、部門長などと協力し、チーム全体で業務を公平に分担できるよう調整しましょう。そのためには、業務マニュアルの整備や、チーム全員でフォローし合う体制を構築することも有効です。
うつ病の同僚のサポートに疲れた従業員のために、産業医や社内相談窓口、外部のEAP(従業員支援プログラム)といった相談窓口の存在を積極的に周知します。
特に「周りの人」の疲労に特化した相談内容にも応じられる体制を整えましょう。
また、チーム内で率直な意見交換ができるよう、定期的なミーティングの機会を設けることも効果的です。「チームとしてどう協力すれば良いか」をオープンに話し合うことで、特定の個人に責任が集中するのを防ぐことに期待ができます。

産業医は、うつ病に対する正しい知識を従業員に提供する上で、専門家として頼りになる存在です。メンタルヘルスに関する職場のリテラシー向上や面談・相談を通じて、従業員のケアを行いましょう。
研修についてですが、うつ病は誰でもかかりうる病気であることを理解してもらうためにも重要です。
主なテーマとしては、うつ病の症状、早期発見のサイン、セルフケアなどを扱います。これにより、うつ病に関して自らが早期気づくことや自己でケアすることで悪化を防ぐ効果に期待できます。
また、ラインケアの観点から管理職向けの研修も大切です。管理職は部下のメンタルヘルスを把握し、初期対応を担う重要な役割があるからです。
研修では産業医から、部下への適切な声かけの方法、休職・復職時の対応、そして相談窓口へのつなぎ方について具体的に学びます。
・
・
・
うつ病の従業員を職場で支えることは細心の注意が必要です。また、周囲の同僚などが疲弊してしまわないよう、人事として対応しましょう。
業務の公平な再分配や、産業医・相談窓口の活用を積極的に進め、会社全体で無理なく支え合える体制を築き、健康的に働ける職場を目指してみてください。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け