

産休育休制度とは、従業員が出産や育児のために取得できる法定休暇です。従業員が産休育休制度の利用を希望した場合、事業者は速やかに手続きを行う必要があります。
しかし、いざ従業員から産休・育休制度の利用について申し出があった場合、どのように対応すればいいのか悩んでしまうケースも少なくありません。申し出があった際にきちんと対処できるよう、行うべき手続きについて理解しておくことが肝心です。
本記事では、産休育休制度が適用される従業員の条件や会社が行うべき手続きを解説します。
目次
 産休育休制度とは、出産や育児のために仕事を一時的に休業できる制度です。正確には、産前・産後休業と育児休業の2つの制度を指します。
産休育休制度とは、出産や育児のために仕事を一時的に休業できる制度です。正確には、産前・産後休業と育児休業の2つの制度を指します。
産前・産後休業と育児休業は、労働基準法と育児・介護休業法によって定められている法定休暇です。したがって、従業員が取得を希望した場合、原則として会社は拒否できません。
 産前・産後休業、育児休業を取得できる期間は、それぞれ以下のとおりです。
産前・産後休業、育児休業を取得できる期間は、それぞれ以下のとおりです。
・産前休業:出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)から出産当日まで
・産後休業:出産日の翌日から8週間まで
・育児休業:産後休業満了日の翌日から子どもが1歳になるまで
産前休業の取得は従業員の任意であるため、出産予定日の6週間前(多胎の場合は14週間前)からであれば、従業員自ら自由に休業開始日を決められます。
一方、産後休業は、労働基準法で「出産の翌日から8週間は就業させてはならない」と定められているため、従業員の希望の有無にかかわらず取得させる必要があります。
ただし、産後「6週間」が経過しており、かつ出産した本人が就業を希望している場合は、医師の許諾を得れば就業が可能です。
育児休業は、子どもが保育施設に入所できないなどで就業不可能な場合に、最長子どもが2歳になるまで延長できます。
また、育児・介護休業法の改正により、2022年10月1日からは男女ともに2回にわけて取得できるようになりました。
【参考】
厚生労働省 働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート「産前・産後の休業について」
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
厚生労働省「令和3(2021)年法改正のポイント」
 産前・産後休業と育児休業では、取得できる従業員の条件が異なります。それぞれの制度の取得条件を解説します。
産前・産後休業と育児休業では、取得できる従業員の条件が異なります。それぞれの制度の取得条件を解説します。
【参考】厚生労働省 都道府県労働局「働きながらお母さんになるあなたへ」
産前・産後休業を取得できるのは、出産する女性従業員です。雇用形態・期間に関係なくすべての女性従業員が取得できます。
なお、産後休業は、妊娠4ヶ月以上での分娩で取得でき、死産や流産も対象になります。
育児休業は、1歳未満の子どもをもつ従業員であれば男性も女性も取得できます。女性は産後休業満了日の翌日から、男性は出産予定日から取得が可能です。
子どもが1歳以降の育児休業については、保育施設に入所できないなど就業不可能な事情がある場合に取得できます。
 産休育休制度は、パートやアルバイトなどの非正規雇用の従業員でも利用できます。
産休育休制度は、パートやアルバイトなどの非正規雇用の従業員でも利用できます。
ただし、育児休業においては、「子どもが1歳6ヶ月を迎えるまでに雇用契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない」ことが条件です。
子どもが1歳6ヶ月になるより以前に雇用関係が終了することが決まっている、または書面や口頭で契約を更新しない旨が明示されている場合は、育休を取得できません。
非正規雇用の従業員から育児休業の申し出があった場合は、定められた条件に該当するか、よく確認しましょう。
【参考】厚生労働省「有期雇用労働者の育児休業や介護休業について」
 産休・育休は有給休暇ではないため、会社は休業期間中における給料の支払い義務はありません。産休・育休期間中を有給とするか無給とするかは、会社が決められます。
産休・育休は有給休暇ではないため、会社は休業期間中における給料の支払い義務はありません。産休・育休期間中を有給とするか無給とするかは、会社が決められます。
ただし、産休・育休期間中に給料を支払わない場合は、従業員が経済的に困窮することになるため、出産手当金や育児休業給付金について十分に説明する必要があります。
出産手当金と育児休業給付金の支給期間、受給できる金額の目安は以下のとおりです。
| 給付金の種類 | 支給期間 | 支給金額 |
| 出産手当金 | 出産予定日の42日前(多胎の場合は98日前)から出産日翌日の56日目まで | 1日につき給料の3分の2に相当する金額 |
| 育児休業給付金 | 育児休業の開始日から最長子どもが2歳になる日の前日まで | 育児休業開始から6ヶ月までは休業前の給料の67%、6ヶ月以降は50%に相当する金額 |
出産手当金は健康保険、育児休業給付金は雇用保険への加入が必要です。
他にも複数の支給条件があるため、従業員からこれらの給付金について申請があったら、加入状況をよく確認したうえで制度を利用できるかどうかしっかりと説明しましょう。
【参考】
全国健康保険協会「出産手当金」
厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き」
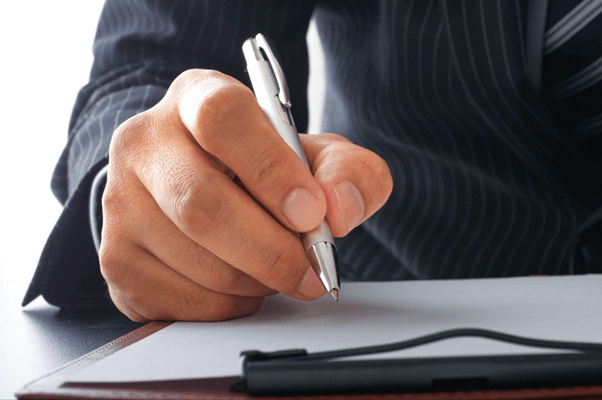 従業員が産休育休制度を利用する際に企業が行う手続きを、以下の4つに分けて解説します。
従業員が産休育休制度を利用する際に企業が行う手続きを、以下の4つに分けて解説します。
・従業員が産前・産後休業に入るときに行う手続き
・従業員が出産したときに行う手続き
・従業員が育児休業に入るときに行う手続き
・育児休業が終了するときに行う手続き
従業員が出産や育児に専念できるよう、それぞれの内容を理解してスムーズに手続きを進めましょう。
従業員が産前休業に入る際は、出産手当金の申請手続きを行う必要があります。出産手当金の申請手続きは、会社と従業員のどちらが行っても問題ありませんが、会社側が行うことが一般的です。
会社が手続きを行う場合は、出産手当金支給申請書に必要な証明書類などを添えて、加入している健康保険組合に提出します。
従業員が申請する場合、休業期間や賃金についての事業主の証明が必要になるため、従業員から申し出があった際は速やかに対応しましょう。
また、産休の取得期間中は、従業員と会社双方の社会保険料が免除されます。産前・産後休業取得者申出書に必要事項を記入して、会社の所在地を管轄する年金事務所に提出しましょう。
社会保険料の免除の申請は、産前産後休業期間中または産前産後休業の終了日から起算して1ヶ月以内に行う必要があります。
【参考】
全国健康保険協会「出産手当金」
日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
従業員が子どもを出産したら、まず育児休業の取得希望について聞くのが基本です。従業員が取得を希望した場合は、育児休業の開始予定日・終了予定日を明確にしたうえで、従業員に育児休業申出書を提出してもらいましょう。
企業は従業員に対し、育児休業取扱通知書を交付します。なお、通知書には育児休業中の待遇や休業後の賃金、労働条件などを記載する必要があります。
また、産後休業の満了予定日前に休業を終了する場合は、社会保険料の免除を解消する手続きも必要です。産前・産後休業の終了届を作成し、管轄の年金事務所に提出しましょう。
【参考】日本年金機構「従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き」
従業員が育児休業に入る際、事業者は以下の手続きを行う必要があります。
・育児休業中の社会保険料免除
・育児休業給付金の受給資格確認
育児休業中も従業員・会社双方の社会保険料は免除されます。育児休業等取得者申出書を作成して管轄の年金事務所に提出しましょう。
育児休業給付金は、育児休業の期間中、一定以上の給与が支払われないケースにおいて、雇用保険から給付金が支給されます。事業者は従業員の受給資格確認のために、以下の書類を管轄のハローワークに提出する必要があります。
・当該従業員の休業開始時の月額賃金証明書
・育児休業給付受給資格確認票
・育児休業の取得期間と賃金の支払い状況が分かる証明書
・出産の事実が分かる証明書
受給資格の確認後は、受給資格確認通知書と育児休業給付金支給申請書が交付されます。所定の手順に従って育児休業給付金の手続きを進めましょう。
【参考】日本年金機構「育児休業等を取得し、保険料の免除を受けようとするとき」
育児休業の終了時は、以下の3つの手続きが必要です。
・育児休暇終了届の提出
・社会保険料の変更手続き
・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出
従業員が育児休業を終了予定日よりも早く切り上げる場合は、日本年金機構に対し、育児休業の終了届を提出しなければなりません。
また、育児休業から復帰して3ヶ月経過したら、管轄の年金事務所に「社会保険料の報酬月額変更届」を出します。この手続きにより、育児休業終了後の平均給与額にもとづいて社会保険料が改定されます。
また、短時間勤務などによって、従業員が将来受け取る年金額が減少しないよう、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」の提出もあわせて行いましょう。
 従業員が産休・育休を終了する際、会社は以下の対応をとる必要があります。
従業員が産休・育休を終了する際、会社は以下の対応をとる必要があります。
・職場復帰後の仕事内容の調整や変更
・子育てに関する法的な配慮
それぞれの内容について詳しく解説します。
産休・育休の終了後は、従業員が育児の時間を確保できるよう、仕事内容の調整や変更を行いましょう。
育児休業を取得した従業員の職場復帰後の待遇については、育児・介護休業法により「原職または原職相当職に復帰させる」ことが原則とされています。
しかし、なかには企業側の勝手な判断で、本人が望まない業務内容で復職させるケースもみられます。
従業員本人が希望していないにもかかわらず、業務内容を変更すると従業員から不満が出たり、トラブルに発展したりする可能性もあるため注意が必要です。また、職場復帰後に従業員に大きな負担がかかる配置転換もしてはなりません。
育児休業を取得した従業員が職場に復帰する際は、今後の仕事内容についてあらかじめ従業員とよく話し合っておくことが大切です。現状の業務について説明する人を決めておくなど、職場全体でフォローする工夫も必要です。
復帰後は無理なく仕事と育児の両立ができているか、業務で困ったことはないかなど、定期的に面談を行うとよいでしょう。
【参考】厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
事業者は、従業員が産休・育休から復職した後も、育児・介護休業法に則り、多方面から従業員に対して配慮しなければなりません。
具体的には、以下などの制度を利用できるよう、従業員に周知する必要があります。
・短時間勤務制度
・子の看護休暇
短時間勤務制度は、子どもの養育のため「原則として1日6時間」の短時間勤務ができる制度です。
子の看護休暇は、病気や怪我をした子どもの看護などのために、子ども一人につき年に5日間の休暇を取得できます。このような制度を知らず、従業員からの申し出を断ってしまい、トラブルになるケースもあるため要注意です。
育児・介護休業法について理解を深め、従業員に対してどのような法的配慮を行うべきなのか、把握しておきましょう。
【関連記事】【2025年4月施行】改正育児・介護休業法の内容とは?企業が実施すべき対応を解説
 従業員が産休育休制度の利用を希望した際には、スムーズに手続きを進めることで、従業員が安心して出産・育児に臨めるようになります。
従業員が産休育休制度の利用を希望した際には、スムーズに手続きを進めることで、従業員が安心して出産・育児に臨めるようになります。
しかし、産前・産後休業と育児休業では、取得できる従業員の条件や期間が異なるため注意が必要です。
また、産休・育休を取得した従業員が職場復帰後に育児の時間を確保できるよう、配慮することも大切です。
産休育休制度の適用条件や手続きを理解して、従業員の育児と仕事の両立を支援しましょう。
従業員相談の一次窓口として、産業医と貴社産業保健スタッフを連携しやすくする外部相談窓口サービスの資料です。 下記のようなお困りごとがあれば、ぜひ一度ご覧ください。 ・メンタル・フィジカル不調者が複数いる ・契約中の相談窓口の費用対効果が低い ・何かあった時の相談窓口を持っておきたい
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け