
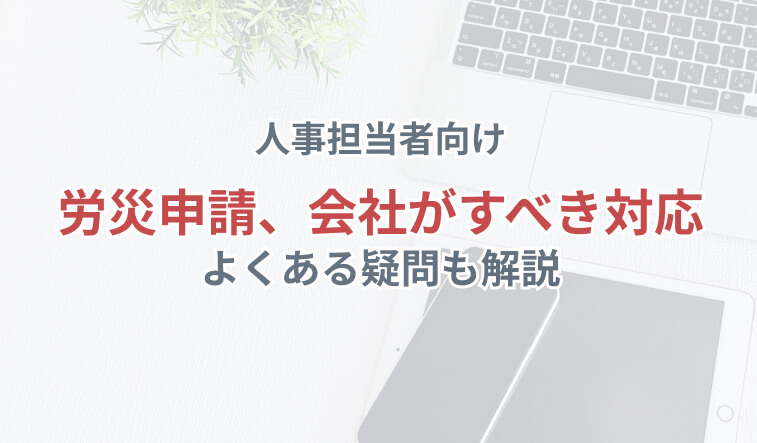
従業員が労災に遭ったとき、「会社としてどう対応すればいいのだろう」と悩む人事担当者の方は多いのではないでしょうか。労災申請は、会社が適切に対応しなければ、従業員とのトラブルに発展したり、法的リスクを負ったりする可能性があります。
この記事では、労災申請における会社の役割と、具体的な対応方法を詳しく解説します。労災の基本から、申請手続き、会社が拒否することのリスクまで、人事担当者が知っておくべきポイントを網羅的にご紹介します。
目次
労災申請は、従業員本人だけでなく、会社も手続きを行うことができます。しかし、会社には労災申請を代行する法的な義務があるわけではありません。労災保険は、従業員が請求して初めて給付される「請求主義」が原則です。
ただし、労働基準監督署からの調査に協力したり、従業員の手続きをサポートしたりすることは、事業主として当然の責務であり、誠実な対応が求められます。
会社が労災申請に協力しなかったり、申請を妨害したりすることは、労災保険法違反となり、労働基準監督署から是正勧告を受ける可能性があります。
さらに悪質な場合は、50万円以下の罰金に処せられることもあります。従業員との信頼関係を損なうだけでなく、社会的信用も失うリスクがあるため、労災申請の申し出があった場合は、誠実に対応することが重要です。
ここでは、従業員が労災申請を希望した場合の、会社が取るべき具体的な対応を5つのステップで解説します。
まずは、事故や病気の原因が業務上、または通勤途上であるか事実確認を行います。このとき、従業員から状況を詳しくヒアリングし、証拠となる写真や診断書などを集めます。特に重要なのは、以下の3つの要素を正確に把握することです。
労災申請には、複数の書類が必要となります。従業員が準備する書類と、会社が準備する書類を明確にし、従業員に提出を促します。
従業員が用意するもの:
会社が用意するもの:
労災の種類(療養、休業、障害など)に応じて、会社が記入する申請書(様式第5号や様式第8号など)を作成します。様式は厚生労働省のホームページからダウンロード可能です。書類の記入には、以下の点に注意してください。
準備した書類を、会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ提出します。郵送または持参して提出するのが一般的です。
申請後も、労働基準監督署から追加で資料の提出を求められることがあります。スムーズに対応できるよう、従業員と連携を取りながら準備を進めます。また、労災認定後の休職や復職に関する手続き、職場復帰支援プログラムの提供など、従業員への継続的なサポートも重要です。
退職後でも、在職中の災害が原因であれば労災申請は可能です。会社は、在職中と同様に手続きに協力する義務があります。退職しているからといって、手続きを拒否することはできません。
精神疾患による労災は、業務との因果関係の証明が難しいケースが多いです。専門家と連携しながら、従業員が精神的な負担を抱えることなく申請できるように配慮することが求められます。
具体的な対応策:
労災申請によって、労働保険料が上がるなどの直接的なデメリットはありません。しかし、重大な労災事故が発生した場合は、企業として安全配慮義務違反を問われる可能性があり、労働基準監督署から是正勧告を受けることもあります。
労災申請は、単なる手続きではなく、従業員との信頼関係を築くための重要なプロセスです。以下の点に注意し、会社を守るための対策を講じましょう。
労災発生後、従業員が不安を感じている場合があります。状況のヒアリングだけでなく、今後の手続きの流れや会社のサポート体制について丁寧に説明し、安心感を与えましょう。
労働基準監督署への提出書類は、事実に基づいた正確な情報を記載する必要があります。虚偽の申請は、会社の信用を失うだけでなく、法的な罰則の対象となる可能性もあります。
労災事故が起きた場合、再発防止策を講じることは会社の義務です。従業員へのヒアリングや現場の状況を確認し、職場環境の改善に努めましょう。
労災申請に適切に対応することは、従業員を守るだけでなく、会社の信頼を守ることにもつながります。この記事で解説した内容を参考に、適切な労災対応を進めていきましょう。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け