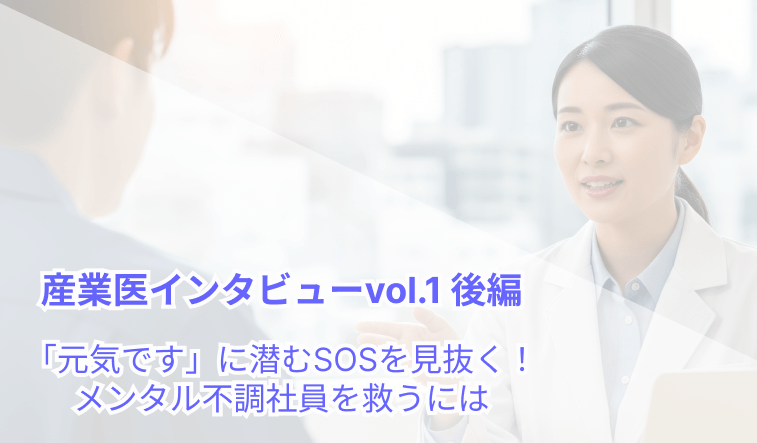

従業員のメンタルヘルス不調は、休職や離職につながるだけでなく、組織全体の生産性にも影響を及ぼす重要な課題です。実際に、メンタルヘルス不調により1か月以上休業または退職した従業員がいる事業所は1割にのぼります。
不調の深刻化を防ぐためには、管理職や人事労務担当者が初期のサインにいち早く気づき、適切に対応することが求められます。この記事では、職場で観察できるメンタル不調のサインを「行動面」「精神面」「身体面」に分けて詳細に解説します。あわせて、不調者への対応方法や、従業員が安心して働ける職場をつくるための予防策についても紹介します。
目次
メンタルヘルスの不調は、精神面だけでなく、身体や行動にも変化として現れます。これらのサインは、うつ病や適応障害といった精神疾患の前兆である可能性もあり、早期発見が重要です。職場で気づきやすいサインを3つの側面に分けて解説します。
勤怠状況や業務遂行能力など、客観的に観察しやすく、周囲が最も気づきやすい変化です。
本人の言動や態度からうかがえる内面的な変化です。行動面の変化と合わせて観察することが大切です。
本人が訴える体調の変化や、周囲から見てもわかる症状です。原因不明の体調不良が続く場合は注意が必要です。
部下や同僚の不調のサインに気づいたら、深刻化を防ぐために迅速かつ慎重な初期対応が重要です。
まず、他の従業員のいない静かな環境で、1対1で話を聞く機会を設けることが第一歩です。目的は相手を評価したり、問題を解決したりすることではなく、本人の話に真摯に耳を傾け、気持ちを受け止めることです。
意見を押し付けたり、安易に「頑張れ」と励ましたりすることは避けましょう。心配しているという姿勢を伝え、本人が安心して話せる雰囲気を作ることが求められます。
人事労務担当者だけで問題を抱え込まず、産業医や社外の相談窓口(EAP)など、専門家のサポートにつなげることが重要です。産業医面談は、従業員の健康状態を専門的な視点から評価し、就業上の措置について助言を得るための重要な機会です。
相談を促す際は、相談内容のプライバシーは厳守されることを伝え、本人が安心して専門家につながれるよう配慮します。
本人の状態やストレスの原因に応じて、一時的な業務負荷の軽減、残業の制限、配置転換など、ストレス要因を減らすための環境調整を検討します。これは、労働安全衛生法で定められた事業者の「安全配慮義務」にも関わる重要な対応です。産業医の意見も参考にしながら、本人と話し合い、最適な措置を講じることが望まれます。
個別の対応だけでなく、組織全体でメンタル不調を予防する取り組みが不可欠です。
メンタル不調は特別なことではなく、誰にでも起こりうるものです。従業員一人ひとりの変化に関心を持ち、組織として支える体制を構築することが、企業の持続的な成長と発展につながります。
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めており、職場におけるメンタルヘルスケアを推進しています。 この指針では、メンタルヘルス対策には4つのケアがあると定義されています。 本資料では、この4つのケアを軸とし、弊社が推奨する取組事項をまとめ、チェックリストにしています。 「セルフケアに関する取り組みが足りていない」「事業場外資源によるケアを行えていない」等、各領域の取り組み状況の確認にご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け