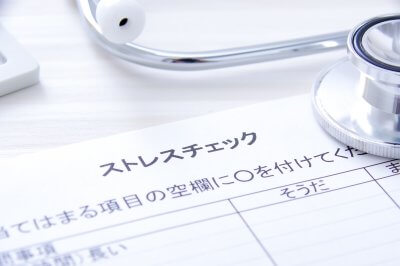
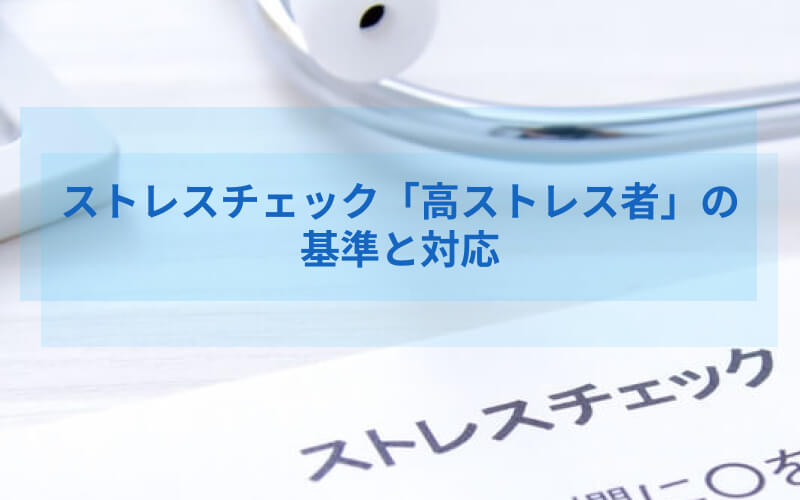
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルス不調を未然に防ぎ、快適な職場環境を築く上で欠かせない制度です。特に、ストレスチェックの結果から「高ストレス者」と判定された従業員への適切な対応は、企業が従業員の安全と健康を守る上で極めて重要となります。
しかし、「高ストレス者」の具体的な基準や、その後の対応について、「これで本当に合っているのか?」「他にやるべきことはないか?」と疑問や不安を感じている人事労務担当者の方も多いのではないでしょうか。
本記事では、企業の人事労務担当者様に向けて、ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準から、面接指導の勧奨、そしてその後の具体的な対応フロー、さらには個人情報保護における注意点まで、実践的な情報を分かりやすく解説します。
目次
ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された労働安全衛生法に基づく制度です。従業員の心理的な負担の程度を把握するための検査であり、ストレスの高い状態にある従業員を早期に発見し、面接指導によってセルフケアや職場環境改善につなげることを目的としています。
この制度において特に重要なのが、「高ストレス者」への対応です。高ストレス者とは、ストレスチェックの結果、心身のストレスが非常に高いと判断された従業員のことであり、放置するとメンタルヘルス不調に陥るリスクが高まります。企業には、このような高ストレス者に対して適切な措置を講じ、従業員の健康を守る「安全配慮義務」があります。そのため、高ストレス者の基準を正しく理解し、迅速かつ適切に対応することが、企業のコンプライアンスと従業員のウェルビーイング向上に直結するのです。
では、具体的にどのような従業員が「高ストレス者」と判定されるのでしょうか。高ストレス者の判断基準は、主に厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」を用いて、以下の2つのいずれかに該当する場合とされています。
職業性ストレス簡易調査票の各項目には点数が設定されており、ストレスの度合いを数値で評価します。
これらの点数基準は、標準的な集団との比較によって客観的にストレスの度合いを評価するために用いられます。
ストレスチェックの結果、量的な基準には該当しなかった場合でも、医師(主に産業医)が個々の状況を総合的に判断し、必要と認める場合に高ストレス者と判定されることがあります。これは、数値だけでは測れない個人の状況や背景、例えば「最近、家庭環境に大きな変化があった」「特定のハラスメントを受けている可能性がある」といった要因を考慮に入れるためです。
この医師(主に産業医)による総合評価は、特に従業員からの自由記述や、ストレスチェック後の面談を通じて得られる情報に基づいて行われることが多いです。
高ストレス者と判定された従業員がいた場合、企業は以下のフローで対応を進めることが一般的です。
高ストレス者と判定された従業員に対しては、医師(主に産業医)による面接指導を受けるよう勧奨する義務があります。これは、従業員自身の健康状態を医師(主に産業医)の専門的な視点から評価してもらい、今後の対応について助言を得るための重要なステップです。
従業員から面接指導の申出があった場合、企業は遅滞なく医師(主に産業医)による面接指導を実施する義務があります。
面接指導の結果、医師(主に産業医)から就業上の措置が必要である旨の意見が出された場合、企業はその意見を参考に、適切かつ必要な措置を講じる義務があります。
【措置の例】
【従業員との合意形成】
措置を講じる際には、従業員の意見を十分に聞き、合意形成を図ることが重要です。一方的な措置は、かえって従業員のストレスを増大させる可能性があります。
【プライバシーへの配慮】
措置の内容によっては、他の従業員に情報が伝わる可能性があるため、最大限のプライバシー保護に配慮する必要があります。
高ストレス者が出たということは、その背景に職場全体のストレス要因が潜んでいる可能性があります。個別の対応だけでなく、ストレスチェック全体の集団分析結果も踏まえ、職場環境の改善に取り組むことが重要です。
【具体的な取り組み例】
・長時間労働の是正
・ハラスメント対策の強化
・コミュニケーションの活性化
・相談窓口の設置・周知
・管理職へのメンタルヘルス研修の実施
・業務プロセスの見直し
これらの取り組みを通じて、ストレス要因を根本から解消し、従業員全員が健康で安心して働ける職場づくりを目指しましょう。
高ストレス者への対応はデリケートな問題であり、以下の点に特に注意が必要です。
ストレスチェックの結果や面接指導の内容は、「要配慮個人情報」に該当し、厳重な管理が求められます。
高ストレス者と判定されたこと、あるいは面接指導を申し出たこと、面接指導を受けたことを理由に、従業員に対して不利益な取り扱いをすることは法律で禁じられています。
自社だけでの対応が難しい場合や、より専門的な知見が必要な場合は、産業医や外部のEAP(従業員支援プログラム)機関などと積極的に連携することが非常に有効です。
本記事では、ストレスチェックにおける「高ストレス者」の基準とその後の対応について解説しました。
高ストレス者への適切な対応は、従業員一人ひとりの健康を守るだけでなく、企業全体の生産性向上と健全な組織運営に不可欠です。本記事が、貴社におけるストレスチェック制度の運用、ひいては従業員が心身ともに健康に働ける職場環境づくりのお役に立てれば幸いです。
エムスリーグループが提供する「職場のストレスチェックplus」のサービス資料です。 サービス内容のご案内、料金、ご契約までの流れを記載しています。 「サービスの導入で何ができるの?」 「産業保健体制の情報収集として知っておきたい」 など、今後のご検討のご参考にしていただけますと幸いです。
本資料は、ストレスチェックの集団分析結果の活用をサポートする資料になります。 「ストレスチェックの集団分析結果をうまく活用できない」、「データを元に、社内全体を巻き込みながら職場環境を改善したい」、「経営陣や産業医と連携をとって施策を進捗させたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け