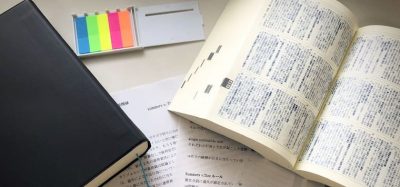
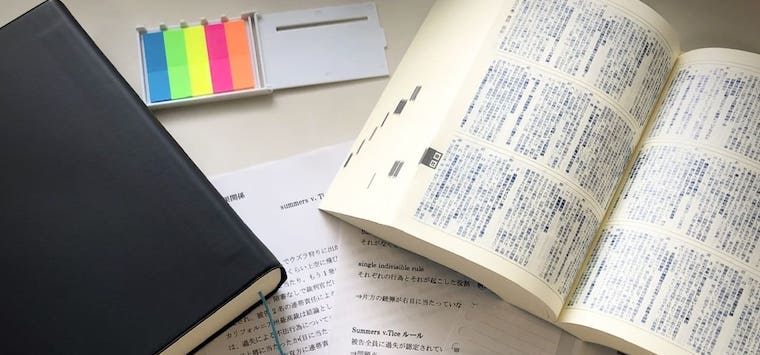
労働安全衛生法(安衛法)は、働く人々の安全と健康を守るための重要な法律です。企業の人事労務担当者の方にとって、この法律を理解し、適切に運用することは、従業員の健康を守るだけでなく、企業の信頼性を高め、法的リスクを回避するためにも不可欠です。
しかし、「労働安全衛生法」と聞くと、その複雑さや広範な内容から、どこから手をつければ良いのか迷ってしまう方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、労働安全衛生法の基本的な目的から、企業が果たすべき具体的な義務、万が一違反した場合の罰則、さらには労働基準法との違いまで、人事労務担当者が知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目次
労働安全衛生法は、労働災害の防止を目的として、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進するための法律です。この法律は、労働者の生命や身体を守ることを最も重要な課題として位置づけ、企業に様々な義務を課しています。
労働安全衛生法第1条には、その目的が明確に示されています。
“労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止を目的とし、労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等、その促進に関する総合的な計画を樹立し、実施することを目的とする。”
簡単にまとめると、以下の3つの柱で構成されています。
これらの目的を達成するために、労働安全衛生法は、事業者だけでなく、機械器具を製造・輸入する者、建設工事の注文者など、幅広い関係者に安全衛生に関する措置を義務付けています。
労働安全衛生法は、その目的達成のために多岐にわたる内容を規定しています。主な内容は以下の通りです。
これらの規定は、労働安全衛生法本体だけでなく、その下位法令である労働安全衛生法施行令や労働安全衛生規則、さらには各種告示によって詳細が定められています。
労働安全衛生法は、企業(事業者)に対して多岐にわたる義務を課しています。これらの義務を果たすことは、従業員の安全と健康を守るだけでなく、企業の社会的責任を果たす上でも極めて重要です。ここでは、企業が特に意識すべき主な義務を具体的にご紹介します。
事業者は、労働者の安全と健康を確保するため、以下の義務を負います。
これらの義務を確実に履行することで、労働災害の発生を未然に防ぎ、労働者が安心して働ける環境を整備することができます。
労働者もまた、労働安全衛生法に基づき、事業者によって講じられる安全衛生に関する措置を守る義務があります。
労働者と事業者が一体となって安全衛生に取り組むことが、より安全で健康な職場環境の実現につながります。
労働安全衛生法は、単に企業の努力義務を定めるだけでなく、違反に対する厳格な罰則も規定しています。重大な違反があると、企業のイメージダウンや信用失墜にもつながるため、法令遵守は企業の持続的な発展にとっても極めて重要です。
労働安全衛生法における企業の責任は、単に罰則を受けることだけではありません。
これらのリスクを回避するためにも、企業は労働安全衛生法を深く理解し、常に最新の情報を把握しながら、適切な安全衛生管理体制を構築・維持していく必要があります。
労働者の保護を目的とする法律として、労働安全衛生法と並んで「労働基準法」がよく挙げられます。両者は密接に関連していますが、その目的と内容には明確な違いがあります。
労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律です。具体的には、労働時間、賃金、休日、休暇、解雇など、労働契約に関する基本的なルールを定めています。労働者が人として文化的な生活を営むことができるよう、労働条件の改善を図ることを目的としています。
一方、労働安全衛生法は、労働者の安全と健康の確保に特化した法律です。労働災害の防止、快適な職場環境の形成を目的として、作業場の安全対策、機械設備の安全基準、健康診断の実施、安全衛生教育など、主に職場の環境や作業方法に関するルールを定めています。
| 項目 | 労働基準法 | 労働安全衛生法 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 労働条件の最低基準を定めること | 労働災害の防止、労働者の安全と健康の確保 |
| 対象範囲 | 労働時間、賃金、休日、休暇、解雇など、労働契約全般 | 職場の安全対策、健康管理、作業環境など、安全衛生全般 |
| 所管 | 厚生労働省 労働基準局 | 厚生労働省 労働基準局(安全衛生部) |
このように、労働基準法が「労働条件」という広範な側面をカバーするのに対し、労働安全衛生法は「安全と健康」という特定の側面を深く掘り下げています。両方の法律を理解し、遵守することが、企業にとって健全な経営を行う上で不可欠です。
労働安全衛生法は、従業員の安全と健康を守り、快適な職場環境を整備するために、企業が遵守すべき重要な法律です。本記事では、その目的、企業が負う具体的な義務、違反した場合の罰則、そして労働基準法との違いについて詳しく解説いたしました。
労働災害は、従業員の心身に深い傷を残すだけでなく、企業の経営にも深刻な影響を及ぼします。法的罰則や損害賠償、企業イメージの失墜など、その代償は計り知れません。
人事労務担当者の皆様には、この記事で解説した内容を参考に、労働安全衛生法の基本をしっかりと理解し、自社の安全衛生管理体制を見直していただくことを強く推奨いたします。日々の業務において、以下の点を意識して取り組んでいきましょう。
労働安全衛生法の遵守は、企業の義務であると同時に、従業員が安心して長く働ける職場を提供するための重要な投資でもあります。
安全衛生委員会のテーマ資料サンプル集です。 「ハラスメント」「メンタルヘルス」「業務災害」の3つのテーマについて 委員会でご利用いただける資料のサンプルをダウンロードいただけます。 効果的な議論を行うためにも、ぼんやりとテーマを決めておくのではなく テーマについて下調べし、資料を作成しておくことが大切です。 参加者の論点を揃え、具体的な話や改善策の検討につながるように準備しておくとよいでしょう。
エムスリーキャリアの産業医サービスを導入いただいている企業様の導入事例集です。 「産業医サービスを実際に導入した企業の声が知りたい」 「産業医サービスを導入しようか検討している」 とお考えの企業様はぜひご参考になさってください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け