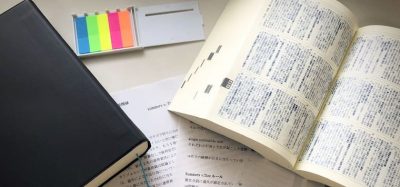

2025年に施行された改正労働安全衛生法は、企業の人事労務担当者にとって、喫緊の課題となっています。本記事では、法改正の背景から具体的な改正内容、企業が取り組むべき対応まで解説します。特に、ストレスチェック制度の見直しや熱中症対策の強化など、実務に直結する重要な変更点に焦点を当てていきます。
目次
2025年に施行された改正労働安全衛生法は、労働者の安全と健康を一層確保することを目的としています。近年の労働環境の変化や新たなリスクの顕在化に対応するため、既存の枠組みでは不十分と判断された点が多数見直されています。特に、メンタルヘルス対策の強化や、熱中症リスクへの対応は、企業が喫緊で取り組むべき課題として位置づけられています。
この改正は、単なる法規制の追加ではなく、企業が自主的に安全衛生管理を推進し、労働者が安心して働ける環境を構築することを強く促すものです。人事労務担当者は、今回の改正が自社の事業活動にどのような影響を与えるかを正確に把握し、適切な対策を講じることが求められます。
現在、従業員50人以上の事業場に義務付けられているストレスチェックですが、2025年の改正では、その対象が拡大される可能性が示唆されています。従業員数が少ない事業場においても、労働者のメンタルヘルスケアの重要性が高まっており、小規模事業場への義務化拡大や、実施頻度の見直しなどが検討されています。
現在は対象外であったとしても、今後の動向には常に注目し、早めの準備を進めることが重要です。厚生労働省の動向や関連省令の発表を注視し、制度改正の具体的な内容を把握しましょう。
近年、記録的な猛暑が続き、職場での熱中症リスクはますます高まっています。このような状況を受け、労働者の命と健康を守るため、2025年6月1日より労働安全衛生規則が改正され、熱中症対策が強化されました。
今回の改正で、事業者に義務付けられる具体的な措置は以下の2点です。
これらの措置を明確にし、手順を共有することで、いざという時に迅速かつ適切な対応ができるようになります。貴社では、これらの新たな義務に対応するための準備が整っているか、今一度確認してみましょう。
まず、最も重要なのは、労働安全衛生法改正に関する最新かつ正確な情報を継続的に収集することです。厚生労働省のウェブサイトや関係省庁の発表、信頼できる専門機関からの情報を常にチェックし、法改正の具体的な内容が確定次第、速やかに社内で共有する体制を整えましょう。
特に、経営層や各部署の管理職に対し、法改正の重要性と自社への影響を説明し、理解と協力を得ることが不可欠です。社内研修の実施も有効な手段です。
法改正への対応は、多岐にわたる専門知識を要することが少なくありません。特に、ストレスチェックの結果分析に基づく職場改善や、複雑な労働災害発生時の対応などにおいては、産業医や弁護士などの専門家の知見が不可欠です。
今回の改正を機に、これらの専門家との連携を強化し、必要に応じてアドバイスを仰ぎ、適切な対策を講じられる体制を構築しましょう。顧問産業医や顧問弁護士がいない場合は、この機会に契約を検討することも重要です。
2025年の労働安全衛生法改正は、企業の人事労務担当者にとって、労働者の安全と健康を守るための重要な機会となります。ストレスチェック制度の深化や熱中症対策の強化など、実務に直結する変更点が多く、早期の対応が求められます。
産業医をはじめて選任する場合、産業医についての知識や担当業務、探し方や選任手続きについて、何をどうすればいいのかわからない担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。 本資料は保健師監修のもと作成した、産業医をはじめて選任する企業担当者様向けの資料になります。「産業医選任の基本的な知識について確認したい」、「産業医の探し方や選任手続きの流れについて知っておきたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
安全衛生委員会のテーマ資料サンプル集です。 「ハラスメント」「メンタルヘルス」「業務災害」の3つのテーマについて 委員会でご利用いただける資料のサンプルをダウンロードいただけます。 効果的な議論を行うためにも、ぼんやりとテーマを決めておくのではなく テーマについて下調べし、資料を作成しておくことが大切です。 参加者の論点を揃え、具体的な話や改善策の検討につながるように準備しておくとよいでしょう。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け