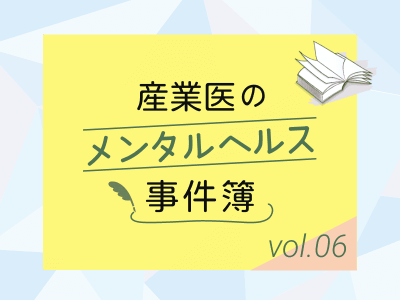
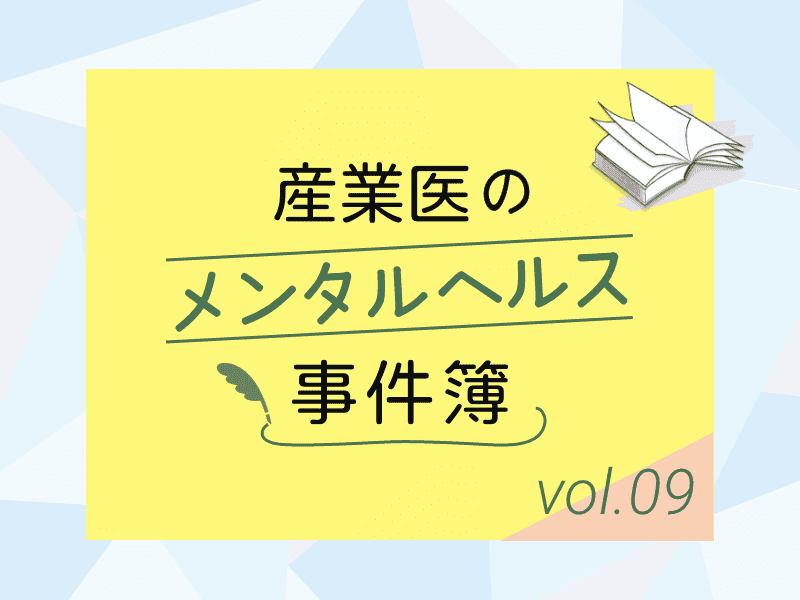
企業の人事労務担当者が思い悩むことの1つに、従業員のメンタルヘルス対応が挙げられるでしょう。「産業医のメンタルヘルス事件簿」では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷の産業医兼精神科医の先生方に、産業保健の現場で起きていることやその対応について寄稿いただきます。
今回はVISION PARTNERメンタルクリニック四谷のパートナー医師である岸本雄先生に、訴訟を招きかねない事例の対応方法について教えていただきました。
目次
産業保健法学会で話題になった「シャープNECディスプレイソリューションズ事件(横浜地裁令和3年12月23日判決)」という事件があります。発達障害特性を背景に職場不適応を起こし休職、不適応のきっかけになった症状は改善し、主治医および産業医の判断で復職可能となったものの、企業側が許可せず休職期間満了を機に自然退職させたため、訴訟となったケースです。この裁判では、『心の準備ができていない人に 「診断を受けるように促した」こと』から最初のこじれが生じました。産業医、会社側としてはどういう対応をとるべきだったのか、似たような事例を通して考えてみたいと思います。
このような場合、産業医・人事担当者の立場でどのように対応するのが妥当か考えてみました。
時に会社の人事担当者は「病気であることがはっきりし、本人がそれを受容しなければ、物事が解決しないのではないか?」と思ってしまうことがあります。しかしこの考え方は危険です。特に今回のように、本人に自覚がない場面で、無理に診断や精神科への受診を勧めようとするとこじれる可能性が高くなります。反対に「朝起きられなくて欠勤が続いている」「集中力が落ちてミスが増えている」「無断で残業している」といった労務上の問題(事例性)について本人と共有した方が、まだスムーズに進むことがあります。なぜなら本人自身も困っている、もしくはうまくいっていないと部分的には自覚していることが多いからです。
病院への受診を勧めるとしても、「発達障害だと思うから診断をつけてもらってください」と言うのではなく「〇〇といった問題行動が続いていると思うけれども、あなたとしてはどう思うか?」「我々はあなたにストレスがかかりすぎていないか心配しているので一度病院(産業医)に相談するのはどうか?」と促す方が衝突する可能性は低くなります。それでも病院への受診を拒否し、問題行動がおさまらない場合は、労務上の問題として、懲戒処分の対象となることを伝えながら対応していくことになるでしょう。
Aさんのケースで更にこじれを生んだのは、復職のラインを後からずらしたことです。休職の原因となった『事例性』について明確に本人と共有できたのであれば、やはりその問題が解決したかどうかが重要になります。現実的には、背景である発達障害の特徴が事例性に大いに関わっていることはよくあり、明確に区別するのは難しいと思います。しかし後から違った理由を持ち出して復職を許可しなかった場合、新たなこじれに繋がります。
この行為は訴訟という観点から見ても不利です。同様のケースとして神奈川SR経営労務センター事件、冒頭で触れたシャープNECディスプレイソリューションズ事件などが参考に挙がりますが、いずれも「労働者の保護の観点からは、休職期間満了時点で、その傷病の症状が私傷病発症前の職務遂行レベルの労働を提供することに支障がない程度にまで軽快した場合には、当該傷病とは別の事情による自然退職とすることはできない」という点が、判例上ポイントになっていました。よって主治医から復職可能の診断書が出された後で、違う理由で復職を許可せず、休職期間満了による退職扱いにしたとしても、訴訟を起こされた場合は無効にされてしまう可能性が高いと言えます。
では主治医から復職可能の診断書を出された場合、会社側としては無条件で復職を許可するしかないのでしょうか。許可をだすにしても、可能な限り本人と復職後の働き方についてすり合わせをしておきたいのではないでしょうか。例えば復職面談を行う前に、以下の項目について産業医と共有しておくといいかもしれません。
上記の内容を産業医や職場上司、人事担当者などで事前にまとめて共有しておき、可能であれば復職面談そのものも皆が同席した状態で行えるとより望ましいでしょう。
本人に対して『病気であることを診断し、受容すること』にこだわるのは危険です。
これらを具体的に定め、本人とすりあわせていくことが、結果的に大きなこじれを生むリスクを下げることにつながると考えます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け