
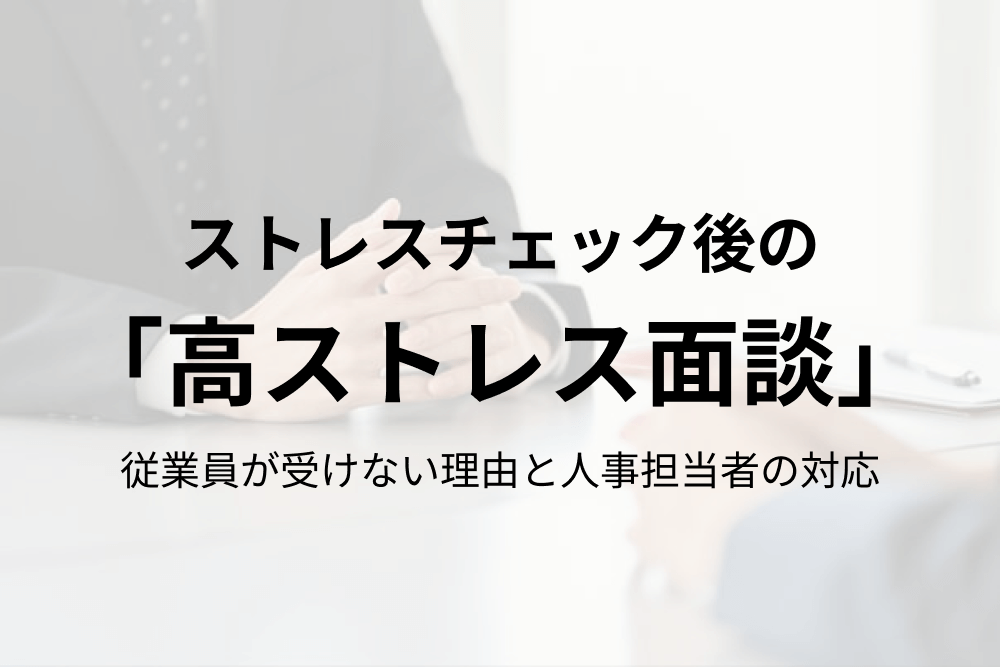
従業員50名以上の事業場では、年1回以上のストレスチェック実施が事業者の義務とされています。この法制度は、2028年頃を目処に、従業員50名未満の事業場にも義務の対象が拡大される見込みです。
ストレスチェックの目的は、従業員のストレス状態を早期に把握し、メンタルヘルス不調の未然防止や職場環境改善につなげるための重要な取り組みです。しかし、高ストレスと判定されても面談を希望しない従業員は一定数存在し、企業の担当者としては対応に悩む方もいるのではないでしょうか。
本記事では、ストレスチェック後の面談について「受けたくない」と考える従業員側の理由と、面談を受けてもらうために取り組みたい人事担当者の対応について具体的に紹介します。
目次

従業員が高ストレス面談を受けたくない理由は多岐にわたりますが、厚生労働省の検討会にて取り上げられた内容等によると、主に以下の3つの懸念が挙げられます。
最も多いと考えられるのが、「人事評価に影響があるのではないか」という理由です。これは、会社や産業医への不信感を抱いている状況ともいえます。
ストレスチェックの結果や高ストレス者面談の内容は、非常にデリケートな個人情報です。そういった情報が会社に知られることで、不適切な形で利用されるのではないかという不安は根強く存在します。
従業員としては、「面談で話した内容が、上司や他の同僚に筒抜けになるのではないかと不安だ」「自分の弱みを会社に握られるような気がして抵抗がある」といった思いを抱いています。また、「面談を受けることで異動させられたり、責任の重い仕事を外されたりするのではないか」といった漠然とした不安を抱く人もいるでしょう。
従業員がストレスチェック後の面談を受けたくないと考える2つ目の理由は、面談の目的やメリットを感じられないからです。
「ストレスチェック後の面談が何のためにあるのか分からない」「面談を受けても意味がないのではないか」といった考えが根底にあります。面談の具体的な目的や、受けることで得られるメリットが十分に伝わっていない場合、面談の必要性を感じにくいのは当然です。
従業員の心境としては、「ストレスチェック後の面談を受けたところで、具体的な解決策が得られるとは思えない」「産業医に話したところで、会社の体質が変わるわけではないし、自分にメリットがない」といったものが想定できます。
3つ目の理由は、産業医面談を受けること、そしてその事実が知れ渡ってしまうことで、高ストレス者のレッテルを貼られてしまうのではないか、という危惧です。
従業員は、ストレスチェック後の面談を受けることで「精神的に弱い人間だ」というレッテルを貼られるのではないかと懸念しています。
また、高ストレス判定の要因が職場のハラスメントに関連しているような場合は、会社自体に不信感を抱いているケースも考えられ、面談に対してより抵抗を感じる傾向にあります。

ストレスチェック後の産業医面談は、従業員のメンタルヘルス不調の深刻化を防ぐためにも、非常に重要な機会です。そのため、人事担当者は前述したような従業員が抱える懸念や疑問を解消し、ストレスチェック後の面談が受けやすい環境を整備することが重要です。
面談を効果的な取り組みにするためには、人事担当者による適切な周知と丁寧な対応が不可欠です。以下に具体的な方法を紹介します。
企業担当者として、まずはストレスチェックの目的を明確に伝えることが重要です。ストレスチェックが単なる義務や「高ストレス者をあぶり出す」ものではなく、不調者に対して早期にアプローチすることや、職場の環境改善のために行うことを明記してください。
具体的には、ストレスチェック実施の前に、イントラネット、メール、社内への掲示などを通じてその内容を伝えます。特に、職場ではじめてのストレスチェックを実施するような場合では、説明会の開催などを通じて、個人情報の取り扱いや面談の任意性などを詳細に説明します。場合によっては質疑応答の時間を設け、従業員の疑問や不安に直接答える機会を作りましょう。
ストレスチェック後の高ストレス面談は、従業員からの申し出があった際に実施されるものです。よって、まずは面談が強制ではないことを明確に伝える必要があります。
また、「プライバシーの保護」も徹底して伝えます。産業医には守秘義務があり、面談で話した内容は従業員本人の同意なしに外部に漏えいすることはありません。
具体的な対応例としては、こうしたプライバシー保護について、書面や口頭で「面談はあくまで任意であり、本人の同意がなければ実施しないこと」「面談を受けなくても、いかなる不利益も生じないこと」を明記し、周知を行います。
最後に、従業員に対し高ストレス面談の具体的なメリットを伝えることが重要です。従業員が得られる具体的なメリットを提示することで、面談の必要性を感じてもらいやすくなります。
例えば、以下のようなメリットを伝えると良いでしょう。
ストレスチェック後の高ストレス者面談は、従業員の心の健康を守るだけでなく、より良い職場環境を築くための重要な取り組みです。面談を受けたくないと考える従業員の背景には、制度への理解不足やプライバシーへの懸念など、様々な理由がありますが、人事担当者はこれらの懸念を解消し、面談のメリットを丁寧に説明することが不可欠です。
従業員が安心して産業医面談を受けられる環境を整え、産業保健スタッフとの連携を強化することで、面談が従業員自身の心の健康を守る有効な機会となるよう努めましょう。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
エムスリーグループが提供する「職場のストレスチェックplus」のサービス資料です。 サービス内容のご案内、料金、ご契約までの流れを記載しています。 「サービスの導入で何ができるの?」 「産業保健体制の情報収集として知っておきたい」 など、今後のご検討のご参考にしていただけますと幸いです。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け