
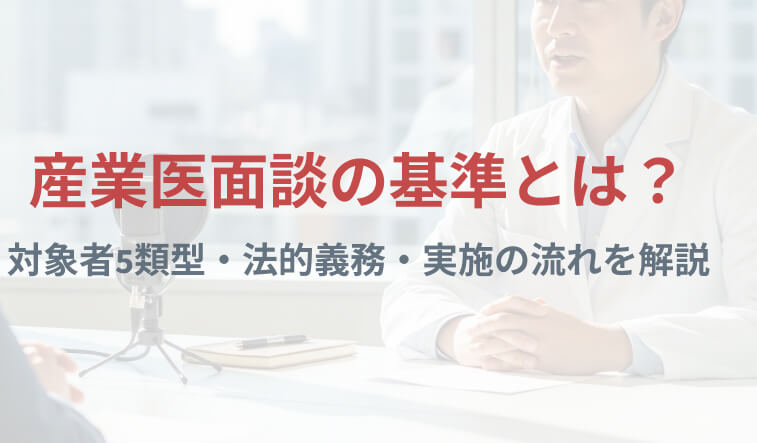
目次
産業医面談は、単なる福利厚生の一環や形式的な手続きではありません。これは、労働契約法や労働安全衛生法に定められた企業の「安全配慮義務」を果たすための、極めて重要な法的プロセスです。従業員の心身の健康を守ることはもちろん、企業を労務リスクから守る「守りの要」となる活動です。
従業員の健康問題が深刻化した場合、企業は安全配慮義務違反を問われ、法的な責任を負う可能性があります。産業医面談を適切に実施し、その記録を保管することは、企業が従業員の健康確保のために必要な措置を講じたことを示す客観的な証拠となります。
この記事では、人事労務担当者の皆様が、産業医面談に関する法的な要件を正確に理解し、実務で適切に対応できるよう、網羅的かつ実践的な情報を提供します。対象者の選定基準から面談後の措置、法的リスクまで、この一本で全てがわかる「業務マニュアル」としてご活用ください。
【関連記事】
産業医面談の対象となる従業員は、主に5つの類型に分けられます。それぞれの基準と企業の法的義務は複雑なため、まずは全体像を把握することが重要です。
| 対象者の類型 | 面談実施の主な基準 | 企業の法的義務 | 従業員の申出 | 主な根拠法令 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 長時間労働者 | 月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積があって本人が申し出た場合 | 義務 | 必要 | 労働安全衛生法 第66条の8 |
| (研究開発業務従事者等) 月100時間超の時間外・休日労働 | 義務 | 不要 | 労働安全衛生法 第66条の8の2 | |
| 2. 高ストレス者 | ストレスチェックの結果、「高ストレス者」と判定され、本人が申し出た場合 | 義務 | 必要 | 労働安全衛生法 第66条の10 |
| 3. 健康診断有所見者 | 健康診断の結果、「異常の所見」があった場合 | 義務 (医師からの意見聴取) | 不要 | 労働安全衛生法 第66条の4 |
| 4. 休職・復職者 | メンタルヘルス不調等で休職していた従業員が、復職を希望する場合 | 義務 (安全配慮義務に基づく) | 必要 (本人の復職希望) | 労働契約法 第5条 |
| 5. 本人希望者 | 上記以外で、心身の不調や職場環境に関する悩みを理由に本人が希望した場合 | 義務 (安全配慮義務に基づく) | 必要 | 労働契約法 第5条 |
この表はあくまで全体像です。次章以降で、各類型の詳細な基準と、人事労務担当者が取るべき具体的なアクションを解説します。
長時間労働は、脳・心臓疾患との関連性が医学的に指摘されており、産業医面談の最も厳格な基準の一つです。企業には、労働時間を正確に把握し、基準を超えた従業員に対して適切な措置を講じる法的義務があります。
時間外・休日労働時間が1ヶ月あたり80時間を超え、かつ従業員本人に疲労の蓄積があり、面談の申し出があった場合、企業は医師による面接指導(産業医面談)を実施しなければなりません。
ここで重要なのは、面談の実施は従業員の「申し出」が起点となる点です。しかし、企業はただ申し出を待つだけではいけません。安全配慮義務の観点から、対象となる従業員に対し、面談制度の存在を周知し、申し出を促す(勧奨する)ことが求められます。申し出がなかったとしても、企業がその前提となる情報提供や勧奨を怠っていた場合、義務を果たしたとは見なされない可能性があります。
一部の労働者については、本人の申し出がなくても、企業が面談を義務として実施しなければならないケースがあります。これは特に健康リスクが高いと判断されるためです。
これらのケースでは、企業側が主体的に対象者を把握し、面談を設定する義務を負います。
面談対象者を正確に把握するためには、厚生労働省が定める計算式に基づいて、時間外・休日労働時間を算出する必要があります。この計算と、その前提となる労働時間の把握は、面談制度全体の法的基盤です。ここでの誤りは、その後のすべての対応を無効にするリスクをはらみます。
計算式:
厚生労働省は以下の計算式を定めています。
1か月の時間外・休日労働時間数 = 1か月の総労働時間数 – (計算期間1か月間の総暦日数/7)x40時間
ここで、「1か月の総労働時間数」には、所定労働時間、時間外労働時間、休日労働時間がすべて含まれます。
起算日と計算頻度:
この計算は、毎月1回以上、一定の期日を定めて行わなければなりません。多くの企業では、給与計算の締め日を「起算日」として設定しています。重要なのは、毎月一貫したルールで計算することです。
管理監督者の扱い:
労働基準法上の管理監督者は、残業代支払いの対象外ですが、健康管理の観点からは労働時間の把握対象となります。したがって、管理監督者であっても時間外・休日労働が月80時間を超えた場合は、産業医面談の対象者として同様に扱う必要があります。
労働時間の計算後、企業には以下の2つのアクションが義務付けられています。
これらの通知や勧奨のプロセスを怠った結果、従業員に健康障害が発生した場合、企業は「申し出がなかったから」という言い訳は通用せず、安全配慮義務違反に問われる可能性が非常に高くなります。
【関連記事】
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、年に1回のストレスチェックの実施が義務付けられています。この結果、高ストレス者と判定された従業員も産業医面談の対象となります。
「高ストレス者」の選定は、事業場の衛生委員会等で審議した上で決定された基準に基づき、実施者が行います。厚生労働省のマニュアルでは、数値基準として以下の2つの例が示されています。
これらの基準はあくまで例であり、事業場の実態に合わせて設定することが可能です。
ストレスチェックに基づく面談プロセスは、従業員のプライバシー保護を最優先に設計されています。人事労務担当者は、この点を深く理解しておく必要があります。
この仕組みは、従業員が安心して正直にストレスチェックに回答し、必要であればためらわずに面談を申し出られるようにするためのものです。
企業は、高ストレス者と判定された従業員に対し、医師による面談を申し出るよう勧奨する(申出勧奨)必要があります。しかし、このプロセスで最も重要なのは、人事労務担当者が「強制者」ではなく「信頼できる案内役」として機能することです。
従業員が安心して申し出を行える環境を整備するために、以下の点を徹底して周知することが不可欠です。
従業員の信頼を損なうような言動は、制度全体の形骸化を招き、結果としてメンタル不調の早期発見という目的を果たせなくなります。これは、企業の安全配慮義務の観点からも大きなリスクとなります。
【関連記事】
定期健康診断で「異常の所見あり」と診断された従業員への対応も、法律で定められた企業の重要な義務です。
企業は、健康診断の結果、「異常の所見」があると診断された全ての労働者について、その健康を保持するために必要な措置について、医師(通常は産業医)から意見を聴かなければなりません。この意見聴取は、健康診断が行われた日(または従業員から結果の提出があった日)から3ヶ月以内に実施する義務があります。
これは単に「従業員に産業医と話させる」ことではありません。「企業が、専門家である医師から、就業上の措置に関する意見を公式に聴取する」という、企業自身に課せられた手続き上の義務です。この「意見聴取」という行為自体が、コンプライアンス上の重要なチェックポイントとなります。
医師からの意見聴取の結果、産業医は従業員の就業について、主に以下の3つの区分で判定し、企業に意見を述べます。
この判定は、企業の次のアクションを決定するための医学的な根拠となります。
企業は、産業医から聴取した意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、「就業上の措置」を講じなければなりません。
具体的な措置としては、以下のようなものが挙げられます。
重要なのは、産業医の意見を形式的に受け取るだけでなく、それを基に具体的なアクションプランを策定し、実行することです。この一連のプロセスを文書で記録しておくことが、安全配慮義務を果たした証拠となります。
【関連記事】
メンタルヘルス不調などで休職していた従業員の復職判断は、非常にデリケートで専門的な判断が求められます。この場面で、産業医は極めて重要な役割を果たします。
復職判断において、人事労務担当者は「主治医」と「産業医」の2人の医師と関わることになりますが、両者の役割と視点は明確に異なります。この違いを理解することが、適切な判断の鍵となります。
主治医から「復職可」の診断書が提出されたとしても、それはあくまで復職を検討するスタートラインです。最終的な復職可否の判断は、職場の実情を最もよく知る産業医の意見を重視して、企業が行うべきです。なぜなら、企業の安全配慮義務は、従業員を職場に戻すことではなく、復職後に再発・再休職させない環境を整えることにあるからです。
産業医は、主治医の診断書や本人との面談を通じて、多角的に復職の可否を判断します。厚生労働省の指針などでも示されている主なチェックポイントは以下の通りです。
これらの基準を満たしていないにもかかわらず復職を許可すると、症状の再燃リスクが高まり、企業の安全配慮義務違反を問われる可能性があります。
心の健康問題による休業者の職場復帰支援については、厚生労働省が「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」を公開しています。この手引きでは、休業開始から復職後のフォローアップまでを5つのステップに分けて解説しており、企業が体系的な支援プログラムを構築する上での「標準的なマニュアル」とされています。復職支援のプロセスを社内で標準化し、個々の担当者の判断に依存しない仕組みを構築するために、ぜひ参照してください。
【関連記事】
これまで挙げた4つの基準に当てはまらない場合でも、従業員は自らの意思で産業医面談を申し出ることができます。
など、心身の健康に関するあらゆる相談が可能です。企業には、この申し出があった場合に、速やかに面談を設定し、対応する義務があります(安全配慮義務)。
この制度は、問題が深刻化する前に従業員が自ら助けを求めることができるセーフティネットであり、企業にとっては潜在的なリスクを早期に発見するための重要な「早期警戒システム」として機能します。人事労務担当者は、全従業員に対してこの相談窓口が常に開かれていることを周知し、利用しやすい雰囲気を作ることが重要です。
【関連記事】
産業医面談を円滑かつ適切に進めるためには、人事労務担当者の事前の準備と当日の配慮が不可欠です。ここでは、具体的な手順を解説します。
面談対象者への通知は、本人のプライバシーに最大限配慮して行う必要があります。周囲に知られることで、本人が不利益を感じたり、面談をためらったりすることがないように注意しましょう。
面談がより効果的になるよう、事前に産業医へ必要な情報を提供しておきます。これにより、産業医は限られた時間の中で的確なヒアリングと助言を行うことができます。
提供すべき情報の例:
これらの情報を整理し、面談前に産業医に共有しておくことが、人事労務担当者の重要な役割です。
面談は通常30分から1時間程度で行われます。産業医は、勤務状況、生活習慣、心身の自覚症状などについてヒアリングを行います。
近年、テレワークの普及に伴い、オンラインでの産業医面談も増えています。オンラインで実施する場合、対面と同等の質を確保し、情報漏洩を防ぐために、厚生労働省が定める要件を満たす必要があります。
オンライン面談実施の主な要件:
これらの要件を満たしているか、事前に確認し、体制を整えておくことが重要です。
産業医面談は、実施して終わりではありません。面談後の対応こそが、従業員の健康回復と企業の法的リスク管理において最も重要です。
面談後、産業医は企業の講ずべき措置についてまとめた「意見書」を作成し、事業者に提出します。これは、産業医から企業への公式な報告書であり、医学的専門家の見地からの提言です。
意見書の主な内容:
厚生労働省や中央労働災害防止協会が意見書のフォーマットを公開しており、これらを参考に自社の様式を準備しておくとスムーズです。
【参考資料】
人事労務担当者が最も注意すべき点は、産業医の意見書の法的な位置づけです。
しかし、この「法的拘束力がない」という点を「従わなくてもよい」と誤解しては絶対にいけません。意見書を無視することのリスクは、計り知れないほど大きいのです。
つまり、産業医の意見書は、企業にとって「法的な地雷」のようなものです。それ自体は爆発しませんが、それを踏みつけて(無視して)進んだ先に、安全配慮義務違反という巨大な法的責任が待っています。
企業は、産業医の意見を真摯に受け止め、衛生委員会などで審議の上、適切な就業上の措置を決定・実施する必要があります。そして、そのプロセスと結果を記録し、保管することが不可欠です。
労働安全衛生規則に基づき、産業医面談の実施記録や意見書は、5年間保管する義務があります。この記録こそが、万が一の際に、企業が安全配慮義務を尽くしたことを証明する重要な防御策となります。
【関連記事】
最後に、人事労務担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
A: 一部の例外(研究開発業務従事者の月100時間超労働など)を除き、従業員に面談を受ける義務はなく、企業が強制することはできません。
対応のポイントは以下の2点です。
A: 従業員50人未満の事業場には、産業医の選任義務はありません。しかし、長時間労働者への面接指導義務や、労働契約法上の安全配慮義務は、事業場の規模にかかわらず適用されます。
このような小規模事業場のために、独立行政法人労働者健康安全機構が運営する「地域産業保健センター(地さんぽ)」が全国に設置されています。ここでは、長時間労働者への面接指導や健康相談などを原則無料で利用することができます。まずは最寄りのセンターに相談することをお勧めします。
【関連記事】
A: 産業医の意見書は、事業者(会社)宛てに作成されるものです。しかし、その内容は従業員本人の健康情報や今後の働き方に関する重要な情報を含んでいます。
個人情報保護の観点や、本人との信頼関係を構築し、円滑に就業上の措置を進めるためにも、意見書の内容、特に就業上の措置に関する部分は本人に説明し、共有することが望ましいです。情報共有のプロセス全体を通じて、透明性を保ち、本人の同意を得ながら進めることが基本となります。
産業医面談は、法律で定められた企業の義務であり、従業員の健康を守るための重要な制度です。本記事で解説した5つの対象者基準を正しく理解し、それぞれのケースに応じて適切な対応を取ることが、人事労務担当者には求められます。
特に重要なのは、面談を実施するだけでなく、その後の産業医の意見を尊重し、具体的な就業上の措置に繋げることです。この一連のプロセスを適切に運用し、記録を残すことが、従業員の健康と幸福に貢献するだけでなく、企業の法的リスクを管理し、健全な経営を守ることに直結します。
本記事が、皆様の事業場における産業医面談制度の適切な運用のための羅針盤となることを願っています。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
産業医面談を効果的なものにするには、面談後の従業員の満足度や状態を把握し、就業上の措置を講じることが重要です。 効果的な面談をスムーズに実施いただくためのツールとして、ぜひ本フォーマットをご活用ください。 ■フォーマットの内容 ・産業医面談実施後アンケート ・面接指導結果報告書・就業上の措置に係る意見書
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け