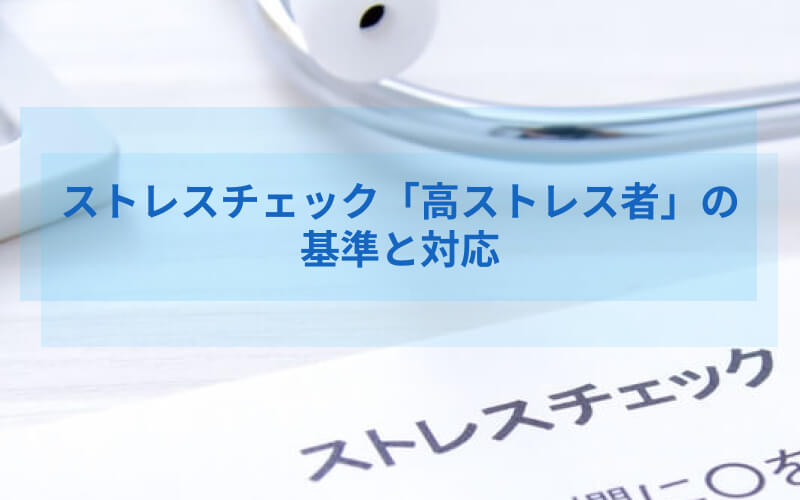
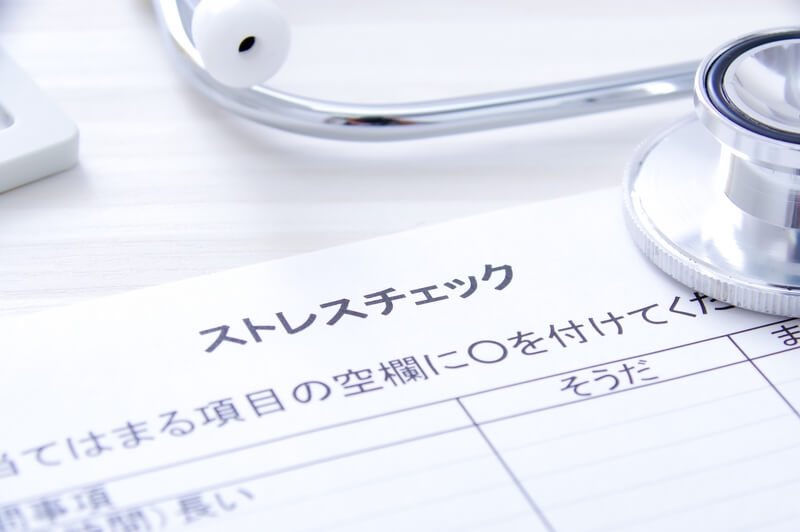
従業員のメンタルヘルス不調は、企業にとって大きな課題です。心身の健康を保つことは、従業員のパフォーマンス向上だけでなく、企業の生産性やイメージにも直結します。
この課題に対し、2015年12月より、労働安全衛生法に基づいて義務化されたのが「ストレスチェック制度」です。しかし、「ストレスチェックとは具体的に何を指すのか?」「なぜ義務化されたのか?」「どのように実施すればよいのか?」といった疑問をお持ちの人事労務担当者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
この記事では、人事労務担当者様が知っておくべきストレスチェック制度の基本から、具体的な実施方法、高ストレス者への対応、集団分析の活用方法まで、網羅的に解説します。
ストレスチェック制度とは、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐ「一次予防」を目的とした、定期的な心理的な負担の程度を把握するための検査制度です。労働安全衛生法に基づき、事業者に実施が義務付けられています。
ストレスチェック制度は、労働者が自身のストレス状態に気づき、セルフケアを行うきっかけを提供します。また、高ストレス者に対しては医師による面接指導を促し、早期のケアに繋げることが目的です。さらに、検査結果を事業場全体で集計・分析することで、職場環境の改善にも役立てられます。
2015年12月にストレスチェック制度が義務化された背景には、メンタルヘルス不調による休職者や退職者の増加、それに伴う企業の生産性低下や経済的損失が深刻化したことがあります。労働安全衛生法第66条の10において、常時使用する労働者数が50人以上の事業場に対し、年1回のストレスチェック実施が義務付けられました。これにより、事業者は従業員のメンタルヘルスケアに積極的に取り組むことが求められるようになりました。
ストレスチェックの対象者は、原則として常時使用するすべての労働者です。具体的には、期間の定めのない労働契約を結んでいる労働者や、1年以上継続して雇用される予定の有期契約労働者が該当します。実施頻度は、年に1回と定められています。
ストレスチェックの実施は、単に質問票を配布するだけではありません。制度に則った正しい手順を踏む必要があります。
ストレスチェックは、医師、保健師、または厚生労働大臣が定める研修を修了した歯科医師や看護師、精神保健福祉士、公認心理師などが実施者となることができます。また、人事権を持つ者以外の担当者(例:衛生管理者)が共同実施者となり、実施事務に従事することが一般的です。
ストレスチェックで使用する調査票は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易調査票(57項目または80項目)」が一般的です。その他、事業場の実態に合わせて独自の調査票を用いることも可能です。配布方法は、紙媒体またはWEBシステムによるオンライン実施が選択できます。WEBシステムを利用することで、回収・集計の手間を大幅に削減できます。
ストレスチェックの結果は、個々の受検者本人に直接通知されます。事業者が個人の結果を把握することは原則としてできません。高ストレスと判定された労働者には、結果とともに医師による面接指導を受けるよう勧奨されます。
高ストレスと判定され、面接指導を希望する労働者に対しては、事業者は医師による面接指導を実施する義務があります。面接指導では、医師が労働者のストレス状況を詳しく把握し、必要に応じて就業上の措置(労働時間の短縮や配置転換など)や専門機関への受診を勧奨します。
ストレスチェックは、個人のメンタルヘルスケアだけでなく、組織全体の健康状態を把握し、職場環境改善に繋げる重要なツールです。
ストレスチェックの個人結果は原則として事業者に開示されませんが、部署や課などの一定規模の集団ごとに集計・分析した結果は、事業者に提供されます。この「集団分析」の結果は、職場のストレス要因を特定し、組織的な改善策を講じるための貴重なデータとなります。例えば、「残業が多い部署」「ハラスメントが多い部署」など、具体的な課題を可視化できます。
集団分析の結果を受けて、事業者は職場環境改善に向けた具体的な取り組みを行うことが重要です。例えば、長時間労働の是正、ハラスメント対策の強化、コミュニケーション活性化のための施策、業務プロセスの見直しなどが挙げられます。これらの取り組みは、従業員のエンゲージメント向上や離職率低下にも寄与し、ひいては企業の生産性向上に繋がります。
ストレスチェック制度を適切に運用するためには、いくつかの注意点があります。まず、労働者の同意なく個人の結果を事業者が閲覧することはできません。また、ストレスチェックの結果を理由とした不当な人事評価や不利益な取り扱いは固く禁じられています。これらの違反があった場合、事業者には労働安全衛生法に基づき罰則が科される可能性があります。適切な運用体制を構築し、従業員のプライバシー保護に最大限配慮することが求められます。
ストレスチェック制度は、適切に導入・運用することで、企業の健康経営を推進し、従業員がいきいきと働ける職場環境を構築するための強力なツールとなります。
ストレスチェックの実施には、専門的な知識とノウハウが必要です。自社での実施が難しい場合や、より専門的なサポートを求める場合は、ストレスチェックサービスを提供する外部機関や産業医、保健師などの専門家を活用することをおすすめします。これにより、法令遵守はもちろんのこと、質の高いストレスチェックの実施と効果的なフォローアップが可能になります。
ストレスチェック制度を効果的に活用するためには、従業員への十分な周知と制度への理解促進が不可欠です。制度の目的や重要性、個人情報の取り扱いに関する説明を丁寧に行い、従業員が安心して受検できる環境を整えましょう。説明会や社内広報などを通じて、制度への理解を深めることが、受検率向上にも繋がります。
ストレスチェック制度は、単なる法令遵守にとどまらず、企業の「健康経営」を推進する上で重要な位置づけとなります。従業員の心身の健康を積極的にサポートすることで、従業員満足度の向上、生産性の向上、企業イメージの向上といった多岐にわたるメリットを享受できます。ストレスチェックで得られた情報を戦略的に活用し、持続可能な企業成長を目指しましょう。
この記事では、ストレスチェック制度の概要から、具体的な実施方法、高ストレス者への対応、集団分析の活用、そして制度運用の注意点までを詳しく解説しました。ストレスチェックは、従業員のメンタルヘルスを守り、健康的な職場環境を築くための重要な取り組みです。
人事労務担当者として、制度の正しい理解と適切な運用は不可欠です。この記事で得た知識を活かし、貴社のストレスチェック制度の導入・運用に役立てていただければ幸いです。
エムスリーグループが提供する「職場のストレスチェックplus」のサービス資料です。 サービス内容のご案内、料金、ご契約までの流れを記載しています。 「サービスの導入で何ができるの?」 「産業保健体制の情報収集として知っておきたい」 など、今後のご検討のご参考にしていただけますと幸いです。
本資料は、ストレスチェックの集団分析結果の活用をサポートする資料になります。 「ストレスチェックの集団分析結果をうまく活用できない」、「データを元に、社内全体を巻き込みながら職場環境を改善したい」、「経営陣や産業医と連携をとって施策を進捗させたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け