
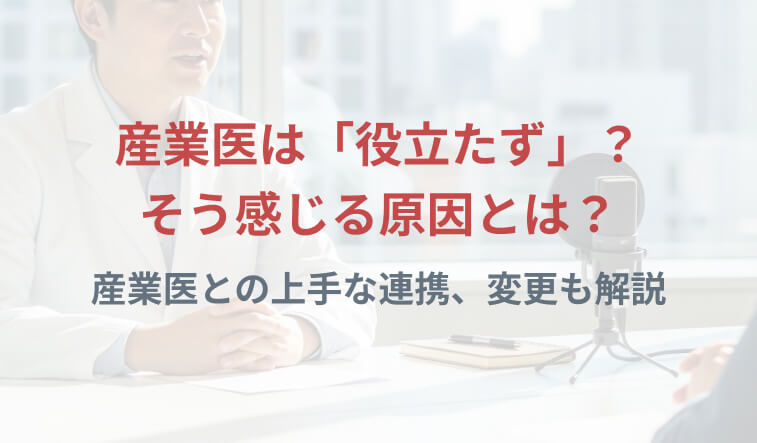
企業の人事労務担当者には、従業員の健康管理やメンタルヘルス対応に奔走する中で、産業医の対応に疑問を抱く場面が出てくることもあります。なかには、「産業医が役立たずだ」と語気を強めて不満を漏らす方もいます。
形式的な面談、当たり障りのないアドバイス、会社の意向ばかりを尊重する姿勢。産業医を設置している義務は果たしていても、実態が伴わなければ意味がありません。
この記事では、なぜ産業医が「役立たず」と感じられてしまうのか、その原因を深掘りします。さらに、産業医の能力を最大限に引き出すための「うまい使い方」、そして、どうしても改善が見られない場合の「産業医の変更・解任」の具体的な手続きや、自社に最適な産業医の探し方まで、人事労務担当者が知りたい情報を網羅的に解説します。
目次
人事労務担当者の皆様が、産業医に対して「役立たず」と感じてしまう背景には、共通するいくつかの理由があります。自社の状況と照らし合わせてみてください。
最も多く聞かれる不満の一つが、業務の形式化です。
これでは、従業員の健康状態や職場の潜在的リスクを把握するという産業医の役割を果たしているとは言えません。
産業医は、労働者と事業者の双方に対し、中立的な立場で専門的助言を行うことが求められます。しかし、実際には「会社の味方すぎる」と感じられるケースがあります。
例えば、従業員がメンタル不調で「休職が必要」と訴えていても、会社側の「人手が足りない」という事情を過度に忖度し、安易に就業継続を促すような意見を出す場合です。これでは従業員は産業医に本音を相談できなくなり、信頼関係が失われ、不調の早期発見・早期対応が困難になります。
医師免許があれば産業医になれますが、すべての医師がメンタルヘルス対応や、特定の業種(例:IT、製造業、運送業など)の労働環境に精通しているわけではありません。
企業のニーズと産業医の専門性(能力)がミスマッチしていると、「使えない」という評価につながりやすくなります。
産業医の役割は、面談や巡視だけではありません。衛生委員会への出席や、職場環境の改善、健康教育(衛生講話)などを通じて、企業全体のリスク管理に貢献することも期待されます。
しかし、衛生委員会に出席しても発言がなかったり、職場巡視で見つけた問題点を指摘するだけで改善策の提案がなかったりすると、企業側は「何のために来ているのか」と疑問を感じてしまいます。
嘱託産業医の場合、訪問は月1回、数時間程度という契約も少なくありません。訪問時以外は連絡が取りにくかったり、緊急のメンタル不調者が出た際に対応を相談できなかったりすると、人事担当者にとって「いざという時に役立たない」存在になってしまいます。
また、産業医の側から積極的に人事担当者や管理職と連携しようとする姿勢が見られない場合も、不満の原因となります。
「役立たず」という不満の根底には、産業医に期待する役割と、産業医が認識している役割の「ズレ」が隠れていることがよくあります。
産業医は「医師」ではありますが、従業員の病気を「治療」する(薬の処方など)のが仕事ではありません。産業医の目的は、労働安全衛生法に基づき、事業者が従業員の健康管理を適切に行えるよう「指導・助言」することです。
主な職務には以下が含まれます。
一方で、近年企業(特に人事労務担当者)が産業医に期待する役割は、メンタルヘルス不調者の対応や、ハラスメント問題への関与、生産性向上につながる健康経営の推進など、より高度で能動的なものへと変化しています。
この「法律上の最低限の義務」しか果たさない産業医と、「能動的な健康パートナー」を求める企業側との間に期待値のギャップが生まれると、「役立たず」という評価につながってしまうのです。
産業医の能力や意欲に問題がある場合もありますが、多くの場合、企業側の「使い方」次第で産業医のパフォーマンスは大きく変わります。産業医を変更する前に、まずは以下のような連携を試してみてください。
衛生委員会は、産業医から専門的な意見を引き出す絶好の機会です。
産業医が一人で職場を巡視しても、現場の課題は見えにくいものです。
産業医は社外の人間であり、待っているだけでは社内の情報は入ってきません。良い判断をしてもらうためには、人事からの積極的な情報提供が不可欠です。
「契約で決まっているから」ではなく、「会社としてメンタルヘルス対策を強化したい」「復職支援の精度を上げたい」といった具体的なニーズや期待する役割を、産業医にはっきりと伝えましょう。
産業医も、企業側が何を求めているかが分かれば、動きやすくなります。要望を伝えた上で、産業医側の得意分野やリソース(時間)とすり合わせることが重要です。
連携を試みても改善が見られない場合、産業医の変更(解任)を検討する必要があります。
事業者は産業医を選任する義務がありますが、特定の産業医を継続して選任し続ける義務はありません。そのため、事業者側の判断で産業医を変更・解任することは可能です。
ただし、産業医が法律に基づく勧告(例:健康への重大な懸念から、特定の作業の停止勧告)を行ったことを理由に解任するなど、不当な解任は認められません。
産業医の変更を決めたら、次は「役立つ」産業医をどうやって探すかが問題です。
新しい産業医候補者とは、契約前に必ず面談(オンライン可)を行いましょう。人事担当者だけでなく、経営層や現場の責任者も同席するのが理想です。
産業医が「役立たず」と感じられる背景には、産業医自身の能力や意欲の問題だけでなく、企業側の期待とのミスマッチや、連携の仕方の問題も大きく関わっています。
まずは、自社の産業医に求める役割を明確にし、積極的に情報を共有し、衛生委員会や職場巡視を活用することから始めてみてください。
それでもなお改善が見られず、従業員の健康管理に支障が出ると判断した場合は、法令違反にならないよう注意しながら、産業医の変更を検討することも人事労務担当者の重要な役割です。
自社に最適な産業医と連携し、実効性のある安全衛生体制を構築しましょう。
本資料は、産業医の交代を視野に入れている企業担当者様向けの資料になります。 「産業医の役割について改めて確認したい」、「自社の産業医がどのくらい職務を果たしているのか客観的に知りたい」、「産業医の探し方や交代手続きの流れについて知りたい」とお考えでしたら、ぜひご活用ください。
産業医サービスの比較検討時にご活用いただける資料をセットにしました。 「導入後、コスト面や活用面について特に見直しできていない」 「契約更新前に他サービスとの比較ポイントについて見直したい」 「産業医を交代したいが、気をつけるべきポイントを知りたい」 上記のようにお考えでしたらぜひご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け