

休職制度は法律で定められたものではなく、企業それぞれが主に就業規則で独自に規定する制度です。
また、適切な休職制度を整えることは、従業員だけでなく企業にとっても多くのメリットがあります。本記事では、就業規則における休職・復職の定め方と文例を紹介しています。
目次

就業規則にて休職の制度を設ける場合、定めるべき主な項目として以下の5つが挙げられます。
具体的にどのような内容を盛り込むべきなのか、順番に解説していきます。
会社がどのような基準で従業員に休職を命じるか、そして休職の適用範囲について明確にします。休職には業務外の傷病や自己都合による休職などがあるため、就業規則で定めておきます。
従業員が休職できる期間を定めます。休職期間は、勤続年数に応じて変化するケースが多いですが、長さは6ヶ月〜3年程度までが一般的といわれています。また、休職期間の満了時に復帰できなかった場合に、期間の延長が可能か否かについても明記しましょう。
休職中も会社の従業員であることを示します。また、待遇についての規定は後々トラブルを防ぐために非常に重要です。「給与」「賞与」「社会保険料」等の項目については就業規則に明記しておきましょう(詳しくは後述します)。
従業員の治療状況等を把握するため、会社の指示によって診断書の提出について定めます。また、休職期間は療養に専念する必要があります。そのため、休職事由と矛盾するような活動は控えることや、各種の報告を怠らないよう規定します。
そして、これらの義務に反する場合は休職を取り消すことも定めます。
従業員が復職する際のルールについて定めます。例えば、診断書の提出期限をはじめ、産業医による面談を実施すること、試し出勤を利用する可能性があることなどを定めます。
〈コラム〉休職中の待遇はどう決める?
・給与
休職中の給与については、法律に定めがなく無給としても問題ありません。また、労働の提供がない以上は賃金も発生しない「ノーワーク・ノーペイの原則」に則り、企業が休職者に賃金を支払う義務も発生しません。福利厚生の一環として休職者に給与を支払う場合でも、企業の判断で自由に金額を設定できます。
・賞与
休職中の賞与については、給与と同様に法律の定めがないため、無給や寸志程度でも問題ありません。必要であれば企業の判断で、査定期間中の最低出社日数や支給額について定められます。
・社会保険料
休職中でも社会保険の被保険者であることは変わりないため、休職者は休職前と同額の社会保険料を納付する義務があります。
「休職中は無給で給与からの天引きができない」などのケースも想定されるため、直接請求など徴収方法を定めておきましょう。
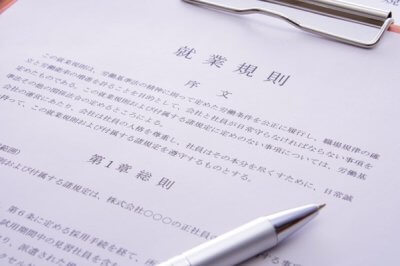
休職制度について就業規則については、厚生労働省にて「モデル就業規則」が閲覧できます。また、本記事では以下に就業規則の例をまとめていますので、こちらも参考にしてみてください。
(休職)
第〇条(休職の種類)
従業員が次のいずれかに該当するときは、休職を命ずることがある。
(1) 業務外の傷病により、長期にわたり労務に服することができないとき。
(2) 個人的な都合により、長期間職務に従事することが著しく困難であると会社が認めたとき(自己都合休職)。
(3) その他、特別の事情により会社が休職を必要と認めたとき。
第〇条(休職期間)
前条第1号に定める私傷病による休職期間は、勤続年数に応じて、次の各号に定める期間内とする。
(1) 勤続3年未満の者:〇か月
(2) 勤続3年以上10年未満の者:〇か月
(3) 勤続10年以上の者:〇か月
前項の休職期間には、試用期間は算入しない。また、私傷病による欠勤が連続して〇日以上となった場合は、その欠勤開始日を休職開始日とみなすことができる。同一または類似の私傷病により休職した者が復職後〇年以内に再度休職する場合、休職期間は通算する。ただし、復職後〇年以上勤務した場合は、新たな休職として取り扱う。
第〇条第2号に定める自己都合休職の期間は、原則として〇か月以内とし、会社が個別に定める。
前各項の休職期間中に休職事由が消滅しない場合は、休職期間満了をもって自然退職とする。
第〇条(休職中の身分および賃金)
休職中の従業員は、従業員としての身分を保有する。
休職期間中の賃金(基本給、手当、賞与等)は、原則として支給しない。ただし、会社が特に認めた場合はこの限りではない。
休職期間中も社会保険料の自己負担分は引き続き会社に支払うものとする。
第〇条(休職期間中の遵守事項)
休職中の従業員は、会社からの指示があった場合は、その都度、療養状況の報告や医師の診断書等の提出に応じなければならない。
休職中の従業員は、療養に専念し、回復に努めなければならない。休職事由と異なる活動を行った場合や、会社からの報告義務を怠った場合は、休職を取り消すことがある。
第〇条(復職)
休職期間満了日までに休職事由が消滅し、復職を希望する従業員は、原則として復職希望日の〇日前までに、会社指定の医師または会社が認めた医師の診断書を添えて復職願を提出しなければならない。
会社は、提出された診断書および会社指定の医師による診断、または産業医との面談等に基づき、従業員が従前の職務を遂行できる健康状態に回復しているか否かを判断する。
会社は、復職の可否を判断するにあたり、必要に応じて試し出勤制度の利用を指示することがある。この場合、試し出勤の期間や条件は会社が別に定める。
会社が復職を許可した場合は、原則として休職前の部署・職務に復帰させる。ただし、従前の職務への復帰が困難な場合や会社の都合により、従前の職務と異なる職務への変更や配置転換を命ずることがある。
会社が復職を不許可とした場合、休職期間満了日をもって自然退職とする。
第〇条(休職の取り消し)
休職中の従業員が次のいずれかに該当するときは、休職を取り消すことがある。
(1) 休職期間中に、休職事由が消滅したにもかかわらず会社に申告しなかったとき。
(2) 休職事由と異なる行動をとるなど、休職を継続するに値しないと会社が判断したとき。
(3) 正当な理由なく、会社からの指示や報告義務を履行しないとき。
※上記の就業規則はあくまでも例文です。内容はそのまま流用せず、自社に適した規定を作りましょう。
適切な休職制度の規定があることは、従業員と企業双方のためになります。
休職制度が整備されておらず、従業員を休職させずに解雇した場合、不当解雇として従業員から訴えられる可能性があるためです(労働基準法で禁止されている解雇権の濫用)。
訴訟は企業のイメージダウンにつながるケースもあるため、会社を守るためにも休職に関する規定を就業規則に定めましょう。
参考:e-Gov法令検索「労働基準法第16条」

休職に関する就業規則には、メンタル疾患の休職に対応できる内容を組み込みましょう。具体的に組み込むべき項目には、以下の3つが挙げられます。
それぞれの詳細について解説します。
メンタル疾患に対応した休職制度を策定するには、医師の診断書の提出が必要な旨を定めるとよいでしょう。
メンタル疾患には、検査がなく症状のみで病気と判断されるケースが多々あります。そのため、従業員がメンタル疾患を理由に休職を希望した場合、休職事由に当てはまるかどうかを本人の申し出だけで判断するのは困難です。
医師の診断書があれば、原因となる疾病や必要な療養期間が確認できるため、休職の必要性を判断するのに役立ちます。
メンタル疾患による休職者の休職期間について、就業規定に盛り込みましょう。メンタル疾患による休職の場合でも、休職期間は傷病による休職期間と同じにしているケースが多い傾向にあります。
もちろん、メンタル疾患独自の休職期間を設けることも可能です。状況によって休職期間を延長できるように就業規則に定めるなど、メンタル疾患による休職に柔軟に対応できるようにしておくのもよいでしょう。
また、休職と復職が繰り返されるのを防ぐために休職期間の通算規定も設けましょう。休職期間が満了した後に1日でも復職すれば、休職期間はリセットされます。そうすると再度、休職期間上限まで休職に入ることもできてしまうからです。
同種のメンタル疾患による休職の場合は、復職前の休職期間と通算するなども明記しましょう
【関連記事】復職しても欠勤続きの従業員、どうアプローチすればいい?―産業医のメンタルヘルス事件簿vol.11
メンタル疾患での休職中に、会社の指定医または産業医と面談するよう就業規則に設けることもできます。
メンタル疾患は、同じ病名であっても人によって症状が違うため、それぞれの休職者の回復具合を考慮し、総合的な復職可否の判断が必要です。そのためには指定医・産業医と連携し、医学的な見解を得る必要があります。
しかし、従業員には指定医や産業医との面談を受ける法的な義務はないため、休職者に拒否されるケースも考えられます。そのため、会社の求めに応じて、指定医・産業医との面談を受ける必要がある旨を定めておくとよいでしょう。
・
・
・
休職制度については法律で規定されていないため、企業ごとに基準を設けて就業規則に定める必要があります。
休職者に対してスムーズに対応できるよう休職制度を整えることは、結果的に企業イメージの向上や人材の流出防止にもつながります。休職に関する就業規則を作り、企業と従業員の双方にとってよりよい社内環境になるよう努めましょう。
当ブログを運営しているエムスリーキャリアでは、産業医面談が1件から依頼できるサービスをご提供しております。
休職・復職面談にも対応しており、1件あたり1.5万円からご利用に慣れますので、ぜひ詳細をご覧ください。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け