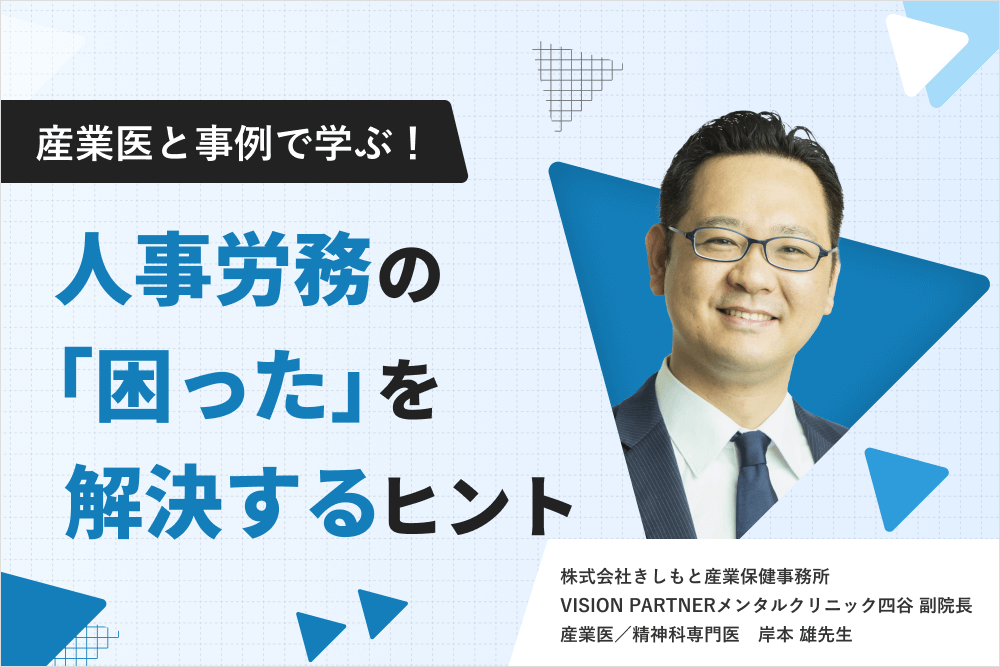
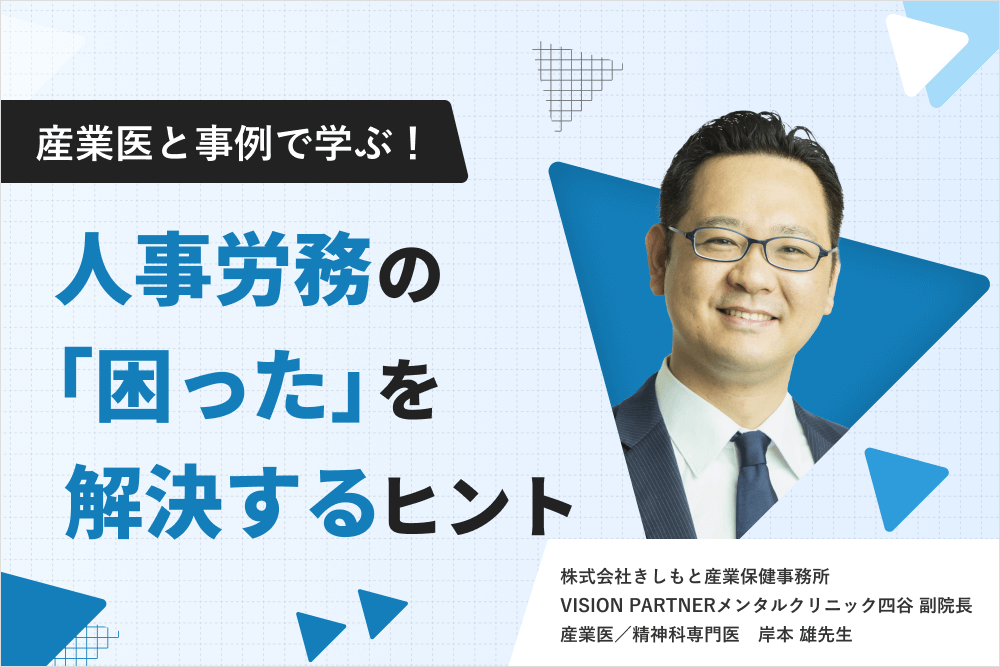
日頃、社内の産業保健対応をするにあたり、「こんな時どうしたらいいんだろう」「他社はどう対応しているんだろう」と思い悩むことはありませんか。
『産業医と事例で学ぶ!人事労務の『困った』を解決するヒント』では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷 副院長・岸本雄先生に寄稿いただき、産業保健で起こった事例(※)に基づいた対応、そういったケースを未然に防ぐTipsを取り上げていきます。
※事例の細部は変更してご紹介しています。
目次
今回は少し視点を変えて、精神科主治医の立場からお話しできればと思います。
実際に、私が対応した事例をご紹介します(以下、事例の細部は変更しています)。
家族の同意が確認できない、協力が得られない。そのせいで、目の前の治療を要する人に治療介入ができない。産業医という立場だけではありません。私は精神科主治医の立場でも、そうしたケースを何度も経験してきました。
ケースのように精神疾患の勢い(病勢とも言います)が強く、その影響が強く出ている状態だと、人は自分の置かれている状況を冷静に判断することが難しくなります。特に心の病は「転んで骨を折った」ように明らかに目に見えるものではないため、より一層自分が危機的な状況にいること、治療が必要な状態であることを認識することが難しくなります。
では、その状態の本人を「自分で病気であることを認識するまで」放っておいていいのでしょうか?そういうわけにはいきません。このため、特に精神科的な緊急事態の場面では、時に非自発的な治療導入を選択せざるを得ない場面が出てきます。
この“非自発的治療導入”の一つに「医療保護入院」という入院形態があります。この入院は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下:精神保健福祉法)第33条に規定されており、①精神保健指定医による診察で入院が必要と判断されること、②家族等(配偶者・親・子・兄弟姉妹など、民法上の扶養義務者や後見人を含む)のいずれかの同意があること、この二つが揃って初めて成立します。
「本人が拒否していても医師の判断で強制的に入院できる」「死にたいと言っているから即入院させられる」と誤解されがちですが、実際はそう簡単ではありません。家族の理解と同意がない限り、法律上は強制入院ができないのです。なぜならこの入院がもし恣意的に利用されてしまった場合、本人に対する重大な人権侵害につながるからです。
家族の協力は、単に「入院の手続きをしてもらうだけ」の話ではありません。実際には、もっと多くの場面で、理解と支えが必要になります。
たとえば
さらには、入院後の治療方針や生活の見通しなど…家族にも丁寧に説明する必要があります。
つまり、精神科の救急対応では、本人だけでなく家族も含めて一緒に動いていくことが大切なのです。
ただし、家族にとっても「突然」呼び出されて、「今すぐ病院へ連れてきてください」「入院に同意してください」と言われても、すぐに理解して対応するのは簡単なことではありません。
「え?うちの家族が精神病?しかも会社で?今すぐ入院!?」
と、本人以上に驚き、戸惑ってしまうことも珍しくありません。
だからこそ、「いざというとき」になる前の段階――たとえば、少し不調の兆しが見えてきた段階で、あらかじめ家族と情報を共有しておくことが、とても重要なのです。
「今すぐ何かをしてもらうわけではないですが、状況としてこういうことがあるかもしれません」とお伝えしておくだけでも、いざというときに家族が落ち着いて行動しやすくなります。
ご本人にとっても、家族にとっても、そして会社にとっても、“急変前の一歩”が、スムーズな対応につながる大切な備えになります。
理想は自殺リスクが警戒される段階で家族に連絡することです。例えばこんなサインが出始めたら、本人の同意を取りつつ家族に情報を共有しておくのが望ましいかもしれません。
| メンタルヘルス
不調サイン |
自殺リスク
警戒サイン |
自殺リスクが
切迫しているサイン |
|
| 上司から見えるサイン | ・突然遅刻・欠勤が増え、仕事の進みが極端に遅くなる ・明らかに集中力が続かず、簡単なミスが増える ・身だしなみが急に乱れてくる(髪や服装の変化) |
・これまで責任感が強かったのに、急に「どうでもいい」という態度になる ・評価面談などで「自分には価値がない」と口にする ・退職願を唐突に提出する、業務を放り出すような行動が出る |
・メールや会話中に「すみません」「お世話になりました」と異常に繰り返す ・出勤しても上の空で、仕事が手につかない ・出勤せず連絡が途絶える(無断欠勤) ・デスクに遺書のようなメモや、危険な物(ロープ、大量の錠剤など)を確認 |
| 同僚から見えるサイン | ・昼休みや雑談に参加せず、一人で過ごすことが増える ・急に飲み会や趣味活動に来なくなる ・口数が減り、話しかけても反応が薄い ・「疲れが取れない」「眠れない」とよく口にする |
・「もう生きていても仕方ない」など冗談交じりでも死をほのめかす ・急に身の回りの物を人に譲る、整理を始める ・借金やお金の工面を気にしている様子が強くなる ・夜遅くまで飲酒を繰り返すようになる |
・「もう終わりにする」「来週まで持たない」と具体的な言葉を口にする ・ネット検索やSNS投稿で「死にたい」「消えたい」と直接的に書き込む ・急に親しい人に「ありがとう」「さようなら」と別れを告げる ・最近まで沈んでいたのに、急に明るく落ち着いた様子を見せる(=実行を決意したサインのことがある) |
警戒サインがみられるからといって、すぐに命の危険があるとは限りません。しかしそのまま放置し、切迫サインがみられるようになると、いよいよ自殺既遂のリスクが高まります。よって警戒サインの段階で一度家族を巻き込み、精神科受診の必要性についてワンクッション整えておくことが、スムーズな治療介入への鍵になります。
本人が共有を拒否する場合はどうか?については、まずはその理由について丁寧に思いを聞いたのちに「次同じようなエピソードが起きた場合には、家族に共有させていただきます」とエクスキューズしておく手法を取ります。
サインを把握するだけでなく、緊急時に備えて以下の3つの備えを準備してもいいかもしれません。
遺書を書いている、道具をそろえて具体的に死ぬための準備を今まさに行っているなど、事態がまさに切迫しており、かつ家族とも連絡が取れないような状況では、本人の安全確保を最優先に考え、警察に相談することも選択にあがります。ただしこの判断は、医療機関・産業医・専門家と連携のうえで行うことが原則です。
従業員の家族への連絡は、非常に繊細な問題です。本人の意思やプライバシーへの配慮も必要であり、どのタイミングで、どのように関わるべきか、頭を悩ませます。だからこそ、産業医や精神科医、社労士などの専門家と連携しながら慎重に進めることが重要です。
そのうえで、本人の安全確保や治療導入をスムーズに進めるために、ご家族の関与が助けになる場面もあるということを、ひとつの選択肢として知っていただければと思います。
※本記事は、実際の精神科救急医療に関する制度や実務の一例をご紹介するものであり、あくまで参考情報としてお読みください。精神疾患の対応や家族への連絡については、個々のケースに応じて対応が異なります。実際の判断は、現場の産業医・精神科医・社労士等の専門家とご相談のうえ、慎重に行ってください。
エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。
産業医面談の受診勧奨を促すWord形式の参考例文フォーマットです。 参考例文をコピー&ペーストしてそのままメール文として送れるものになっています。産業医面談が義務である従業員用、努力義務である従業員用の2種類をご用意していますので、用途に応じて使い分け可能です。 本フォーマットを活用いただくことにより、速やかに産業医面談の受診勧奨をすることができます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け