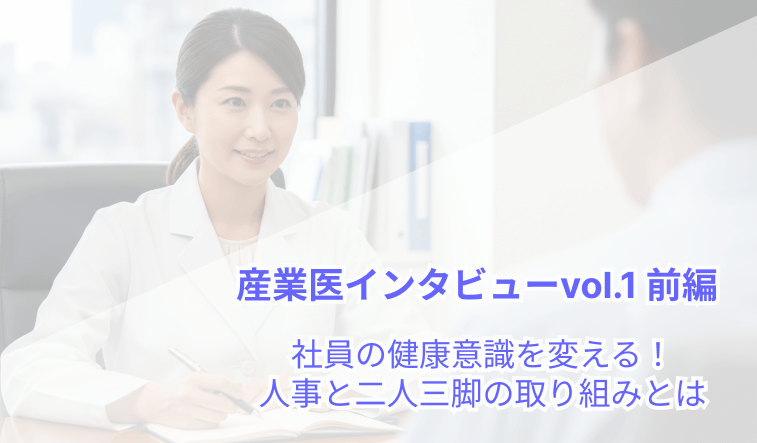
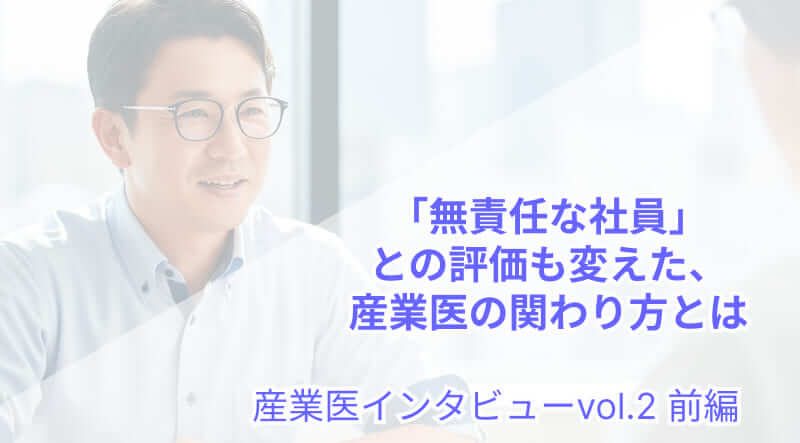
従業員の健康を守り、活き活きと働ける職場環境を整備することは、企業にとってその重要性が増しています。しかし、産業保健活動には「唯一の正しい答え」があるわけではありません。リソースも限られる中で効果的な産業保健活動を実現するには、産業医などの専門家と連携することが必要です。
本記事では、これまで大企業からベンチャー企業までさまざまな企業の産業保健に携わり、現在も20社の嘱託産業医を務める産業医・古河 涼先生にインタビュー。企業と産業医が「協働」することで、従業員の健康課題を解決し、より良い職場環境を築いていくための具体的なヒントや、産業医の専門性を最大限に活かすコミュニケーションの秘訣を伺いました。
前編では、産業医が最も専門性を発揮する「就業措置」と、一歩進んだ「多分野の専門家との連携」について深掘りします。

|
公衆衛生分野の研究に従事後、産業医として活動。5年間で幅広い業種・規模の企業を担当。これまでに製造業(食品、事務用品、自動車)、鉄道業、IT業界、金融業、コンサルティング業などの企業で、従業員の健康管理、メンタルヘルス対策、職場環境改善などに尽力してきた。
現在は嘱託産業医として20社と契約し、専門的な立場から企業の産業保健をサポートしている。 |
――先生が産業医になられたきっかけや、その活動で特に大切にされていることを教えてください。
私はもともと、公衆衛生の研究に従事していました。単に病気を治すことだけではなく、「病気を抱えながら社会で生きていくこと」に深く関心があったんです。たとえば職場でどう働いてらっしゃるのか、社会の中で疾患や不調を抱えながら、いかに活き活きと生活してらっしゃるのか、という側面に興味がありました。
実は、私自身、医学部の教育で産業医の具体的な仕事内容に触れる機会はほとんどありませんでした。多くの医師が、産業医資格を取る段階で、具体的な業務内容などを知り始めるのではないでしょうか。私の場合、同僚の医師に勧められたことが直接のきっかけとなり、活動を始めることになりました。産業医としてのキャリアは5年ほどになります。
産業医活動で最も大切にしているのは、「正解がない」ことを前提に、多様な考え方の中から最適な道を探っていくことです。産業保健活動には、「こうすれば完璧」という「唯一の正しい答え」があるわけではありません。私自身も、常に「こうありたい」と努力し、試行錯誤しながら模索している段階です。
――産業医活動で難しいと感じる場面はありますか?
特に難しいと感じるのは就業措置です。疾病を抱える従業員に対して、職場でどのような措置や配慮が必要か、という判断ですね。これは、医学的な要素だけで決められるものではありません。
たとえば、ある病気を持った方がいたとして、その方にとって最適な就業措置は、その方が「どういう職場で、どういう仕事をしているか」によって大きく変わってきます。デスクワークなのか、製造業の工場で身体を使う仕事なのか、それだけでも全く異なります。最近では、リモートワークが可能かどうかも非常に大きな論点です。リモートワークの可否によって、就業措置のあり方は大きく変わってきます。
しかし、医師は全国の職場の状況や業務内容に精通しているわけでもありません。そのため、就業措置は、「職場や業務に対する専門性」をもつ企業と、「医療の専門性」をもつ産業保健職(産業医等)の協働によって、初めて理想的で実効性のある措置が生まれると考えています。職場や業務のことは全く分からないので、そこが一番難しく、同時に非常に興味深い点だと感じています。
――企業と産業医が協働していくために、どのようなコミュニケーションが理想的だとお考えですか?
理想論としては、関係者全員が納得できる解決策を、皆さんで知恵を出し合って見出すことです。産業医が出す医学的意見は、そのための一要素として活用されるのが最も理想的だと思います。企業、従業員、主治医らが対立する関係になるのではなく、「健康に働いていく」という共通の目標に向かって協力し合うことが重要です。
これは一朝一夕にできることではなく、会社とそこで働く人々との関係性や風土が色濃く出る場面でもあります。産業医ができることにはどうしても限界がありますが、お互いが理解を深め合うような空気を作っていく努力は必要だと感じています。
具体的な実践として、私は「多様な意見を聞く」ことを心がけています。たとえば、直属の上司の方と人事労務の方で意見が異なることもありますし、一人ひとりの意見が全く違うこともあります。企業という組織は、そうした多様な意見を持つ人々で成り立っています。特定の意見だけを聞いて産業医の意見を形成してしまうと、ものの見方が偏り、対立構造や板挟みを生みやすくなるからです。多くの人の話を丁寧に聞くことで、板挟み問題の一部は解決できると考えています。
もちろん、企業の皆さんも産業医も多忙ですから、十分な時間を割くことが難しい場合もあるでしょう。どれだけリソースを割けるかは、企業と産業医の双方にとっての共通課題だと思います。しかし、私がお付き合いしている企業では、こちらが時間をいただけないかとお願いすれば、お時間をいただけることがほとんどです。これは非常にありがたいことです。
――実際に関係者同士が協力し合っていくにあたり、印象的なエピソードがあれば教えてください。
印象に残っているのは、ある企業で営業社員Aさんと連絡が取れなくなり、その方が担当していた外部業者からもクレームが入るという事態が発生したケースです。職場の皆さんはとても困惑し、上司の方は「Aは無責任な人物だ」と評価していました。
そこで産業医として私がご本人との面談や周囲へのヒアリングをしたところ、Aさんが「一時的に意識を失ったり意識がもうろうとしたりする疾患」を抱えているのではないかという疑いが出てきたんです。てんかんや、自律神経性の失神、起立性低血圧、不整脈などの心疾患による失神など、意識を失ったりもうろうとしたりする病気は、一般の方々が考えているほど珍しいものではないと言えるかもしれません。本人も連絡が取れなかった時の記憶が曖昧で、原因が分からない状態でした。
私はAさんに専門性の高い大病院での検査受診を促しました。詳細は省きますが、結果、原因となった疾患の診断がつき、治療が開始されました。この診断によって、職場でのAさんへの評価は一変しました。それまで「無責任な人物」だと疑われていたのが、「病気だったのなら仕方ない」「実は本人も困っていたのだ」という理解へと変わったのです。
そこから、「意識を失うことを防ぐために職場としてどのような配慮ができるか」「意識を失った場合、周りはどうすれば良いか」といった建設的な議論ができるようになり、両者が納得感を持ちながら課題解決に向けて進むことができました。
このエピソードは、職場と従業員の間に生じるギャップに対し、産業医がその“橋渡し役”になれるケースもあるという分かりやすい例だと考えています。仮に、Aさんがご自身の判断で受診して診断書を持ってきた場合でも、ご自身のみでは疾患に関する詳細な説明は難しいかと思いますので、職場の理解を得ることが困難だったかもしれません。あらかじめ産業医が双方から丁寧に話を聞き、医学的な見地を交えて説明することで、関係者の納得感が得やすくなることを実感しました。
後編につづく
【関連記事】
・社員の健康意識を変える!人事と二人三脚の取り組みとは―産業医インタビューvol.1前編
・「元気です」に潜むSOSを見抜く!メンタル不調社員を救うには―産業医インタビューvol.1後編
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
エムスリーキャリアが提供する専属・嘱託・スポット、すべての「産業医サービス」について分かりやすく1冊にまとめたサービス紹介パンフレットです。 お悩み別にオススメの産業医サービスがひと目でわかります。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け