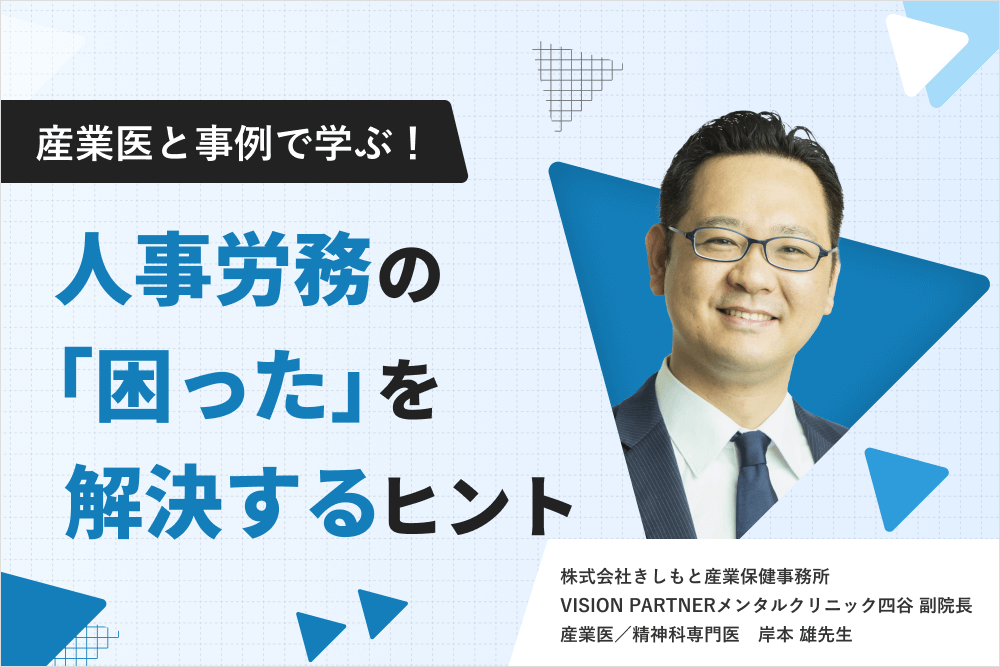
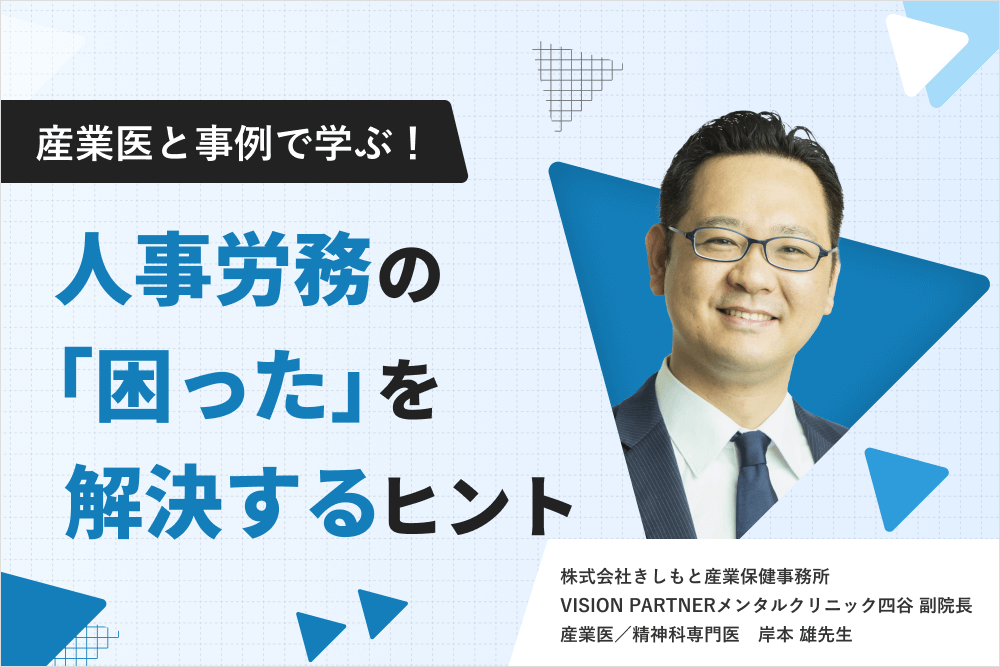
日頃、社内の産業保健対応をするにあたり、「こんな時どうしたらいいんだろう」「他社はどう対応しているんだろう」と思い悩むことはありませんか。
『産業医と事例で学ぶ!人事労務の『困った』を解決するヒント』では、VISION PARTNERメンタルクリニック四谷 副院長・岸本雄先生に寄稿いただき、産業保健で起こった事例(※)に基づいた対応、そういったケースを未然に防ぐTipsを取り上げていきます。
※事例の細部は変更してご紹介しています。
人事担当者としては「強く言えばハラスメントになるのでは」と悩み、会社としてもどこまで踏み込んでいいのかわからない——そんな状況かもしれません。
上記のような面談や受診を拒む社員は、皆さんの職場にもいらっしゃるのではないでしょうか。
特にメンタルヘルス不調の場合、自分が病気である自覚(病識)が持ちづらく、「本人の権利・意思の尊重」と「会社の安全配慮義務」のあいだで板挟みになることがよくあります。
このような場面で大切なのは、焦って「面談させよう」とするのではなく、冷静に丁寧に“手続きを踏んでいくこと”です。
今回は、従業員に面談を拒否されたときの初動対応、つまり最初の「手続き」について一緒に考えていければと思います。
目次
皆さんもご存じかもしれませんが、会社は安全(健康)配慮義務(労働契約法第5条)を負っています。これは「社員の健康リスクを見過ごさず、必要な配慮を行う義務」と意訳しても良いかもしれません。
近年の裁判例では、企業が健康管理のために必要な手続きを取っていれば、仮に本人が面談や病院受診を拒否し結果的に悪化した場合でも、その責任が一定程度軽減される傾向があります。逆に、記録や説明がなく「何も措置を講じていない」と見なされた場合、会社は義務を果たしていなかったと判断されかねません。
そのため、人事が最初に意識すべきポイントは「とにかく面談をさせる」ことではなく、「会社としてどのように誠実に対応したか、その手続きと記録を残すこと」になります。
面談や受診拒否に焦るのではなく、冷静に“手続きを積み重ねる”こと。
それが結果的に会社だけでなく、時に従業員を守ることにもつながるのです。
面談や受診を拒否する従業員は、単純に「必要ない」と思っているから拒否をしているのでしょうか?
最終的に産業医面談や精神科の初診で出会う人達のお話をうかがうと
「まさか自分が病気になるとは思っていなくて…」
「周囲に迷惑をかけたくなくて」
「病気だとわかってしまうのがこわかった」
「『病気だ』と思われたらキャリアに響く」
「病気になった人が休んでいる間にどんな風に言われているか知っているから…」
といった罪悪感や不安、時には“職場への不信感”について耳にすることが多いように思います。
表面的には「必要ない!」と怒っているように見えても、その裏には複雑な思いが隠れている。
そのことを一度立ち止まって考えてみると、「ただ面談を強く勧め続ける」ことがあまり意味をなさないことに気づけるかもしれません。
ここで大切なのは
「会社はあなたを評価・批判するわけでもないし、病人のレッテルを張るために面談や受診をすすめているわけではない」
「健康に、安全に働き続けてほしい。そのために必要な確認なんだ」
というメッセージを伝えることです。
会社からのメッセージを丁寧に伝えるための「手続き」……その一つの方法が、次に紹介する「3回ルール」です。
面談拒否が起きたとき、感情や焦りで押し通そうとすると、お互いに緊張や反発が生まれ、疲弊するだけになってしまいます。「健康に、安全に働き続けてほしい」というメッセージを段階的に伝えつつ、記録に残していくことが重要です。それが結果的に、「会社として十分な努力を尽くした」という証拠になりえます。
最初に行うのは「拒否の言葉の裏にある思いについて丁寧に聞くこと」です。拒否的になっている従業員さんの裏にはいろいろな思いが浮かんでいます。時にはうまく言語化できていないこともあるかもしれません。だからこそじっくり「相手の思い」を聞き出してみることです。十分にその思いを聞き出したのちに改めて
「産業医面談や病院受診は、あなたを批判したり人事評価のために行うものではありません」
「健康に働き続けていただくための確認です」
と伝えます。また、ちょっとした言葉の選び方で相手の反応が大きく変わることもあります。
| NGワード | OKワード |
| 「最近のあなたの勤務態度は問題がある」 | 「体調や集中に波があるように見える」 |
| 「最近ミスが多い気がして…」 | 「お仕事の中で少し負担がかかっているように見えます」 |
| 「仕事を任せられません」 | 「安全に仕事が続けられる状態なのか確認したい」 |
| 「産業医面談を受けなさい」 | 「元気に働き続けるためにどんな工夫ができるか、専門家に聞いてみない?」 |
説明したあとは、「いつ・どこで・どんな内容を話し、相手がどう反応したか」をメモに残します。
会話が成り立たなかった場合も、その事実を残しておきましょう。
さて話はしたものの、それでも受診や面談を拒む場合、もしくはそもそも話かけても聞いてくれない場合はどうしたらいいのでしょうか?その場合は数日〜1週間おいて、今度はメールまたは社内チャットで文面を送ります。この段階では、
など、本人が話しやすい配慮や代替手段を提示します。
例:「面談や受診を勧めているのは、ご自身に健康で安全に働き続けていただくためです。
対面が難しければオンライン面談も可能ですし、信頼できる方の同席も調整できます。」
返信がなくても、「送付した事実」「寄り添おうとした証拠」が残ることが重要です。
それでも応答がない場合はどうするか?3回目からは若干「フォーマル」な文書になります。ここでようやく“会社は「あなたの心身の安全を守るために必要な措置を講じる」義務がある”ことを伝える形になります。
「この面談及び病院への受診勧奨は、会社としての安全配慮義務を果たすために必要なものです。ご協力が得られない場合、あなたをこのまま『安全に働かせていい状態なのか』判断することが難しくなります。結果的に、あなたの健康状態が確認できるまでは、一時的な勤務制限などの対応を検討せざるを得ない可能性が出てきます。」というトーンに変わってきます。
この通知書とともに、これまでの説明内容や本人の反応を時系列で整理しておくことも忘れないでください。こうした一連の記録こそが、会社が果たすべき“手続き”です。
面談や受診を拒否される場面では、「どうすれば面談(受診)してもらえるか」より、「いかに誠実に手を尽くしたか」という軸で考えたほうが、少し気持ちが落ち着くかもしれません。
そして、そのポイントは次の三つです。
誠実な手続きを重ねる中で、ふとした瞬間に従業員の気持ちが和らぎ、面談や受診に応じてくれることもあります。
ただ、努力を重ねても状況が変わらないこともあります。そのときこそ、人事が冷静に「線引き」を考える場面です。次回は、この“けじめの境界線”をどのように引くか、一緒に考えていきたいと思います。
本資料は、企業担当者様が従業員の方に配布することを目的とした資料になります。 内容を編集してご利用いただけるよう、PowerPoint形式でご用意しております。 【資料の内容】 ・従業員の皆様へ:産業医と面談してみませんか? ・産業医面談の流れ ・よくある質問:Q1.産業医との面談内容は会社に伝わりますか? ・よくある質問:Q2.産業医と面談する意味は?面談した後はどうなるの? ・一般的な産業医への相談と事後対応例 ・産業医プロフィール
産業医面談の受診勧奨を促すWord形式の参考例文フォーマットです。 参考例文をコピー&ペーストしてそのままメール文として送れるものになっています。産業医面談が義務である従業員用、努力義務である従業員用の2種類をご用意していますので、用途に応じて使い分け可能です。 本フォーマットを活用いただくことにより、速やかに産業医面談の受診勧奨をすることができます。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け