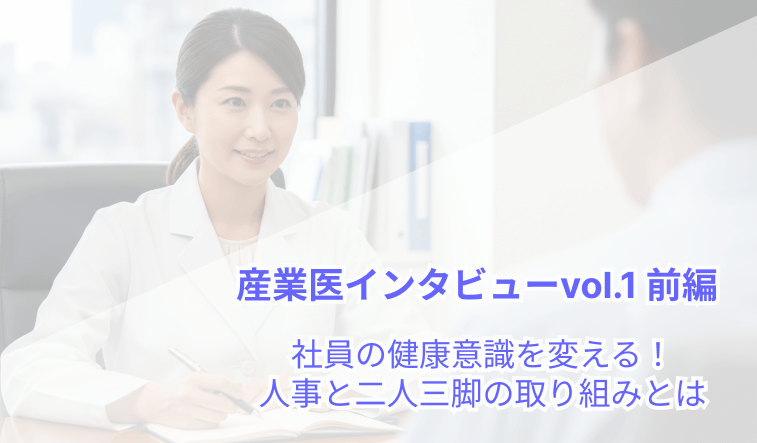
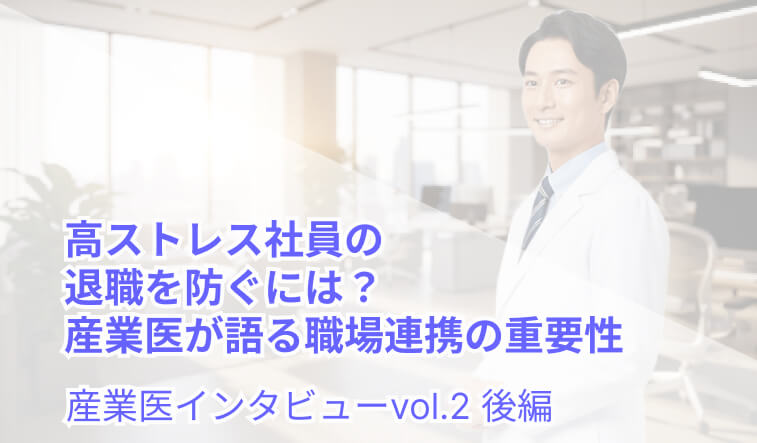
従業員の健康を守り、活き活きと働ける職場環境を整備することは、企業にとってその重要性が増しています。しかし、産業保健活動には「唯一の正しい答え」があるわけではありません。リソースも限られる中で効果的な産業保健活動を実現するには、産業医などの専門家と連携することが必要です。
前編に引き続き、精神科専門医・指導医、精神保健指定医の資格を持つ産業医・三宮先生(仮名)にインタビュー。後編では、先生がこれまで経験された印象的なエピソードから、企業が産業医と連携する上で特に力を入れるべき点などについて深掘りします。

|
精神科専門医・指導医、精神保健指定医の資格を持ち、病院勤務医としても活躍。これまで7年間で、従業員50人未満から300人規模の企業を中心に、合計10社の嘱託産業医を務める。 現在は5社の嘱託産業医を担当。企業と従業員にとっての最適な着地点を見出すことをモットーとしている。 |
――これまでの産業医活動で、特に印象に残っているエピソードがあれば教えてください。
身体的な健康問題では、健診で高血圧とわかっていた従業員が業務中に脳出血で倒れ、麻痺が残って職を辞めざるを得なくなったケースが印象に残っています。病院には通って服薬もしていたのですが、それでも血圧が少し高かったんです。そうした状況で就業を止めるわけにもいかない難しさがあります。「どうすれば防げたのか」と、産業医として深く考えさせられました。
精神的な健康問題では、適応障害かうつ病の兆候があったにもかかわらず、それが拾いきれないまま退職してしまった若手社員のケースがあります。その社員は、会社側からしてみると特別に心配すべき様子もなかった中で突然の退職申し出があり、「実はストレスチェックで高ストレスと判定されていたが、誰にも相談できなかった」という話が出たんです。これには上司含め会社の方々が驚いていて、「なんとかできたのではないか…」と悔やまれました。こうした事態を防ごうにも、誰が高ストレス判定を受けたか分からない難しさがあります。
こうした経験から、せめて中間管理職によるコミュニケーションは増やし、従業員の異変を早めに察知する重要性を感じています。そして残業を減らして早く帰らせるなど、具体的な対策を講じることの大切さも再認識しました。また、就業規則を厳格にしすぎず、個別のケースに合わせて休職などの対応を柔軟に行うことも重要です。
それから、新卒採用を始めたばかりで若手の扱い方に試行錯誤している会社のケースも印象的です。精神的な健康問題の場合、病名がつく前の、いわゆる軽症の段階でいかに問題を拾い上げるかが非常に難しいんです。症状が顕在化して明らかにわかるレベルでは、すでに重症化していることが多い。管理職の方々には、メンタル不調の兆候となる行動の変化をなるべく具体的にお伝えするなど、早期に異変を察知できるような仕組みづくりにもがいている状態です。
――先生が特に力を入れたい分野はありますか?
各企業が気軽に相談できる、いわば「病院の専門家」のような存在を企業ごとに作りたいと考えています。健診を受ける医療機関は各社で決まっていると思いますが、その後の精密検査や受診先は従業員各自の判断に委ねられているのが現状です。異常値が出た時に「何科を受診すればいいのか」と迷う従業員は少なくありません。
そこで、企業に優先相談病院のようなものを持ってもらいたいんです。「企業のかかりつけ医的な存在」ですね。かつては開業医が自身のクリニックで身体的な問題に対応すればよかった時代もありましたが、精神的な問題は対応できない開業医も多い。だからこそ、最寄りの医療機関をいくつかピックアップして提案するようにしています。
たとえば、精神的に調子が悪そうな従業員を上司が発見し、産業医面談を希望されたケースがありました。事前情報からすぐに受診が必要だと判断できましたが、面談希望日は翌週や翌々週になってしまう。そこで、すぐに精神科にかかってもらうよう促し、結果的にうつ病と診断され休職、実家に戻って立て直すことになりましたが、円満退職につながりました。このように、いかに早く適切な医療機関につなげられるかが重要だと考えています。
――最後に、企業の人事労務担当者の方々へ、産業医との連携に関するアドバイスをお願いします。
専門知識をひけらかす産業医は、企業には必要ありません。企業に必要なのは、質問したら「わかる/わからない」を明確に答えられ、適切な“仕分け”ができる、人当たりがよくて決断ができる産業医です。
もし現在の産業医との連携に課題を感じているのであれば、産業医を替えることを我慢しないでほしいと伝えたいです。企業は産業医を雇っている側ですし、替えられたからといって激昂する医師はまずいないでしょう。
――今後、先生がチャレンジしたいことはありますか?
復職者のオーダーメイドの復職プランを人事の方と一緒につくり、100%の復職を実現したいですね。以前、それを実現しようとした矢先に退職となってしまったりと、なかなか実現できていません。復職を見届けるだけでなく、あわよくばその後の出世まで見届けられるような関わりができれば、産業医として最高の喜びだと感じています。
厚生労働省では「労働者の心の健康の保持増進のための指針」を定めており、職場におけるメンタルヘルスケアを推進しています。 この指針では、メンタルヘルス対策には4つのケアがあると定義されています。 本資料では、この4つのケアを軸とし、弊社が推奨する取組事項をまとめ、チェックリストにしています。 「セルフケアに関する取り組みが足りていない」「事業場外資源によるケアを行えていない」等、各領域の取り組み状況の確認にご活用ください。
50人以上の事業場向け
1,000人以上の事業場向け
※有害業務従事の場合は500人以上
単発の面談が必要な事業場向け